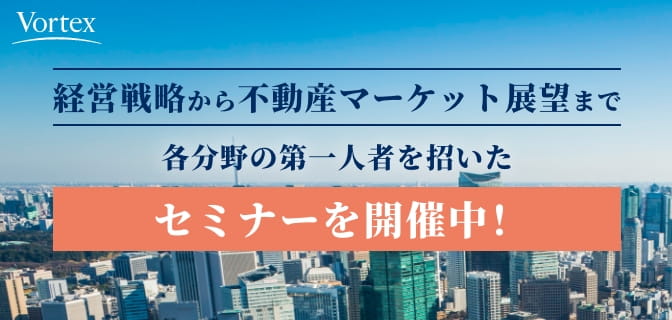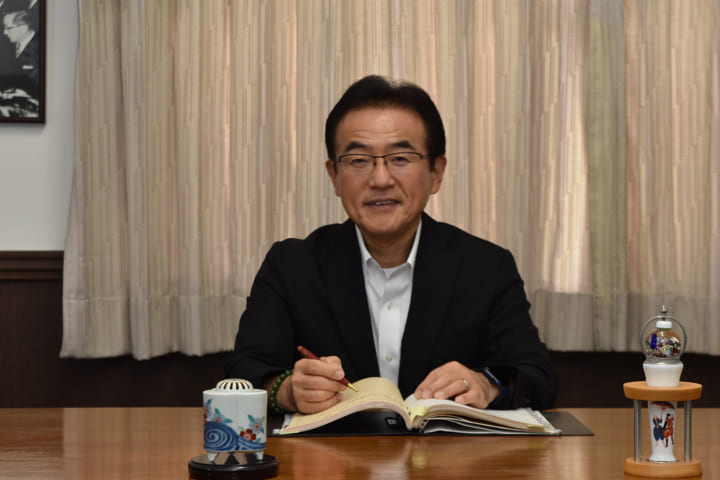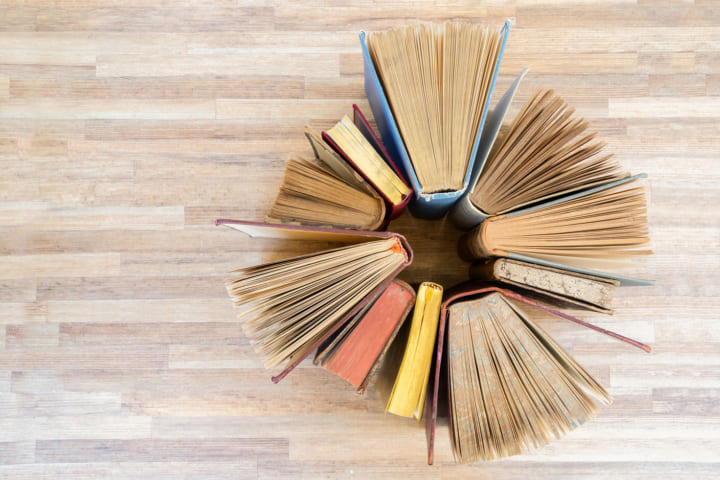DXの真髄は産業構造・企業経営の変革にあり
〜100年企業が実践してきたCXとは〜

目次
DX推進が急務といわれながらも、各企業の意識には温度差があります。「日本企業は違う方向へ向かっている」と危惧するのは、かつての産業再生機構時代から約20年に渡り、日本経済の活性化を牽引してきた西山圭太氏と冨山和彦氏です。DXとは、ツールやシステムの話ではなく、産業構造や企業経営の変革であり、変化の激しい現代において生き残るための戦略だといいます。企業はどのように取り入れるべきか、対談形式で詳しくお聞きしました。
西山圭太氏・冨山和彦氏 登壇! オンラインセミナー
イノベーションは“パクリの掛け算”である
冨山 イノベーションは「技術革新」と訳されますが、これが誤解を生む大きな原因なのです。イノベーションを提唱したシュンペーターは、「新結合」という言葉を使って説明しています。つまり「既存のAと既存のBをくっつけたら新しいCになる」というのが真意であって、少し乱暴な言い方をすれば“パクリの掛け算”です。ところが技術革新という訳が定着したことで、日本ではイノベーション=発明だと思われるようになってしまいました。
西山 レシピのつくり方と似ていますよね。どんな料理も既存の調理法や素材が組み合わさってできています。その中からたまに画期的なレシピが生まれることはあっても、まったく1から生み出されたレシピなんてないですからね。
冨山 イノベーションを「発明」と捉えてしまうと、自前発明主義にならざるを得ません。本当は、自前発明主義は最もイノベーション的ではないのです。でも日本的経営モデルはどうしても違う解釈になってしまうことが多いですね。
かつてソニーと松下を比較して、ソニーのほうがイノベーティブだと言われましたが、あれは逆だと私は思っています。松下電産が長年かけて築き上げた大量生産のノウハウと販売チャネルのプラットフォームがあって、そこにソニーのインベンションが合わさったのです。これこそ「新結合」としてのイノベーションでしょう。
西山 DXへの向き合い方にも同じことが言えると思います。自分で1からすべてを勉強する必要はないのです。
テクノロジーは、素人にも直感的に操作できる方向に確実に進んでいて、その傾向は今後ますます加速します。これはユーザーインターフェイスに限った話ではなくて、デジタルリテラシーの低い人が、デジタルをツールとして使いたいときの課題を、日常会話に近い感覚でITやAIのプロに伝えられるようになるはずです。
「これからの時代、プロが学ぶプログラミングの初級レベルくらいはマスターしておかないといけない」という勘違いが横行しているように思います。ユーザーに必要なことは、プロの初歩をマスターすることではなく、デジタル化の本質とみずからのビジネスとの関わり、向き合い方を大づかみに理解することです。
冨山 でも明らかに、その方向へ進んでしまっています。DX対策で多くの人材を抱えたり、みんなでプログラミング言語を勉強したりする企業が増えているようです。プロが別のレイヤーにいるのだから、自分たちで内製しようという発想はいまの時代に合っていません。
西山 ユーザーとして知るべきことを知っていればいいのだと思います。細かな知識はなくてもいいですが、感覚的に知ってなじむことが必要ですよね。
CXの実践で生き残ってきた100年企業
冨山 世界ではすでにインダストリアル・トランスフォーメーション(IX)が進み、社会や産業構造は、大企業が頂点に立つピラミッド型から多数のレイヤーで成り立つミルフィーユ型へと変貌しています。そこにフィットしない日本的経営モデルが過去の遺物となる中、日本企業が生き残っていくためにやるべきこと。それは、DXのような業務改善レベルの対策ではなく、会社を根こそぎ変えるコーポレート・トランスフォーメーション(CX)です。
西山 近年、企業も経済システムも生命体のようになってきていると感じます。環境の変化が激しいので、環境に適用できる人が組織で生き残る。当たり前のようですが、長寿企業、100年企業はそれができたから続いているのだと思います。まさにCXを実践し、変わるものと変わらないものを見分けて取捨選択することによって、いまに至っているはずです。
人間の悩みがいつの時代もそんなに変わらないのと同じで、時代が変わっても企業の提供する価値、顧客が解いてほしい課題は根本的に変わらないと思うのです。ただ解き方は時代とともに変わってくるので、取り込んでいかないといけません。
冨山 たとえば、昔はテレビを買うこと=コンテンツを買うことだったけれど、YouTubeやNetflixの台頭で、テレビは単なるディスプレーになってしまった。どんなに優れた製品やサービスを提供していても、産業構造の変化によって、自社の立ち位置も変化してしまいます。ただ、そのときどう変わればいいのかは、教科書に書いているわけではありません。
西山 何かを参考にするとき、それが具体的な話のほうがいいと思われがちです。手っ取り早く正解を知りたいと思う気持ちはわかります。でも本当に参考になるのは、そのままではないけれど似ている、少し遠い話のはずです。正解は自分で考えるしかありません。
冨山 講演や書籍でケーススタディが好まれるのは、その典型です。既存の事例は大事ですが、イノベーションのきっかけは既存の事例を参考にしただけでは生まれません。抱えている問題を解決したいと思ったら、具体化で終わらせず、抽象化して本質に当たらないといけません。ベストプラクティスから正解を得られることはないのです。
レイヤー化した産業構造の中で立ち位置を探す
西山 新しいレイヤーが誕生すると、産業構造の変化は免れません。製薬業界もその一例です。個々の製薬会社の研究室で薬を開発し、承認を取って売るというのがかつてのモデルでした。しかしデジタル的に解析して特定の物質を見つけることができるようになって以降、そのサービスを提供するレイヤーができました。そうすると、自社独自の工程を持つことができなくなり、製薬企業各社はそのレイヤーの企業と取引していくことになるわけです。
冨山 自分でつくらずに、分業するような形ともいえますね。新しいレイヤーが生まれるときは、旧来の匠的なものも否定してしまうことになりかねず、反感的な気持ちになることもあります。でも、これからは産業構造や自分の立ち位置が変わっていくのを面白がれるくらいの、好奇心を持つことが必要でしょうね。
西山 さまざまな分野、ビジネスで似たようなことが起こっていると思います。同業他社を見るのではなく、むしろまったく違うジャンルに目を向ければ、自分と似たような、しかし違いがヒントになる立ち位置の企業が見つかるかもしれない。そうすると、ミルフィーユを形成するたくさんの層の中のどこに自分がいるのか、客観的に感じられると思います。
冨山 それにはやはり、具体化と抽象化を行ったり来たりする思考の工程が非常に大事です。あの有名なスティーブ・ジョブズもまさにそれを使いこなしていました。いまは、行ったり来たりが価値を生む時代になったとも言えるでしょう。
お話を聞いた方

西山 圭太 氏
東京大学未来ビジョン研究センター客員教授
/経営共創基盤(IGPI)シニア・エグゼクティブ・フェロー
東京大学法学部卒業後、通商産業省入省。1992年、オックスフォード大学哲学・政治学・経済学コース修了。株式会社産業革新機構執行役員、東京電力ホールディングス株式会社取締役、経済産業省商務情報政策局長などを歴任。故・青木昌彦教授や各国首脳のブレーンとの知的交流を結び、今日のRCEPにつながる東アジア包括的経済連携協定構想の立ち上げなどに関わる。冨山和彦氏と産業再生機構、東電再建と電力システム改革にて協業。時代の数歩先を行くビジョナリーとして、日本の経済・産業システムの第一線で活躍。2020年に退官、現在に至る。近著に「DXの思考法」(文藝春秋)。

冨山 和彦 氏
経営共創基盤(IGPI)グループ会長
/日本共創プラットフォーム(JPiX)代表取締役社長
東京大学法学部卒業、在学中に司法試験合格、スタンフォード大学経営学修士(MBA)。ボストンコンサルティンググループ、コーポレイトディレクション代表取締役を経て、2003年に産業再生機構設立時に参画しCOOに就任。解散後、2007年に経営共創基盤を設立し、代表取締役CEO就任。2020年10月より現職。2020年日本共創プラットフォーム設立。パナソニック社外取締役。経済同友会政策審議会委員長。財務省財政制度等審議会委員、内閣府税制調査会特別委員、内閣官房まち・ひと・しごと創生会議有識者、内閣府総合科学技術・イノベーション会議基本計画専門調査会委員等も務める。『コーポレート・トランスフォーメーション 日本の会社をつくり変える』(文藝春秋)など著書多数。