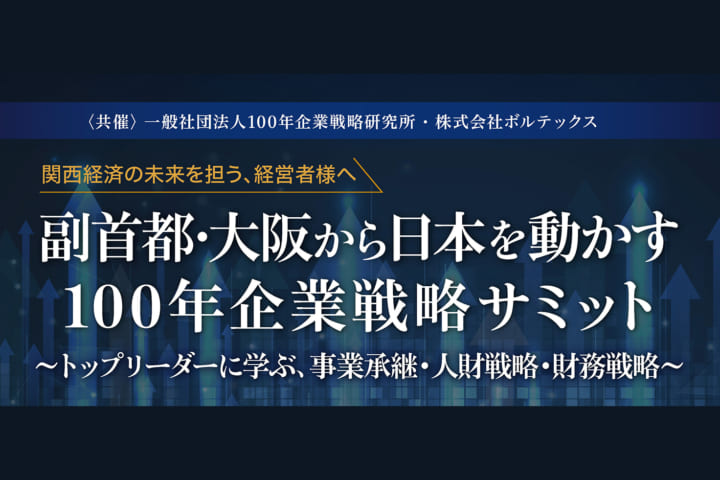日本を代表する老舗旅館が大事にする会社の存在意義
〜社会に対してどのように貢献するのか問い続ける〜

目次
和倉温泉(石川県)の旅館「加賀屋」は、その行き届いたサービスが海外からも評価され、日本を代表する宿泊施設の一つになりました。1906(明治39)年創業の温泉宿を日本一の旅館に育て上げた小田禎彦代表取締役に、加賀屋が実践するおもてなしの本質を伺いました。
ピンチをチャンスに変えた台湾の加賀屋
早いもので、私はもう60年以上も観光業界で働いてきたことになります。東京の大学を卒業して帰郷し、家業の加賀屋に入社したのは1962(昭和37)年でした。最初の東京オリンピックが開催されたのは、その2年後です。したがって、まだ新幹線も高速道路もなかった時代です。そして、加賀屋も北陸を中心に名が知られる程度の温泉旅館でした。
ところが、いまや加賀屋に宿泊することを楽しみにして、海外のお客様がわざわざ能登半島を訪ねてくださる時代になりました。当時を振り返ると隔世の感がありますが、当然ながら、その間には加賀屋もさまざまな試練を経験しています。
1976(昭和51)年に始まった「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」というランキングイベントでは、おかげさまで、通算41回も総合1位の栄誉をいただくことができました。しかしその内実は、常に挑戦の連続。ようやくにして高い壁を乗り越えたら、すでに次の壁が目の前に立ちはだかって行く手をはばんでいるという感覚で、3代目の社長に就任した1979(昭和54)年以降、ほとんど気が休まる間もありませんでした。
しかしながら、今にして思えば、そうして難題を一つひとつ克服してきたことが現在の加賀屋につながったといえます。つまり、真正面から困難と対峙して、その解決に知恵を絞ってきたからこそ、企業として成長できたわけです。記憶に新しいところでは、新型コロナウイルスのパンデミックも深刻な試練でした。
ご承知の通り、パンデミックは全国の観光関連の方々に甚大な影響をおよぼし、私どもでも2021年には前年比で6割もお客様が減りました。パンデミック以前には1日あたり400名から500名のお客様を迎えていたのですが、ひどいときには1日30名程度という日もありました。
まさに存続の危機といえる状況でしたが、その原因がはっきりしていたため、いつもと変わらず、加賀屋のおもてなしを淡々と続けるよりないと腹を決めていました。先に倒れるのは私どもかパンデミックか、いわば根比べのようなものでした。
しかし、そうしたなかでも台湾の北投(ペイトウ)にある加賀屋では2010(平成22)年の開業以来、最も好調な業績で2022(令和4)年を終えました。日本を訪れることはできないものの、台湾にいながら日本を感じることができる場所があるということで、お客様が連日、台湾全土から殺到したそうです。「禍福はあざなえる縄のごとし」といいますが、ピンチとチャンスは紙一重の差でしかないということなのかもしれません。
サービスの本質は「正確性」と「ホスピタリティ」にある
私どもの創業は1906(明治39)年にさかのぼります。祖父の小田與吉郎が田畑を売り払って12室の温泉旅館を買い取り、農業から旅館業に転じたのが加賀屋の始まりでした。
我が祖父ながら、よく思い切ったものだと感じますが、それ以来、祖父の時代も、祖父を継いだ父と母の時代も爪に火を灯すような暮らしぶりで、朝から晩まで懸命に働いて小さな旅館を守ってきました。その姿を見て育った私には、なんとか潰さずに旅館を受け継いで次世代につなげなければならないという気持ちしかありませんでした。
祖父はもちろん、私の両親も旅館経営の素人で、とりわけ実父が地元の町長を務めていた家庭に育った母は、当初、旅館の女将という立場に苦労したようです。とにかくお客様の前に出るのが恐ろしかったそうで、ある日、勇気を振り絞って玄関先に座り、お客様のお出迎えとお見送りに努めていたところ、その様子を目にした父に「お客様用の座布団に女将が座ってどうする」と叱られたといいます。玄関先で足元を整えるお客様のために用意されていた座布団の意味すら、当時の母は知らなかったのです。
そうして失敗を重ねながら、お客様に満足していただくには何をすればよいかと素人なりに考えて、母はお客様をお迎えしてからお見送りするまでに必ず10回はお茶を入れ替えることを日課としました。現代の感覚でいえば、そう頻繁に部屋へ入ってこられると、お客様もゆっくりできなかったのではないかと思いますが、当時はそうしたサービスが丁寧な接客と受け取られたようで、徐々に来客数が増えていきました。
そして、見逃してはならないのが、母が従業員に対しても感謝の気持ちをことあるごとに伝えていたことです。おそらく、自分自身が接客やサービスに苦労しただけに、従業員に対する感謝の気持ちが強かったのでしょう。自分の子供たちは放っておいても、客室係の若い女性や板場で働いてくれる職人たちへの配慮を欠かしませんでした。そうした姿勢が従業員との間に信頼関係を生み、結果としてお客様に対するサービスの向上にもつながったのではないかと思います。
実際、かつてはベテランの“おねえさん”が若い客室係の後輩に「あんたのような若いモンがそういう態度やと、日本一の旅館が泣くがいね」と、親身に指導する姿をよく見かけたものです。東京から戻ったばかりの私が何を言っても耳を貸そうともしなかった客室係の女性たちも、おねえさんたちの言葉には素直にうなずいていました。こうしたやりとりにこそ、私は加賀屋の強みがあらわれていると思います。
私は、サービスの本質とは「正確性」と「ホスピタリティ」にあるという考えで加賀屋を運営してきました。客室係の女性がどんなに明るい笑顔でお客様を迎えても、お勘定を間違えるようでは、信頼を得ることはできません。また、お客様に対して的確に接することができても、仏頂面ではお客様も加賀屋を訪れてよかったとは思わないでしょう。正しいおもてなしと相手を思いやるやさしい気持ちを両立させなければ、十分なサービスとはいえないのです。今、あらためて、そうした加賀屋の原点を見つめ直す必要があるように感じています。
旅館業とは「明日への活力注入業」
とはいえ、時代は変わります。サービスのあり方も、お客様の嗜好や価値観の変化に合わせて、ふさわしいスタイルに変わらなければいけません。
じつは、先日、そうした変化を実感する出来事がありました。修学旅行の学生さんたちにアンケートへの回答をお願いしたところ、食事について「ウニが気持ち悪かった」「刺身よりハンバーグがよかった」といったご要望があったのです。もっとも、年齢を重ねれば学生さんたちの嗜好も変わるのでしょうけれど、私にとっては時代の変化に考えをめぐらせるよいきっかけとなりました。
そうした変化にさらりと対応できるのは、やはり彼らと近い価値観をもつ世代の従業員です。私どもにとって、今後は人材採用と育成がますます重要な経営課題となるに違いなく、現在は働きやすい職場環境の整備が喫緊の課題と受け止めています。一泊二食付きという宿泊スタイルに応じて、旅館業には独特の勤務シフトが定着しているのですが、変則的な勤務シフトは敬遠されがちです。従来のサービスを維持しながら、いかに働きやすい勤務体系を確立するか、難問ではありますが、解決に向けて知恵を絞らなければいけません。
こうした目の前の問題に取り組みながらも、永続企業をめざすうえで大切なことは、自社のミッションを正しく把握し、経営判断を誤らないことだと私は思います。
たとえば、飛行機や新幹線の存在意義が乗客の移動時間を短縮することにあるとすれば、航空業界や鉄道業界は「時間短縮補助業」と表現できるでしょう。では、旅館業をどう表現するか。私は「明日への活力注入業」と言いたいと思います。
単に日ごろの疲れを癒すだけでなく、つらいことがあっても「明日からがんばろう」と思っていただけるような時間と空間を提供することが、私どもの存在意義なのです。本質を見失わなければ、企業は社会から必要とされ続けるのではないでしょうか。

(お話を聞いた方)
小田 禎彦 氏(おだ さだひこ)
株式会社加賀屋 代表取締役
1940年生まれ。1962年立教大学卒業後、加賀屋に入社。1979年代表取締役に就任。会長、相談役を経て2022年再び代表取締役に就任。1906年創業の加賀屋は従業員1,100名、年商140億円(いずれもグループ計)。「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」で総合1位を通算41回獲得するなど、日本を代表する温泉旅館として知られる。客室総数233室。
[編集] 一般社団法人100年企業戦略研究所
[企画・制作協力]東洋経済新報社ブランドスタジオ