仕事で燃え尽きず、生産性を高めて「働きながら本が読める」社会を
仕事と文化の両立が、人も組織も成長させる

目次
働き始めてから読書を楽しめなくなった。仕事に追われて本を読む時間がない。ついスマホばかり見てしまう……そんなビジネスパーソンの実情を言い当てているのか、『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)が30万部のベストセラーとなり話題です。働き方改革が進んでいるのに、なぜ読書ができないのでしょうか。どうすれば働きながら本を読める社会が実現するのでしょうか。著者の三宅香帆さんにお話を伺いました。
働くことで本が読めなくなってしまう?
私は子どもの頃から、外で遊ぶより家の中で本を読んでいるのが好きというタイプでした。本について勉強したくて文学部に進学。学生時代までは思う存分、本と接する時間を過ごしていたんです。
ところが就職したとたん、そんな生活が一変します。平日は毎朝9時半から夜の8時過ぎまで会社にいる。「こんなに働きっぱなしで、みんな普通に生活しているの?」というのが率直な思いでした。
もちろん、これくらいの働き方は、今の日本では特別ハードじゃないことは理解しています。それに、仕事そのものに不満があったわけではありません。会社の仕事は、個人では到底扱うことのできないスケールの大きさがあります。
私はWebマーケティングを推進する部署にいたのですが、取り扱う案件も大きく、またサイトの更新や仕様変更も速くて、そのスピード感にも魅力を感じていました。職場もいい人たちばかりで、働くこと自体は楽しかったのです。
でも、あるときふと気がつきました。「そういえば私、最近全然本を読んでいない」と。
読もうと思えば、電車に乗っている時間や寝る前の時間に読めたはずです。だけど、それができなかった。本を開くよりも、なんとなくスマホに手が伸びてしまって、SNSやYouTubeを見てしまう……。
似たような話は同級生からも聞きました。みんな「社会人になってから、思うように本を読めなくなったよね」と言うのです。ああ、私だけじゃないんだ。本を読みたいんだけれども読めなくなった人って、結構多いんだ、と思いました。
「やっぱり、大好きな本をもっとじっくり読める暮らしがしたい」――そう思って私は3年半で会社を辞めました。すると、ゆっくり本を読む時間がとれて、今は本について評論をする仕事をしています。やっぱり、会社で働きながら十分に本を読むことは難しかったんだ、と改めて実感します。
働き方改革で労働と文化は両立できるのか
こうした経緯をブログに書き始めたら、多くの方から「自分もそうだった」という声をいただきました。そもそも日本の働き方自体が、ゆっくりと本を読めるような状態ではない。どうやらそれが「当たり前」らしいのです。
でも、それってどうなんでしょう。本が読めない働き方が普通とされている社会って、おかしくない!?というのが私の疑問でした。
もちろん、これは読書に限ったことではありません。私にとっては「本を読むこと」ですが、別の方にとっては「好きな音楽を聴くこと」であったり、「家族とゆっくり過ごすこと」であったり、「行きたい場所に旅行に出かけること」であったりするかもしれません。
私にとって読書が人生に不可決な「文化」であるように、それぞれの人に大切な「文化」があると思います。自分の人生にとって大切な文化的な時間を、働くことのためだけに奪われてしまってよいのでしょうか。労働と文化を両立させる働き方があってもいいはずなのに、そのことが難しい社会になっているのが現実です。
「働き方改革」の推進で、昔に比べたら労働時間はかなり減っているのではないか――という指摘はそのとおりだと思います。ただし、昔の日本の働き方は、基本的に誰かが家にいてくれる、つまりお母さんが専業主婦として家事と育児に専念し、お父さんが外で働いて一家の家計を支えるというモデルがあったと思います。
その時代と比べると、今は一人でそこまで稼ぐのが難しくなっていて、共働きでようやく一家の生計が立てられるというケースが増えています。
子育てにかかる時間も増えました。たとえば、昔は子どもだけで通学したり遊んだりする光景が見られましたが、今はセキュリティの観点からそれは危険だとされる世の中になっています。仕事が早く終わっても、あるいは休日が増えても、子どもの送り迎えや付き添いに必要な時間は格段に増えています。労働時間が減っても、家事や育児に割く時間を考慮すれば、単に働き方改革が進んだからいいだろうということにはならないはずです。
「全身全霊」を捧げる働き方の見直しを
高度経済成長以来、日本の会社では「仕事に全身全霊を捧げること」「会社にフルコミットする働き方」が求められ、長時間労働が常態化してきました。
当時を経験した世代の皆さまや、現在も100%の力でバリバリ仕事をされている方は、「仕事に全力を尽くすからこそ、能力は発揮されるし、自分の成長にもつながるものだ」という感覚をお持ちかもしれません。
もちろん私も、そういう面はあると思っています。ほどほどの力で成果を出せるほど世の中は甘くはないですし、時間をかけないとできない仕事もあります。
一方で、100%の働き方をどこまでもずっと続けられるのかという疑問もあります。
働き方改革で会社から長時間労働を強制されることはなくなったとしても、家事や育児に時間をとられて余力がなかったり、あるいは働く人自身が「もっと頑張れる」「努力して成果を上げなければならない」という気持ちになって頑張りすぎてしまうことが現代社会の特徴です。
このままでは「働きながら本が読める社会」はいつまでたっても訪れません。それどころか、働く人のメンタルヘルスが悪化し、ひいては企業に業績の悪化をもたらします。
目の前の成果のためには頑張ることも必要ですし、ある一定期間は仕事に打ち込むこともキャリアには必要です。しかし、それは長くは続かない。長い目で見たら、私は人ぞれぞれ「文化的な時間」があったほうが長く楽しく働けるのではないかと思います。そして、それは結果的に企業にとっても、人材の確保やパフォーマンスの向上というメリットがもたらされるのではないでしょうか。
仕事をしながら自分の夢を追求できる社会に
世界的に見ると、日本のビジネスパーソンは本を読んで勉強する時間が少ないといわれています。読書には娯楽という側面もありますが、たとえ仕事とは直接関係がなくても、その周辺知識や一歩先を行く知識を得られる場合もあります。
仕事と文化は全く切り離された別物ではありません。文化的な活動の中で、普段は見えない顧客の顔が見える瞬間があったりします。仕事に関わる情報にしか接していないと、最終的に自分のアイデアを深掘りしたり、仕事の幅を広げたりする土壌が育まれません。
そういう意味でも、読書をはじめ文化的な活動が仕事と両立するような社会を、私たちは目指すべきだと思います。
そのためには、勤務日数や労働時間、兼業など、働き方の多様化をさらに促進したり、子どもが生まれても給与が下がらないような給与体系にするなど、社会の仕組みや制度をいっそう整えていく必要があるでしょう。
同時に働き手のほうも、単に仕事の負荷が減ればいいと考えるのではなくて、時間当たりの生産性を高めるような働き方をすることは必要です。
働きながら本が読める社会。それは、仕事をしながら自分の夢を追求し実現していけるような社会だと思います。誰もが仕事で燃え尽きることなく、自分の人生にとって大切なことを大切にできる、そんな社会が訪れることを心から願っています。
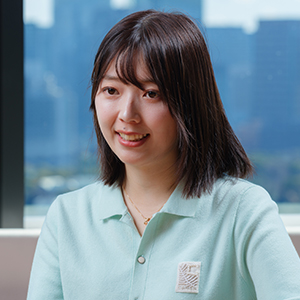
お話を聞いた方
三宅 香帆 氏(みやけ かほ)
文芸評論家
京都市立芸術大学非常勤講師
1994年高知県出まれ。京都大学文学部卒。京都大学人間・環境学研究科博士後期課程中途退学。株式会社リクルート入社。2022年に独立。
文芸評論や社会批評などの分野で幅広く活動。“働きながら本が読める社会をつくる”をミッションに、読書や物語の魅力、働き方や生き方などについて発信、講演を続けている。
著書『文芸オタクの私が教える バズる文章教室』(サンクチュアリ出版)『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社)『「好き」を言語化する技術』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)ほか多数。
[編集] 一般社団法人100年企業戦略研究所
[企画・制作協力]東洋経済新報社ブランドスタジオ












