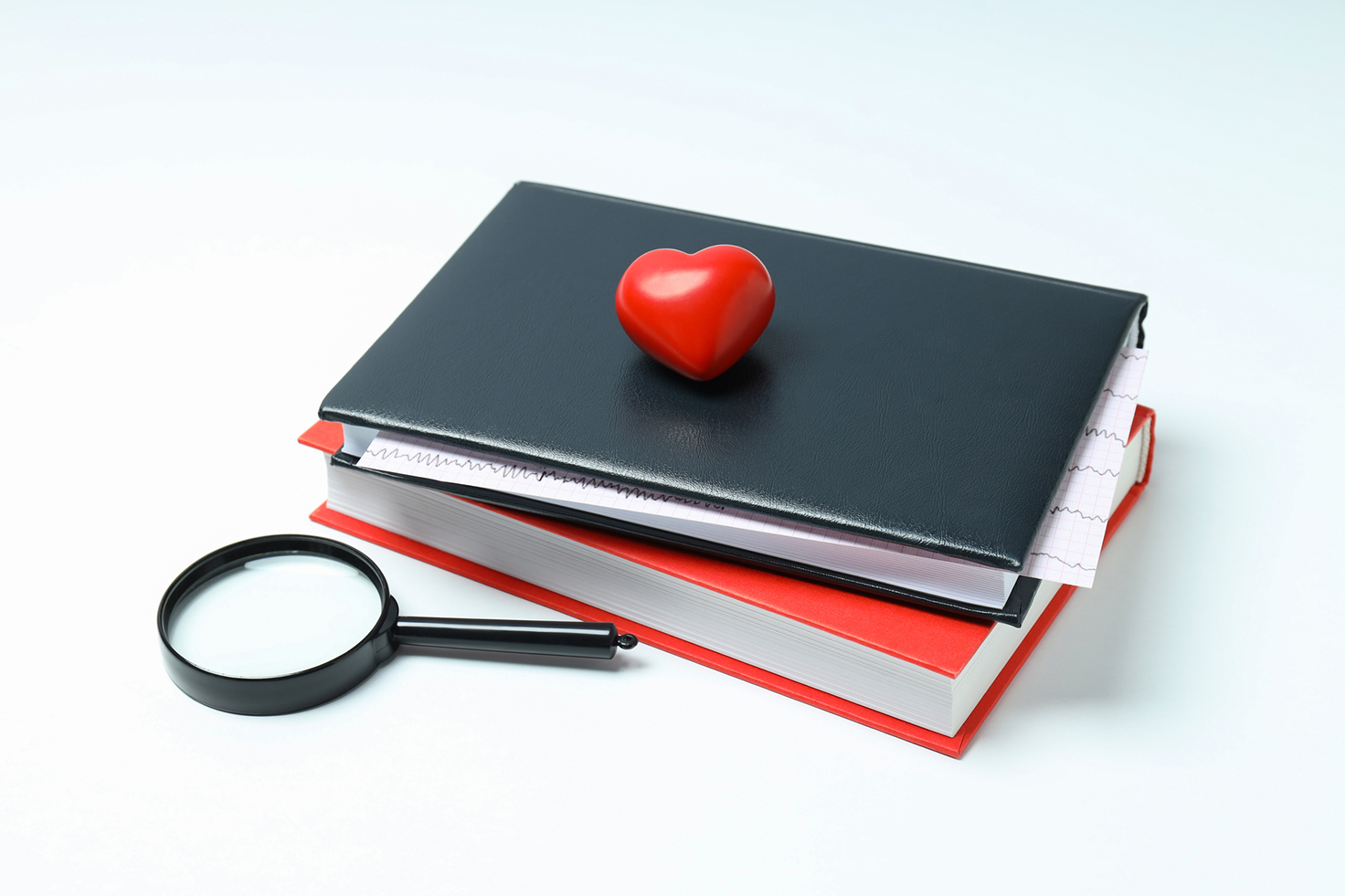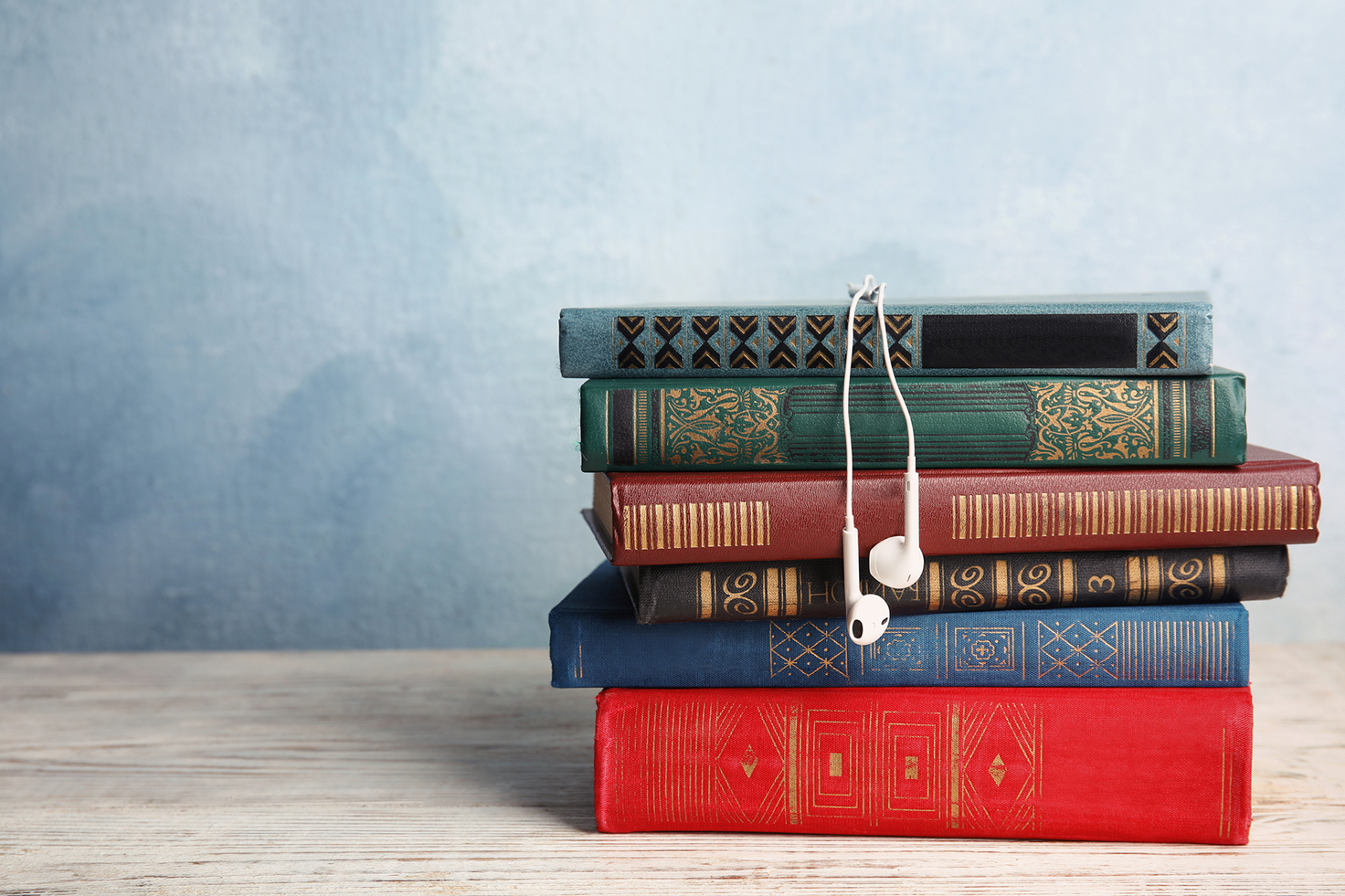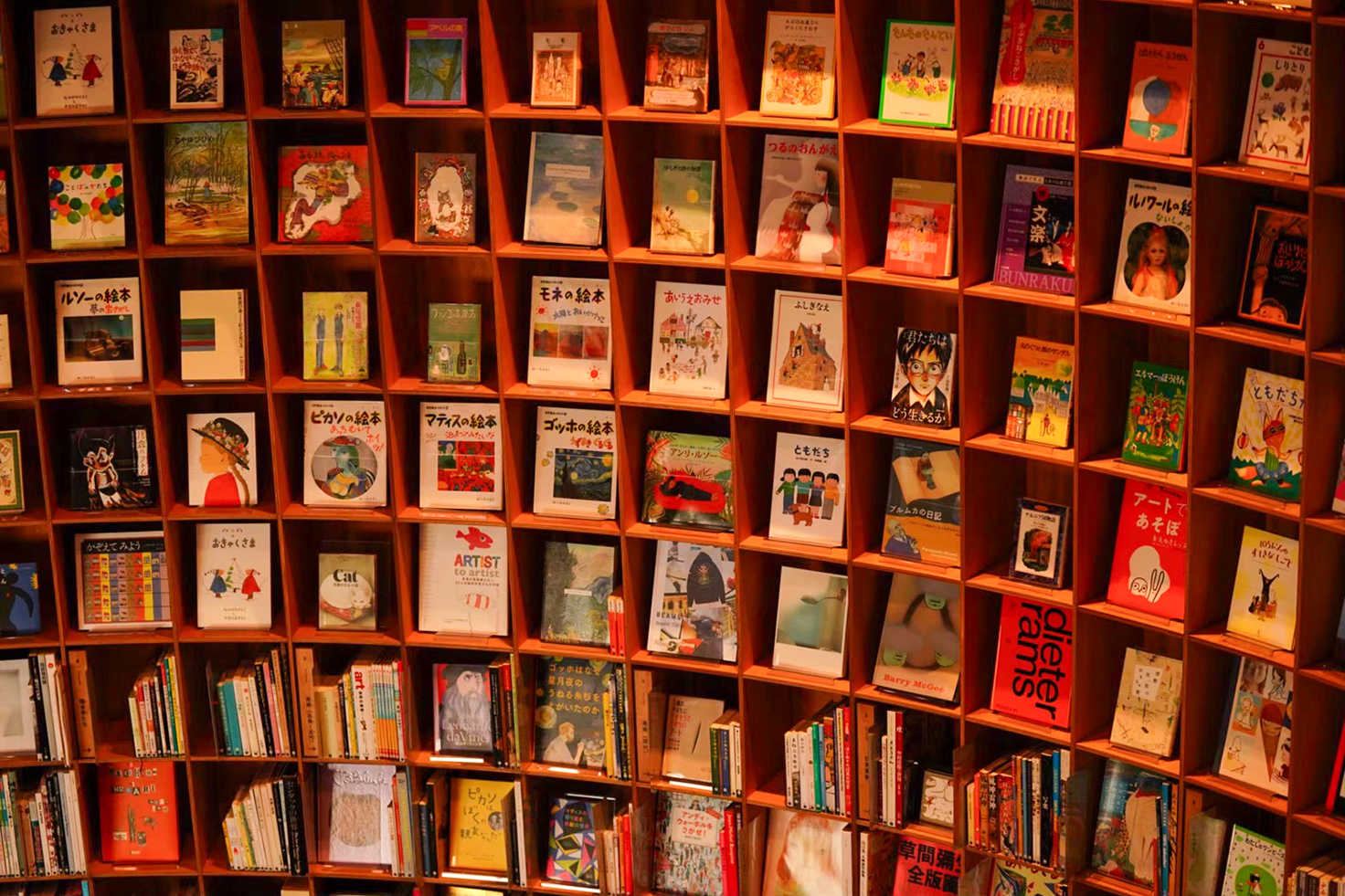経営者にいまおすすめの本6冊 「人口問題」編
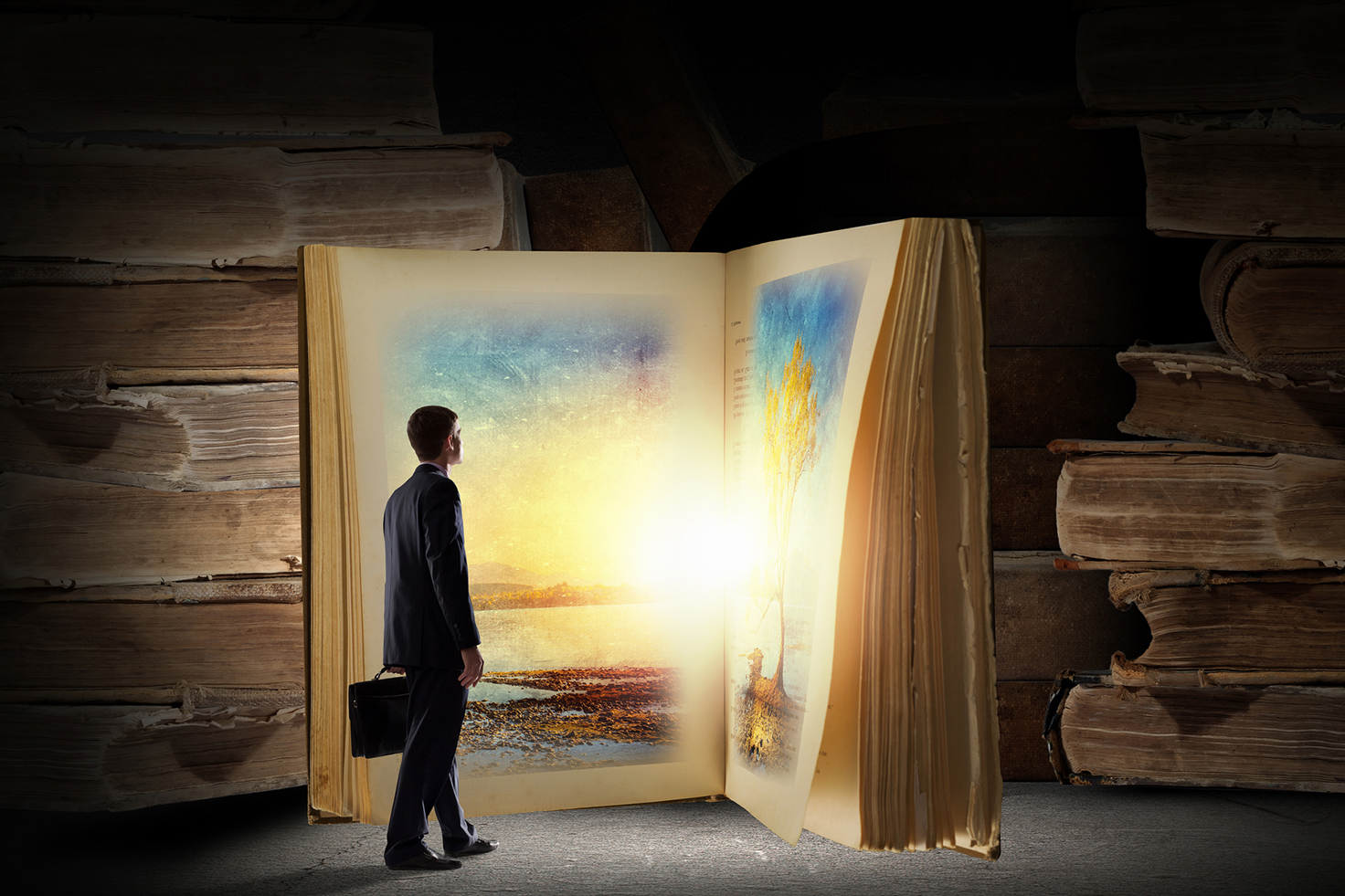
目次
日本における人口減少や高齢化は、国内の産業構造を大きく変容させつつあり、さまざまな対応が急務とされています。私たちは今、どのように思考し、何をすべきなのでしょう? また、人口問題は日本だけでなく、世界中に多大な影響を与えています。人口問題の過去と現在を俯瞰し、未来に起こりうる事象を予測するために、最適な6冊をご紹介します。
世界10の国・地域の人口動態を、キーとなる数字を基に分析
『人口は未来を語る 「10の数字」で知る経済、少子化、環境問題』
ポール・モーランド著、 橘明美 訳 NHK出版 2,860円
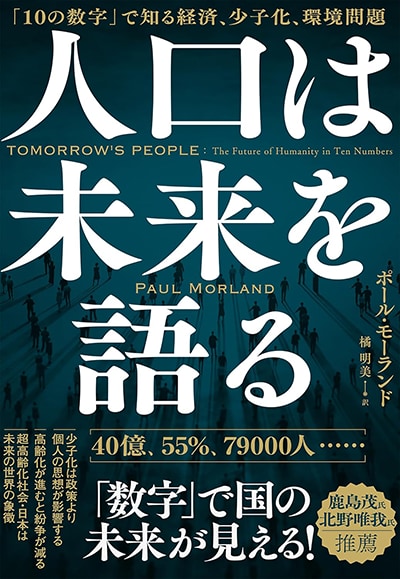
著者のポール・モーランド氏は本書の冒頭で、「今日のわたしたちを作り上げてきたのは、歴史上の人口動態の大きなうねりである」と述べています。この見解をもとにモーランド氏は、世界10の国・地域の人口動態を特徴づける「数字」をピックアップして、その数字が示す意味を分析・解説しています。
第1章 「10」 ペルーの出生1000人あたりの乳児死亡数
第2章 「40億」 2100年のサハラ以南アフリカの人口(予測)
第3章 「121」 中国の人口100万人以上の都市数
第4章 「1」 シンガポールの合計特殊出生率
第5章 「43」 スペイン・カタルーニャ州の年齢中央値
第6章 「79000」 日本の100歳以上の高齢者数
第7章 「55」 100年でのブルガリアの人口減少率(予測)
第8章 「22」 カリフォルニア州の児童に占める白人率
第9章 「71」 バングラデシュの女性100人あたりの識字者数
第10章 「375」 エチオピアの穀物生産の過去25年間での増加率
日本人にとってとくに注目されるのは、第4章のシンガポールにおける出生率の低さといえるでしょう。「1」とは、1人の女性が生涯に産む子供の総数を意味します。これまで東南アジアの出生率は高い傾向にありましたが、先進国化が進めば出生率が下がることをこの数字は示唆しています。
第6章の「79000」は、日本における100歳以上の高齢者数です。これは一社会の人口比としては史上最高のレベルに達していると指摘。日本と同様に、イタリア、ドイツ、中国、アメリカなども高齢者比率が高くなる傾向にあり、それが地域経済や年金制度などに与える影響にも言及しています。こうした分析によってモーランド氏は、各国・地域が今後さらに発展するのか、または情勢が悪化するかを予想しています。
人口学者であるポール・モーランド氏は、オックスフォード大学で哲学、政治、経済の学士号、国際関係論の修士号を取得し、その後、ロンドン大学で博士号を取得して、現在は同大学バークベック校のフェローを務める人物です。本書を読み進めていくと各国・地域が置かれている状況に必然性が感じられ、さらにその背後には人口動態に起因する一定のパターンが見えてきます。
「労働供給制約」を解消する4つの策とは?
『「働き手不足1100万人」の衝撃』
古屋星斗、リクルートワークス研究所著 プレジデント社 1,760円
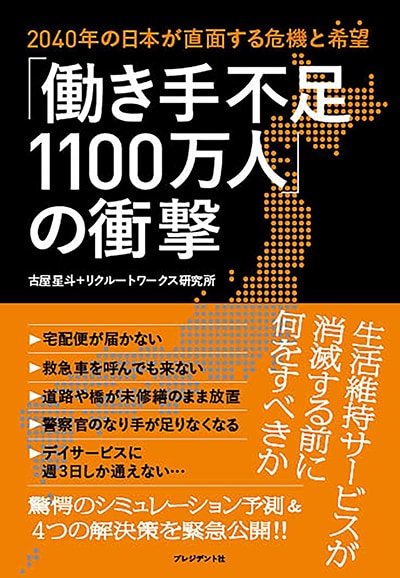
2023年3月、リクルートワークス研究所が発表した『未来予測2040 ― 労働供給制約社会がやってくる』というレポートが大きな話題となりました。この報告書には、われわれが現状のまま「座して待つと何が起こるか」を労働力の需給の観点からシミュレーションし、「2040年に日本では、1100万人の働き手が足りなくなる」ことが記されています。本書は、その報告書を著した同研究所の主席研究員、古屋星斗氏が、豊富な資料を基に、より具体的にその事象を解説したものです。
人口減少が止まらない日本では、すでに何年も前から「労働力が足りない」「足りなくなる」と指摘され続けています。ただし、これまでに語られてきた人手不足は、後継者や技術継承者の不在、デジタル人材の不足など、産業や企業からの視点で語られるものが多数を占めていました。
一方で、これから起ころうとしている人手不足は、「生活維持サービス」の水準低下をもたらすものだと古屋氏は指摘します。例えば2040年には介護サービス職で25.2%、ドライバー職で24.1%、建設業で22.0%の人手が足りなくなると予測。こうした人手不足は、私たちが当たり前に享受してきたサービスが消滅する可能性さえあると警鐘を鳴らします。
本書の前半部では、日本人が直面することになるこの「労働供給制約」について解説され、続く後半部では、この状況を解消する「4つの打ち手」が提案されています。
「4つの打ち手」の1つ目としては、「徹底的な機械化・自動化」(第6章)が提示されています。2つ目では、各人の社会活動を通して人手不足を補う「ワーキッシュアウトという選択肢」(第7章)が挙げられ、例えば散歩をする人や通勤者が、同時に防犯パトロールを担うなどの活動が提案されています。
3つ目の「シニアの小さな活動」(第8章)は、シニアによる活動が現役世代の働き手を助けているという現状を踏まえたもので、本書ではその活動例が列記されています。そして4つ目の「企業のムダ改革とサポート」(第9章)では、社内作業における需要を減らし、供給を増やすことが推奨されています。
売上高ではなく利益高を拡大し、「戦略的に縮む」
『未来の年表 業界大変化 瀬戸際の日本で起きること』
河合雅司著 講談社 1,012円
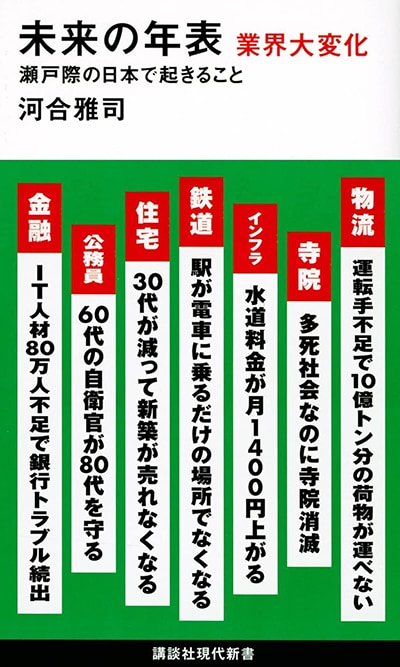
ジャーナリストの河合雅司氏による本書は、『未来の年表』(2017年発行)、『未来の年表2』(2018年)に続くシリーズ第3作目であり、同シリーズの累計発行部数は100万部を突破しています。
人口減少対策総合研究所の理事長を務める河合雅司氏は、膨大なデータを集積・分析することで、日本の人口減少が将来的に引き起こす事象を予測するとともに、企業がその局面をどのように打開すべきかを提言しています。
人口の減少は人手不足を引き起こすだけではありません。消費活動が低下する高齢者の割合が増加することにより、実人数が減る以上にマーケットが縮小し、消費が落ち込む「ダブル縮小」に見舞われるだろうと河合氏は分析。こうした現実から目を背け、このまま売上高の拡大を目指せば、必ずどこかで行き詰まるだろうと指摘しています。
人口減少に抗うには、これまでの経営手法から大きく発想を転換し、「戦略的に縮む」という成長モデルを取り入れる必要がある。それは売上高の拡大ではなく、利益高の拡大を意味し、そのためには各企業が成長分野を定め、そこに集中的に投資や人材投入を行うべきだと、河合氏は主張しています。
本書は2部構成となっており、第1部「人口減少日本のリアル」では、各業種やビジネスを支える公共サービスの現場で発生しつつある課題を、人口減少の観点から捉えます。このまま対策を講じなかった場合、各業界に何が起こるのか。そうした未来の可視化作業によって、ビジネス版の「未来年表」が提示されています。
第2部「戦略的に縮むための『未来のトリセツ』」では、その成長モデルの手順を10ステップに分け、人口減少下での企業の勝ち残り策が提言されています。各ステップのキーワードは、(1)量的拡大モデルとの決別、(2)選択と集中、(3)付加価値の強化、(4)ブランド力の強化、(5)1人当たりの労働生産性の向上、(6)スキルアップ、(7)年功序列の廃止、(8)若者の集中と交流、(9)多極集中、(10)輸出相手国の将来人口分析、です。これら各キーワードを詳細かつ具体的に解説しつつ、未来の人口減少への対応策が検証されています。
『なぜ少子化は止められないのか』
藤波匠著 日本経済新聞出版 990円
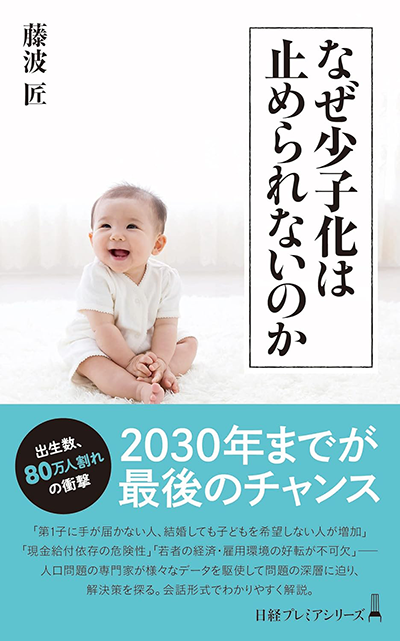
著者の藤波匠氏は、日本総合研究所の上席主任研究員。主として地方再生や人口問題の研究に従事してきた藤波氏が、なぜ少子化は止まらないのか、どのような手を打てばよいのかなど、人口減少に起因する諸問題を各専門家との対話形式によってわかりやすく解説。若者の意識変化、経済環境、現金給付の効果などを、さまざまなデータを基に分析する。
『人口と世界』
日本経済新聞社編 日本経済新聞出版 1,980円
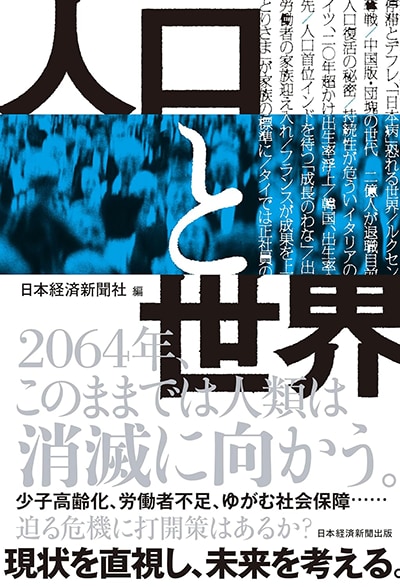
世界における人口問題を日本経済新聞社が総括した一冊。各国で急速に進行する高齢化、欧州の移民政策、ドイツの「両親手当」、成長するインドが抱える問題点、縮む中国、人口より生産性を優先するシンガポールなど、内容は多岐に渡る。これらの国々に生じている歪みや、それに対する政策を確認しながら、日本の進むべき未来を再検証する。
『人口減少社会のデザイン』
広井良典著 東洋経済新報社 1,980円
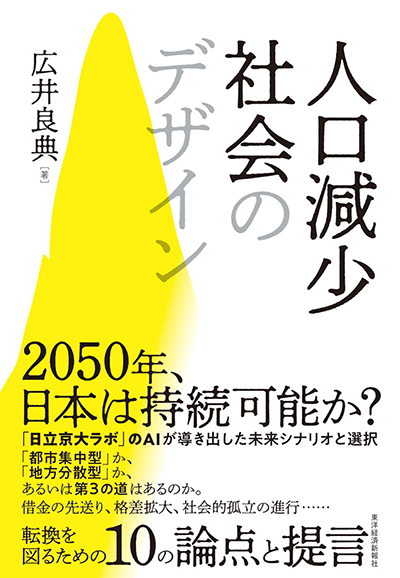
京都大学「こころの未来研究センター」の教授を務める広井良典氏が、「都市集中型」と「地方分散型」の得失を分析。東京一極集中は、地方衰退と格差拡大をもたらすが、国の財政は改善させる。地方への人口分散は、格差を縮小するが、国の財政は悪化させる。では、それ以外の第3の道ははたしてあるだろうか。日立京大ラボのAIが導き出した未来シナリオを検証しつつ、持続可能な社会モデルを探る。
[編集] 一般社団法人100年企業戦略研究所
[企画・制作協力]東洋経済新報社ブランドスタジオ