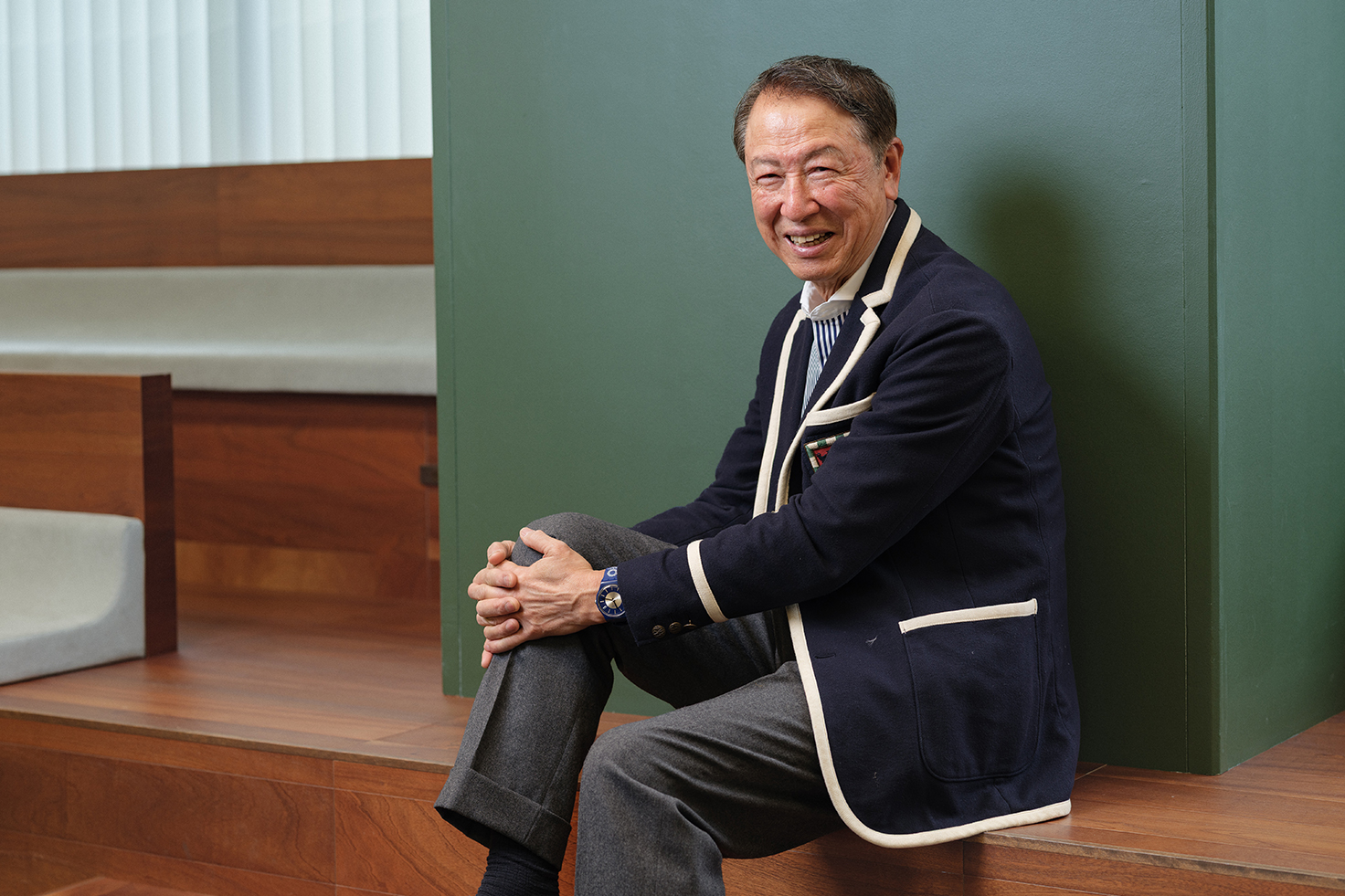クリエイティブ・ペアの盟友が見た素顔の野中郁次郎
~竹内弘高氏インタビュー【前編】
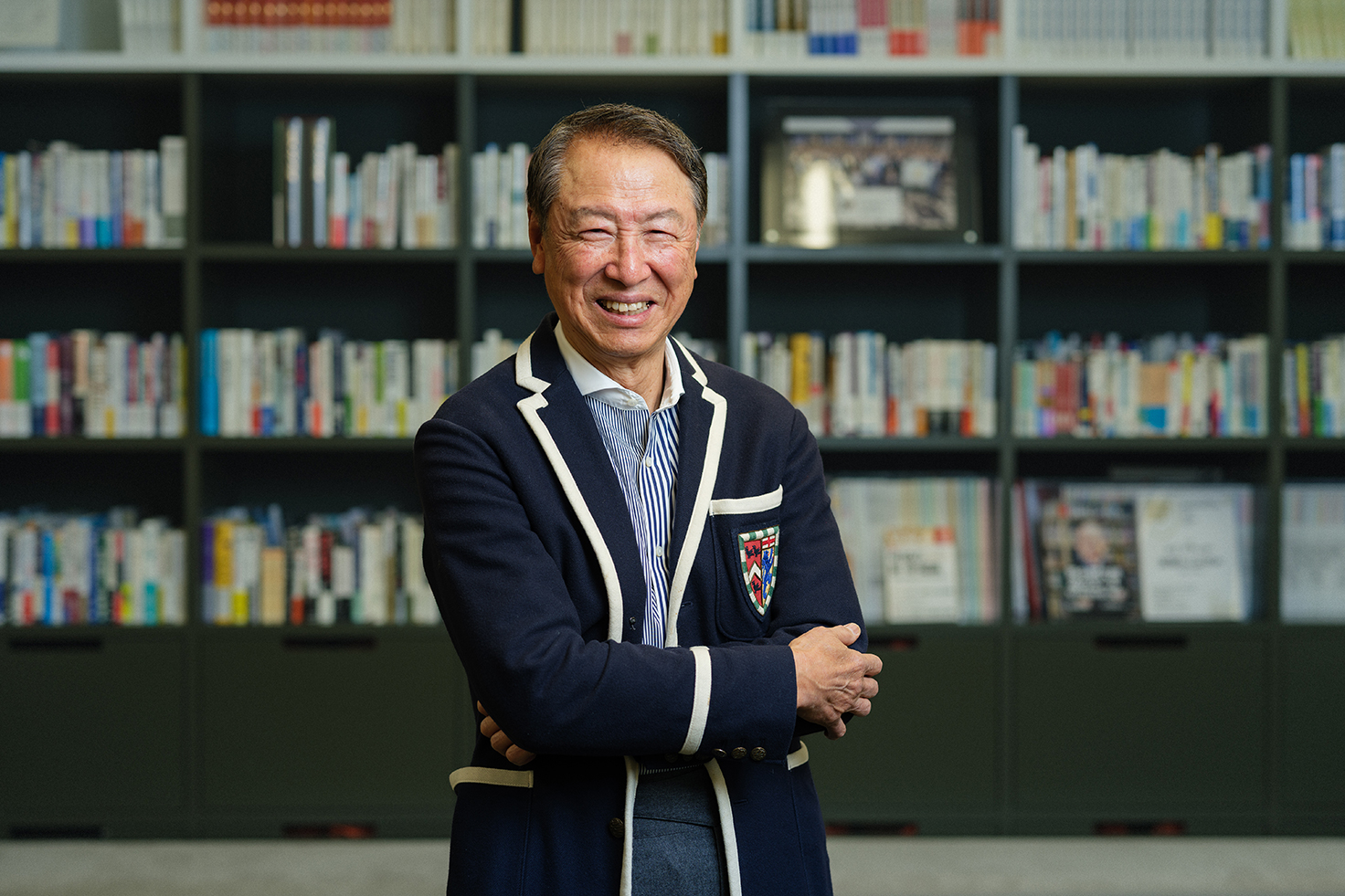
目次
2025年2月に逝去した野中郁次郎氏(一橋大学名誉教授)は、『知識創造企業』『失敗の本質』などの著作(共著)で日本の組織論や経営学に大きな一石を投じました。日本企業の知識創造のスパイラル構造を示した「SECI(セキ)モデル」は国際的に高い評価を得ています。さらに、経営学に留まらず幅広い学究を実践した「知の巨人」です。
『知識創造理論』『ワイズカンパニー』など、いくつかの著作で共著者として名を連ねる竹内弘高氏(国際基督教大学理事長)は、野中氏とは米カリフォルニア大学バークレー校で出会い、一橋大学でともに研究し、親交を結んだ盟友。その竹内氏の目から見た野中氏の実像と、竹内氏が近年力を入れる「グローバル人材認定プログラム」の概要を、前後編に分けて伺います。
一橋大学への就任を強く勧められる
私が野中(郁次郎)さんと出会ったのは1970年、MBAを取得するために入学した米カリフォルニア大学バークレー校でした。そこに博士課程4年目だった野中さんがいたんです。野中さんは米国に奥様の幸子さんを伴ってらして、よくご自宅にも呼ばれました。幸子さんがカレーや餃子を拵えてくださってね。ある意味、それを目当てに野中宅に通っていたようなもので、幸子さんがいなかったら、野中さんとは仲良くならなかったかもしれません(笑)。
私は学者になるつもりはなく、MBAを取得したら米国でコンサルティング会社に就職するつもりでしたが、それが叶わず、ハーバード・ビジネス・スクール(HBS)に7年勤めました。この間に子どもも生まれ、それを契機の1つとして帰国しました。1983年のことです。やはり「子供は私のように日本で育てたい」と思ったからです。
帰国した私は一橋大学商学部の助教授になりました。実はこれは野中さんの影響なんです。遡ること1年前の1982年、日本の事情に関して教えを乞おうと、当時防衛大学で教鞭を取っていた野中さんに相談に行きました。そのとき私には、勤務先として3つ選択肢がありました。当の一橋大学のほか、他の国立大学とコンサルティングファーム。「野中さん、どこがいいでしょう?」。すると野中さんいわく、「一に一橋、二に一橋、三、四がなくて、五に一橋」だと。
それで私は、野中さんがそこまで言うならと一橋大学に決めたのですが、実は当時、野中さんも防衛大学から一橋への移籍が内定していたのです。日本の組織の人事は内定段階だと他言無用ですから、それが言いたくとも言えなかったわけです。野中さんは私より1年早く一橋大学に移り、そして私が続くという格好になりました。
日本企業の特徴を看破した「新たなる新製品開発の方法」
野中さんとの共同研究の端緒を開いたのは私の古巣のHBSでした。ウィリアム・アバナシー教授から、日本企業の新製品開発に関する研究要請があって、入ったばかりの私、野中さん、一橋大学産業経営研究所(産研)所長の今井賢一さんの3人で担当しました。ケースとして取り上げたのは、富士ゼロックス、日本電気、エプソン、ブラザー、キヤノン、ホンダの6社。その研究成果は最初にHBSのシンポジウムで発表し、追って論文にもまとめたところ、非常に高い評価を得ました。
評判を聞きつけて私たちにアプローチしてきたのがマネジメント誌の最高峰、『ハーバード・ビジネス・レビュー』です。それで形になったのが「新たなる新製品開発の方法」と題する論文で、著者は私と野中さん。二人で書いた論文はいくつもありますが、これは唯一、私の名前が初めに来ています。
掲載は、同誌の1986年1月/2月号でした。副題が「リレーを止めてラグビーを取り上げよ」。日本企業の社員の特徴は、全員がフィールドを上下しており、何か問題が生じるとスクラムを組んで一丸となって解決に当たること。それがラグビーのようだということでメタファ(暗喩)に使い、ラガーマンのように俊敏かつ短い期間で実現する日本企業の新製品開発を説明したのです。
野中さんはこのプロセスを通じ、「竹内と組むと英語で論文が発表できる」と考えたのではないかと思います。
私と野中さんとの共著に『知識創造企業』があります。非常に高い評価をいただき、今も世界中で読まれている1冊ですが、これは私が英訳を担当しました。たまたま1994年、野中さんが他の著者に依頼した英文の草稿を見せてくれたんです。それを読んだ私が「英語はよくないし、構成も駄目、ケースの配置も悪い。そもそも面白くない。こんな本を出しちゃいけない」と“酷評”したところ、野中さんから「そこまで言うなら、ヒロ、お前が書いてくれ」と。それで形になったのです。
アメリカでの真剣勝負、木刀を手渡された
野中さんとのエピソードでいうと、真っ先に思い出すのが、1986年に起きた一橋の学長選挙です。産研所長の今井さんは当時、早稲田大学出身の野中さん、国際基督教大学出身の私、慶應義塾大学出身の金子郁容さんなどを招聘し、輸入人事の断行によって商学部の改革を目指しており、さらに自ら学長にも立候補しました。
一橋はリベラルな校風の大学で、当時、学長候補に対し学生が拒否権を行使できる仕組みがあったのです。ふたを開けてみたら、その今井さんへの不信任票が過半数を超え、制度が始まって以来、初の失格者となってしまいました。
この前代未聞の「事件」の背景にあったのが小平キャンパスにおける留学生寮の建設という問題でした。「今井が学長になったら、グラウンドを潰し、そこに留学生寮を造るらしい」というフェイク・ニュースが流れ、多くの学生が付和雷同的にそれを信じてしまったのです。それに怒ったのが、商学部の4人の教員たちです。さっそく抗議のビラをつくって、キャンパス内の生協の前で学生たちに手渡したんです。これもまた前代未聞の出来事でした。
「4人の教員」とは、ほかならぬ野中さん、そして私。さらに米倉誠一郎さん(現一橋大学名誉教授)、榊原清則さん(慶應義塾大学名誉教授。逝去)でした。米倉さんは一橋大学社会学部出身、榊原さんは電気通信大学出身。皆、商学部生え抜きではない「外様」の人たちでした。突き上げを食らっても何も怖くない。あやふやな流言飛語を信じて軽挙に出た学生たちには、きちんと再教育を施さなければ、という純粋な気持ちから出た行動でした。野中さんが最年長で、4人の中のリーダー的存在です。次の日からわれわれは中国の文化大革命よろしく「4人組」と呼ばれ、学生が書く立て看板で名指しで糾弾されました。この事件をきっかけに、私と野中さんはもちろん、4人の絆が深くなりました。
その頃から「戦う」という気持ちを野中さんと私は共有していました。2010年、HBS教授となり、2度目の着任をする際、「ヒロ、これを持って行け」と手渡してくれたのは、ずっしりと重い木刀でした。アメリカで真剣勝負してこい、負けるなよ、という意味だったのだと思います。
野中さんは学者の見本のような方で、自宅のあった八王子から都心まで電車に乗っている時間が1時間あったのですが、その時間を読書にあてていました。一方で、富士電機に9年勤めた企業経験もあり、学者になった後は企業研修、なかんずく幹部候補生の育成に熱心でした。欧米の野中信奉者はこの後者の姿を案外見落としていると感じています。
一橋大学の新しいビジネススクール、国際企業戦略研究科の初代研究科長を私が勤めていたとき、野中さんを目玉教授に迎えたわけですが、その野中さんが「現役学生を教えたくない。彼らが偉くなった頃、自分はもうこの世にいないからだ」とおっしゃる。ならば何をしたいのかを聞いたら、エグゼクティブ向けのプログラムをやりたいと。それでできたのが次世代の経営リーダー育成を目的にしたナレッジ・フォーラムで、2008年のことでした。今でも続いており、今年で18期にあたります。1期生30人の中から7名の社長が出て、野中さんは大喜びでした。
変化の重要性と異質なものの大切さ
野中さんが世界に示した、知の遺産は2つあります。1つは変化し続けることの重要性です。彼がバークレーに留学した時、最初の専攻はマーケティングでした。それから組織論、情報論、知識論、リーダーシップ、哲学、最後は戦略論と、約5年ごとに興味関心が進化していくんです。真骨頂だった哲学の分野でも、マイケル・ポランニー、アリストテレス、フッサールと5年ごとに違う碩学に興味を持ち、研究の土台にしていきました。自分が言いたいことを一番よく表現してくれる哲学者は誰か。それを求めて、毛沢東まで哲学者と見なし、その思想を自分のものにしてしまう。彼には類稀なアジリティ(俊敏性)が備わっていたのです。
もう1つは、自分にとって異質なものの大切さです。野中さんは、バークレー校では分析(アナリシス)の手法を指導教授から徹底的に教え込まれます。次に、その対極のアート(芸術・学術)に行くかと思いきや、アートとサイエンス(科学)の融合に達し、最後は「二項動態」*にたどり着いた。彼の研究の本質は常にboth and(両方)なんです。暗黙知と形式知もそうで、それを相互変換させ、いかに増幅させるかを説いたのが、SECIモデルだったわけです。野中さんは異質なものの組み合わせを大切にしていたからこそ、二項動態に至ったともいえます。
異質なものの重要性は、人間同士の組み合わせにも当てはまります。ホンダにおける本田宗一郎と藤澤武夫、ソニーにおける井深大と盛田昭夫というように、異質な二人、つまり、クリエイティブ・ペアの重要性をよく認識していました。私と野中さんも互いにまったく異質な人間でした。最も大きな違いは野中さんが少年の頃、米軍のグラマン機に銃撃されたという鮮烈な戦争体験を持つ戦前生まれであるのに対し、私が戦争体験を持たない戦後生まれである点です。野中さんの根底には、どうしたらアメリカを超えられるか、というリベンジ(復讐)の気持ちがあったと思います。
(後編へ続く)
*「あれかこれか」という二項対立ではなく、「あれもこれも」と二項を両立させ生かすという概念
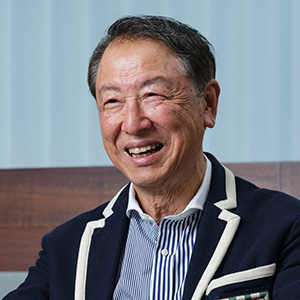
お話を聞いた方
竹内 弘高 氏(たけうち ひろたか)
国際基督教大学 理事長
一橋大学 名誉教授
国際基督教大学卒業後、広告代理店に勤務を経て、米国カリフォルニア大学バークレー校経営大学院で経営学修士(MBA)、博士号(Ph.D)を取得。1976年から1983年まで、ハーバード・ビジネス・スクール助教授。1983年に一橋大学商学部助教授、1987年に教授。2000年に開校した一橋大学大学院国際企業戦略研究科の初代研究科長に就任。2010年より同大学名誉教授(現在)。また2010年から2023年までハーバード・ビジネス・スクール教授。2019年より国際基督教大学理事長(現在)。
主な共著に「The Knowledge-Creating Company」(『知識創造企業』野中郁次郎、竹内弘高共著、東洋経済新報社)「Can Japan Compete?」(『日本の競争戦略』マイケル・E・ポーター、竹内弘高、榊原清則共著、ダイヤモンド社)「The Wise Company」(『ワイズカンパニー』野中郁次郎、竹内弘高共著、東洋経済新報社)がある。
[編集]一般社団法人100年企業戦略研究所
[企画・制作協力]東洋経済新報社ブランドスタジオ