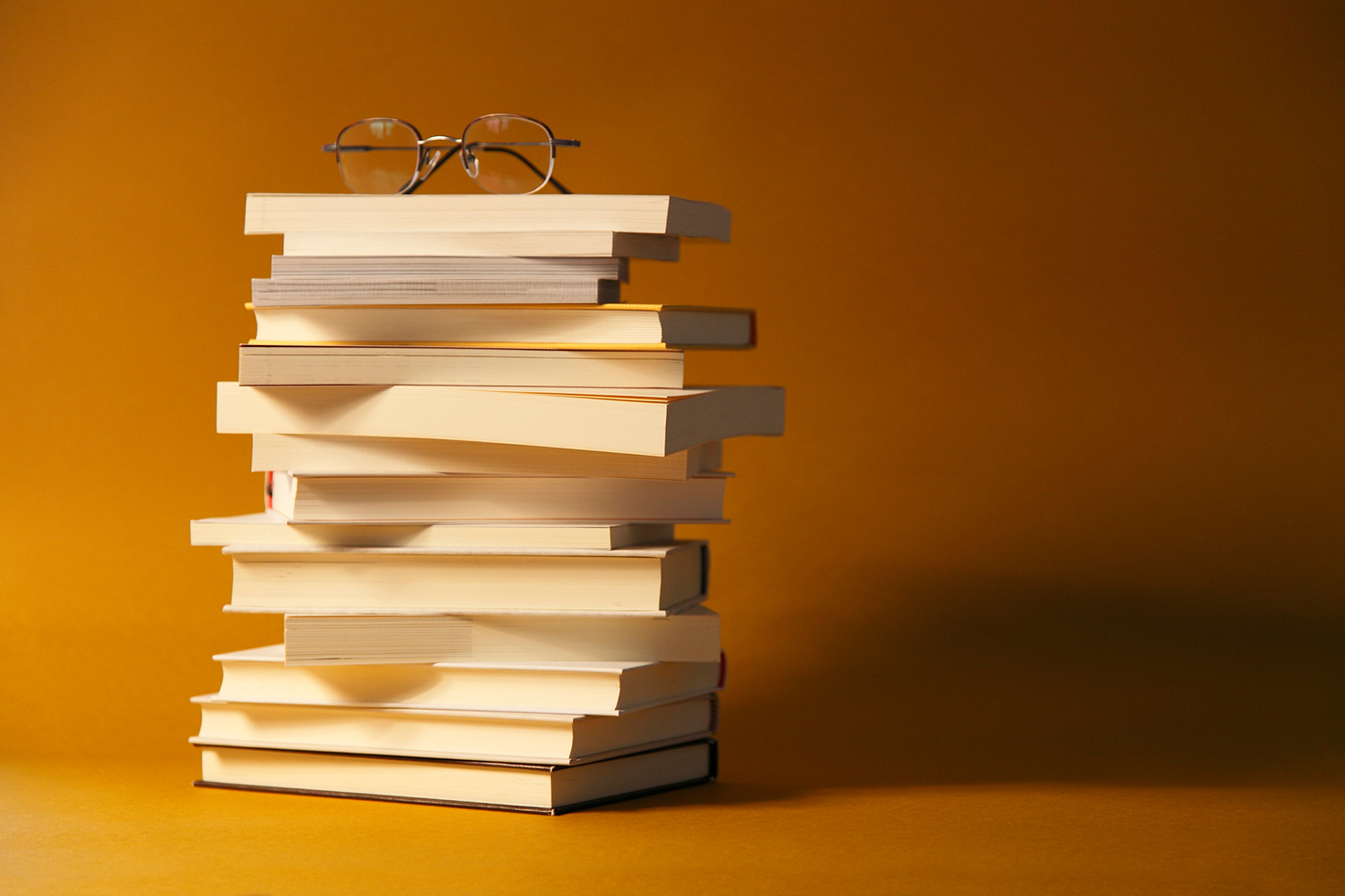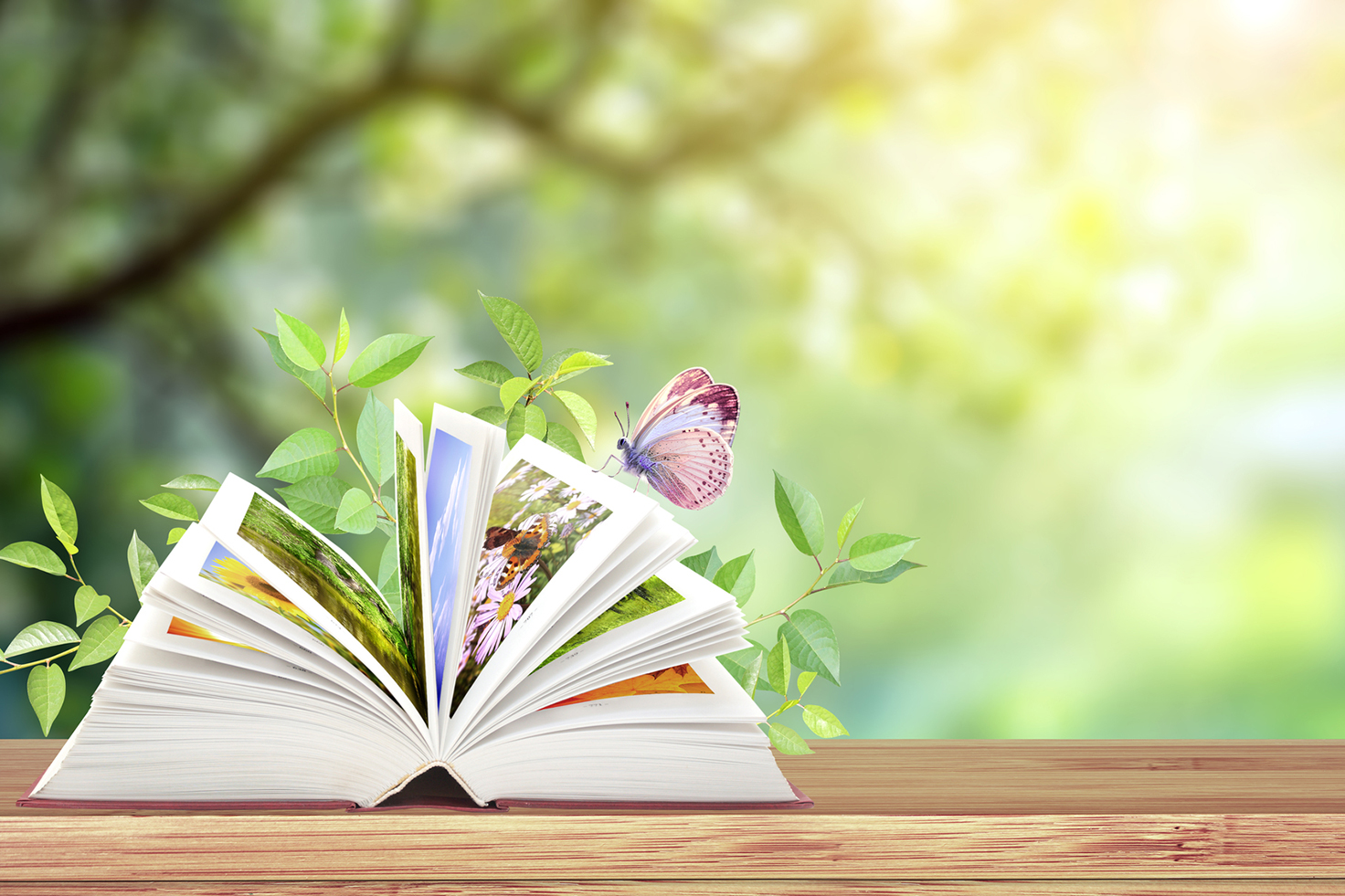経営者にいまおすすめの本6冊 「ブランディング」編
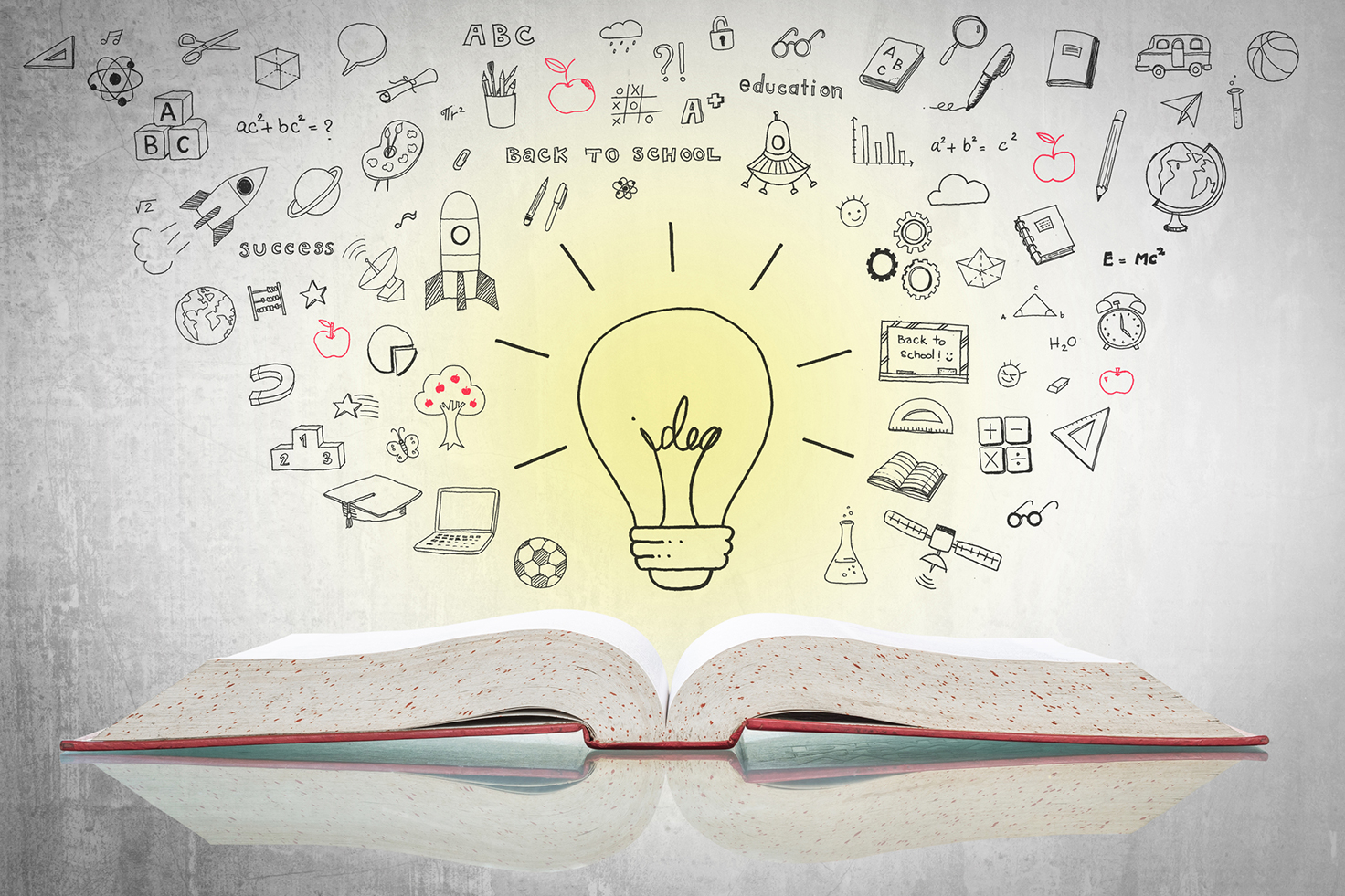
目次
「ブランディング」という言葉には日常的に接しているものの、具体的にはそれがどんな戦略を意味するのか、どのように取り組めばよいのかがわからない、そんなビジネスマンは意外に多いかもしれません。ここに紹介するのは、そんな問いに明快な答えをもたらす6冊。これらの書籍をひもとけば、ブランディングの真の意味合いが理解できるはずです。
『手にとるようにわかる ブランディング入門』
金子大貴、一色俊慶著 かんき出版 1,760円
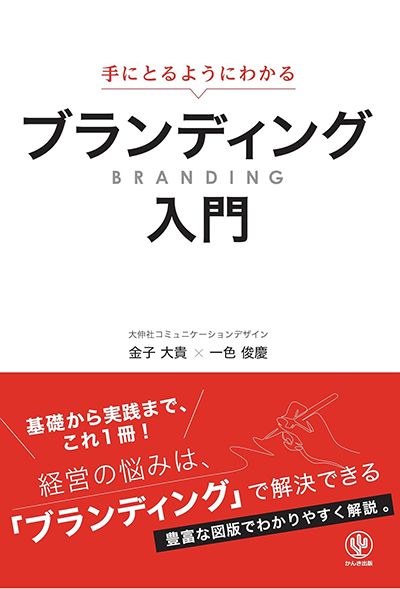
ブランディングは企業の複数の経営課題の解決につながる
ブランドとは何か? ブランディングとは何をすることなのか? こうした問いにズバリ答えるために書かれたのが本書です。
ブランディングとはアパレル業界や大企業、B to Cのビジネスに限った話題ではなく、どんな企業にも必要なもの。企業の存在意義を明確にするという意味においてはパーパス経営にも大きく関連し、その意義がブランディングを実行する際に重要なカギになると、著者は説明します。また、ブランドを確立できれば他社との差別化、人材採用など、一見別の問題にも思える経営課題を解くヒントにもなります。
イメージがつかみづらいブランディングですが、当書ではその意義が明瞭かつ簡潔に解説されています。前半では、ブランドの必要性(PART 1)、ブランドの正体(PART 2)、もたらすメリット(PART 3)、ブランディングの内容(PART 4)、基本プロセス(PART 5)などの話題を網羅。どのパートも平易な文章と豊富な図表で構成され、初めてブランディングに取り組む方々にも最適な、わかりやすい入門書です。
本書を執筆したのはブランディング戦略を手がける大伸社コミュニケーションデザインに所属する2人のディレクター。金子大貴氏は、大手上場企業から中小企業までのリプランニング、新製品のコンセプト開発、ブランド浸透戦略などを担当するブランディングディレクター、一色俊慶氏は、住宅関連企業や医療機器メーカーなど、B to B企業のブランディングやマーケティングを得意とするクリエティブディレクターです。
本書の後半は、両著者のノウハウを凝縮した手引書として構成。ブランディングの目的(PART 6)、自社と競合、顧客の現状理解(PART 7・8)、ブランドコア(中核)の定義(PART 9)、インナー(社内向け)ブランディング(PART 10)とアウター(社外向け)ブランディング(PART 11)、検証と改善策(PART 12)という具合に、ブランディングを実践するための具体的なフェーズをパートごとに解説していきます。
『ブランド論——無形の差別化をつくる20の基本原則』
デービッド・アーカー著、阿久津聡訳 ダイヤモンド社 2,640円
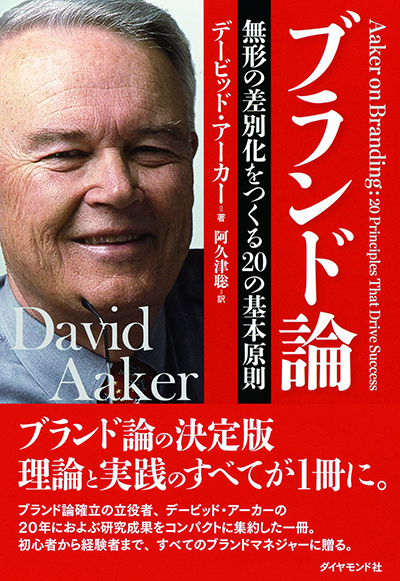
日本にも造詣が深い、ブランディングの第一人者
日本のマーケティング界においてブランディングの重要性が広く認識されたきっかけは、1994年に『ブランド・エクイティ戦略』(ダイヤモンド社)が広まったことだとされています。その著者であるデービッド・アーカー氏はブランド論の第一人者として知られ、これまでに『ブランド優位の戦略』『ブランド・ポートフォリオ戦略』(いずれもダイヤモンド社)などのブランディング関連書を発表。それらのエッセンスを抽出し、20年に及ぶ彼の研究成果をまとめ上げたのが本書です。ブランドに関わる理論やコンセプトが包括的に学べると同時に、初心者にもわかりやすく編纂されているのが本書の特徴といえます。
アーカー氏によれば、ブランドとは単なるブランド名やロゴマークよりもはるかに大きいものであり、組織から顧客への約束、さらには顧客との継続的な関係性を意味します。ブランディングはその関係構築における中核を担い、戦略的判断の足場となり、企業の財務面に影響を与える要因にもなると説明されています。
本書では、アーカー氏が提唱する数十に及ぶブランディングの考え方や実践方法を20の基本原理に凝縮し、それらが20章にわたって解説されています。読者はその章を追うことで、アーカー氏が生み出した「ブランド・アイデンティティ」や「ブランド・ポートフォリオ」「ブランド戦略」などの用語を理解することができます。
また、支持されるブランドを生み出し、強化し、利用するための工程表が示されているのも本書の特徴であり、これをたどることで自社が生み出したブランドに、シナジー効果や独自性などがもたらされるはずです。
アーカー氏は1975年に博報堂に招聘されて初来日して以来、電通の顧問や、日経BPコンサルティングによるブランド価値評価データベース「ブランド・ジャパン」の特別顧問などを歴任。日本企業の実情を熟知したうえで編纂されている本書は、日本のビジネスパーソンにとっても自分ごと化しやすい内容になっています。
『ブランディングの誤解 P&Gでの失敗でたどり着いた本質』
西口一希著 日経BP 2,200円
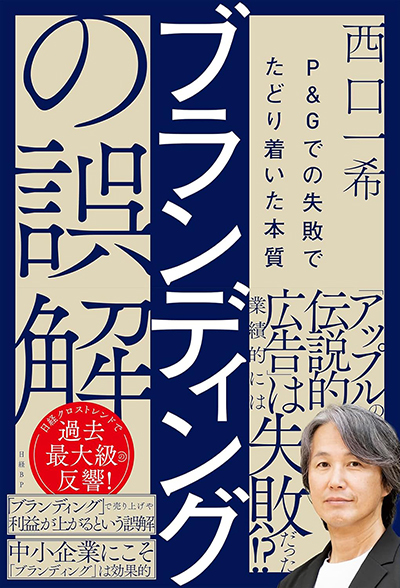
企業のブランディングは「目的」の設定が必須
P&Gジャパンのブランドマネージャーなどを務めた西口一希氏が、その豊富な経験をもとに理知的かつ包括的に分析。興味深い具体事例を数多く挙げながら、ブランディングに対するさまざまな「誤解」を紹介しています。
西口氏は、「ブランディングという言葉は、定義自体が曖昧であり、曖昧であるがゆえに、根拠のない拡大解釈や過剰期待が生まれている」と指摘すると同時に、「ブランディングがビジネスとしての投資である限り、ブランディングの目的を設定することは必須で、その目的が明確でなければ、投資は高い確率で無駄になる」と説明します。
本書は「誤解」を第1章から第3章までで解説した後、続く第4章では、ブランディングの3つの目的を定義。その第1は「想起率※」であり、これはプロダクト(商品やサービスなど)の記憶化と想起性の確立を意味します。この場合のブランドは、商品やサービスなどを競合と区別させ、顧客の想起をうながす”シンボル”として働きます。
第2の「情緒的・心理的価値の提供」とは、商品やサービスに機能的な便益や独自性を超えた付加価値を加えることを意味し、例えば広告にタレントなどを起用するなどの方法によって、それを実現します。
第3の目的の「インナーブランディング」は、顧客というよりも、ビジネス上の関係者や従業員、メディア、株主や投資家、学生らに対する効果を期待するもので、「この企業で働きたい」「応援したい」「投資したい」という気持ちを喚起させるとしています。
著者は巨大ブランドによって無駄な投資や活動が多く生み出されている現状に注意を促す一方、こうした誤解や罠を避けながら、明確なビジネス目的を設定してブランディングを進めれば、中小企業も大きなビジネス効果が期待できると主張します。最後の第8章では、中小企業が目指すべきニッチブランドの意義や、小規模企業も活用できるブランディングの実例が解説されています。
※自社のブランドや商品、サービスなどについて消費者が思い浮かべる割合。
『「個人」「小さな会社」こそ、ブランディングで全部うまくいく』
村本彩 総合法令出版 1,430円
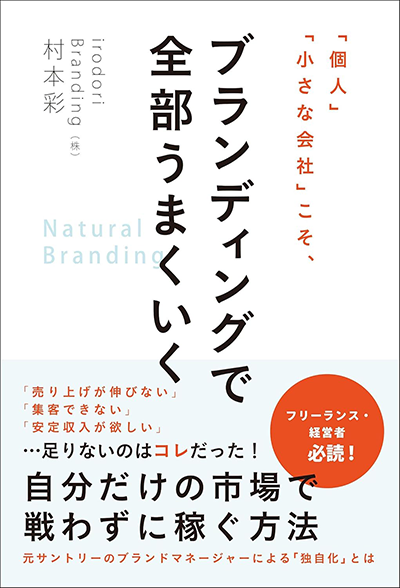
個人経営や小さな会社など、スモールビジネスに携わる方々に向けてつづられたブランディング攻略本。売り手への共感が購買基準になる時代には、「なぜこの商品を提供しているのか」という原点を突き詰め、SNSなどを介してその思いを伝えることがポイントになる。
『ブランディングデザインの教科書』
西澤明洋著 パイインターナショナル 1,760円
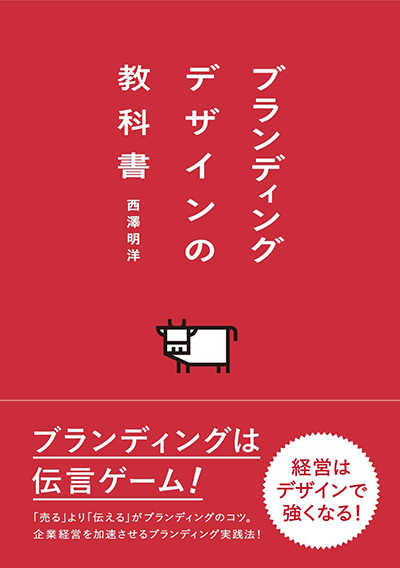
これからブランディングに取り組もうという経営者に向けて、豊富な実績を持つ著者がブランディングとデザインの詳細を徹底解説。“良い"だけでは売れない時代におけるブランディングの思考フレームや、ビジネスや企業経営に役立つデザインの基礎知識を伝授する。
『読むだけブランディング』
佐藤幸憲、平岡広章著、八木真理子イラスト 白夜書房 1,760円
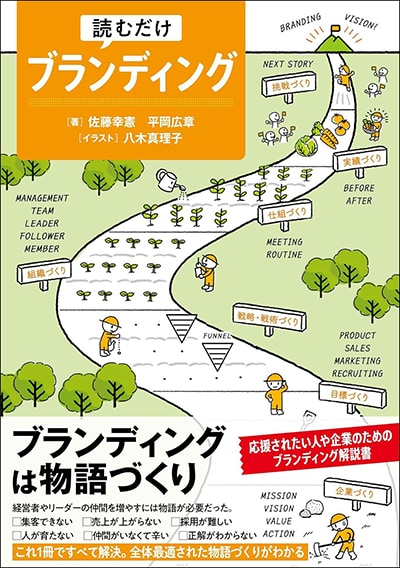
ブランディングとは商品に特化したマーケティング戦略であるだけではなく、「集客」「売り上げ」「採用」などに関わる諸問題を解決し、経営全体を見直す手段でもある。本書ではブランディングを物語づくりと捉え、どのように物語を構築していくべきかを解説する。
[編集] 一般社団法人100年企業戦略研究所
[企画・制作協力]東洋経済新報社ブランドスタジオ