人間の幸せに根差した
ソーシャルビジネスを目指す

目次
ノーベル平和賞受賞者のムハマド・ユヌス氏とバングラデシュで合弁会社をつくるなど、グローバルなソーシャルビジネスの推進と普及に尽力する川村拓也氏。経営するサンパワー(本社・横浜市)は企業の海外進出支援事業を原点に、現在は中古タイヤの輸出と国内タイヤ販売を営み、就労困難者*の雇用率が約7割と、事業を通じた社会課題解決に心血を注いでいます。活動の原点や経営に懸ける思いについて伺いました。
*障害者、高齢者、元受刑者、シングルマザーや留学生など、就職上の課題を抱えている人々をサンパワーでは就労困難者として積極的に雇用している
「社会課題解決」こそが事業を行う目的
私がソーシャルビジネスに本格的に踏み出すきっかけになったのは、ムハマド・ユヌスさんの著書『貧困のない世界を創る』を読んだことでした。ユヌスさんは、バングラデシュで貧困層を対象に事業資金を融資するグラミン銀行を設立し、2006年にノーベル平和賞を受賞された方です。
当時私は30代の初めで、外資系の自動車部品会社でバリバリ仕事をしていました。過分な報酬をいただき、生活には何の不自由もありませんでした。
しかし、ふと思ったのです。このままの生活をずっと続けて、最後に自分の人生の幕を閉じるとき、子どもたちから「お父さんって、人生で何をやってきたの?」と問われたら、果たして胸を張って「これをしてきた」と答えることができるだろうかと。
確かに、外資系企業での仕事は刺激に満ちていました。私のような尖った人間でも受け入れてくれるし、人種や国籍を超えた多様なメンバーがチームを組んで1つのプロジェクトを進めていく。実力さえ認められれば、もっと多くの報酬を得ることができる。
ただ、私にはそれが人間としての幸福につながっているようには見えませんでした。人材が「経営の道具」のように使われて、会社も、社会全体も、一部の裕福な者だけが勝利者になれるような仕組みになっていることが、実際に働いてみてよくわかりました。
そんなときにユヌスさんの本と出合ったのです。仕事の目的は利益ではない。貧困に代表される社会問題を解決し、苦しむ人たちを1人でも多く支えることが、事業を行う目的である。利益はその手段にすぎない──これには衝撃を受けました。そして「人生を懸けて取り組む仕事はこれだ!」と思ったのです。
経営とは「人としてどう生きるか」
外資系企業を辞め、34歳のとき、サンパワーに入社しました。サンパワーは父が創業した会社で、当初は企業の海外進出時の書類作成代行などを請け負い、その後、中古タイヤの輸出を手がけ始めました。日本では廃タイヤになってしまう中古タイヤでも、品質的に十分使えるものが多く、発展途上国に輸出すればリサイクルできるのです。現在は中古タイヤ輸出事業と同時に、新品タイヤも販売する国内直営ショップを運営しています。
外資系企業にいた頃すでに、父との間でいずれ会社を継ぐことを約束していました。しかし、実際に継いでみると、外資系企業とのあまりのギャップに愕然としました。現場で働く若い社員たちがどんな気持ちでいるのか、まったく理解できず、トラブルが頻発しました。どう対応すればいいのかもわからないまま、私は経営者としてこの先やっていけるのだろうかと自信を失った状態でした。
そんなときに支えになったのは、京セラ創業者の稲盛和夫さんや宮城大学名誉教授の天明茂さんの教えです。
稲盛さんから教えられたのは、経営とは生き方そのものだということ。『経営12カ条』にもあるように、事業の意義を明確にし、常に明るく前向きに。その考え方に触れるうちに、現場のトラブルも社員の問題も、会社の問題はすべて経営者としての私に原因があると思うようになりました。経営をよくしたいのであれば、私自身が生き方を改め、よい種をまき続けるしかない。そのことが腑に落ちました。
考えてみれば、わが社がここまでやってこられたのは、社員の皆さんの努力のおかげです。そのことに感謝しなければなりません。その頃からようやく「感謝」ができるようになりました。
それまで、ユヌスさんのソーシャルビジネスは、途上国の貧しい人たちのためにあると思っていました。しかし、そうではない。今、自分の目の前の社員たちのために自分の人生を捧げられずして、どうしてソーシャルビジネスができるだろうか。社会課題解決の根幹には人間の幸せがある。経営者として社員を幸せにして、彼らを人生の勝利者にするのが私の役割だ、と。自分の仕事とソーシャルビジネスが結びついた瞬間でした。
人類が生き残るために必要なビジネス
当社では、通常の財務諸表とは別に、「就労困難者の雇用人数」を重要な経営指標として設けています。社会課題の解決という目的が、どれだけ達成されたのかを問われなければならないと考えているからです。
私が入社した当初の就労困難者雇用率は5%程度でした。現在は約70%になっています。就労困難者は例外的な存在ではなく、当社にとっては当たり前。新事業を検討する際も、「それによってどれだけの売り上げ・利益が見込めるのか」よりも、「就労困難者を何人雇用できるのか」が重要な議題になっています。

もちろん、それを実現するためには利益を出さなければなりません。利益と社会課題の解決は両立しなければならない。それがソーシャルビジネスの基本です。
2017年、私は幸運にもユヌスさんにプレゼンテーションをする機会に恵まれました。そして翌年、ユヌスさんのグラミン銀行と当社で、バングラデシュにソーシャルビジネスの合弁会社を設立することができました。
途上国では自動車部品が十分になく、車の修理技術も未発達です。そのため、車の安全性を担保できないという課題に直面しています。合弁会社では、日本の品質基準に合格した部品供給と、日本の技術を導入した自動車整備工場を造ることで、バングラデシュの車の安全性を高めることに貢献しています。
ソーシャルビジネスは株主をはじめ多くのステークホルダーの理解を得る必要のある大企業よりも、むしろ経営者の意思決定で迅速に実行できる中小企業のほうが取り組みやすいと思います。ただ、当社が取り組んでいるのは、ユヌスさんが定義するソーシャルビジネスです。
「利益の最大化を目的としない」「投資家は投資額を上回る配当を受けない」など7つの原則に基づいています。
ユヌスさんは「既存のビジネスは徐々に消滅していくだろう」と言います。人類は世界規模の環境問題に対していまだに有効な手を打てていません。富の不均衡により社会はいびつになり、AIの進化によって人間存在の意義そのものが問われる時代が来ています。ビジネスの目的の再認識が必要で「ソーシャルビジネスは“善だから”行うのではなく、“人類が生き残るために必要だから”行うのだ」と言うのです。
これからも当社は、社会課題解決に向けて、自分たちの身の丈に合う、できることに全力を尽くしてゆくつもりです。そして「お父さんは、こんな人生を歩んだ」と子どもたちに誇れる父親でありたいと願っています。
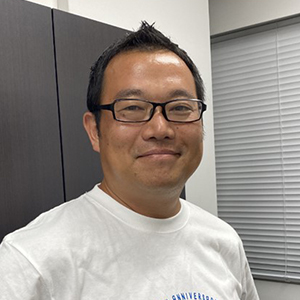
お話を聞いた方
川村 拓也 氏(かわむら たくや)
株式会社サンパワー 代表取締役社長
1975年生まれ。同志社大学経済学部卒業。商社勤務(大阪本社、ドイツ現地法人勤務)後、米国系の自動車部品メーカーに勤務。2010年に株式会社サンパワー入社。2013年代表取締役社長就任。2018年にノーベル平和賞受賞者のムハマド・ユヌス博士が創設したグラミングループと合弁会社(Grameen Japan Sunpower Auto)をバングラデシュに設立。また、サンパワーは2019年に国連環境計画(UNEP)のパートナー企業にも選出された。著書に『80億人起業家構想 僕がユヌスさんと会社をつくった理由』(晴山書店)がある。












