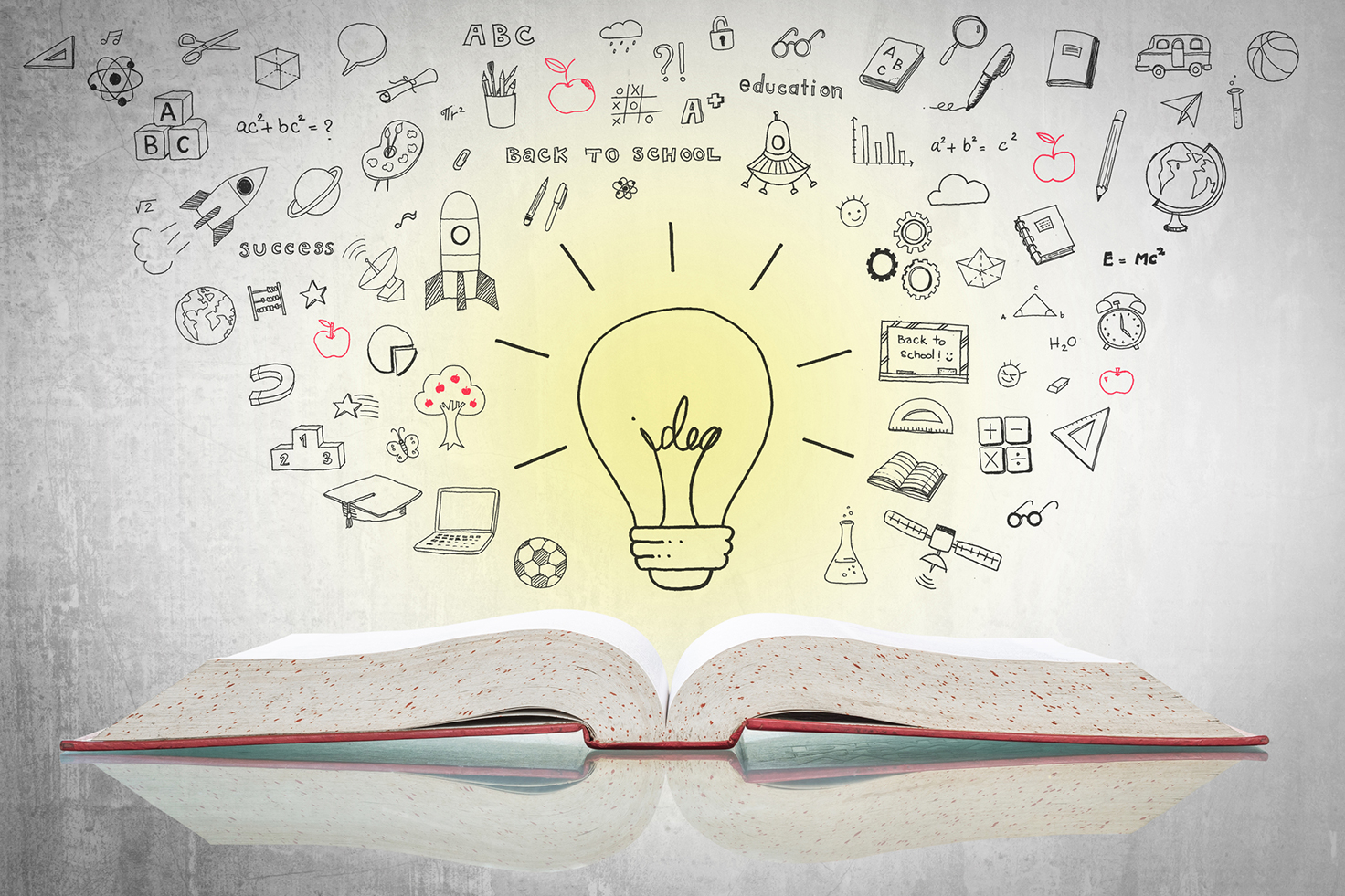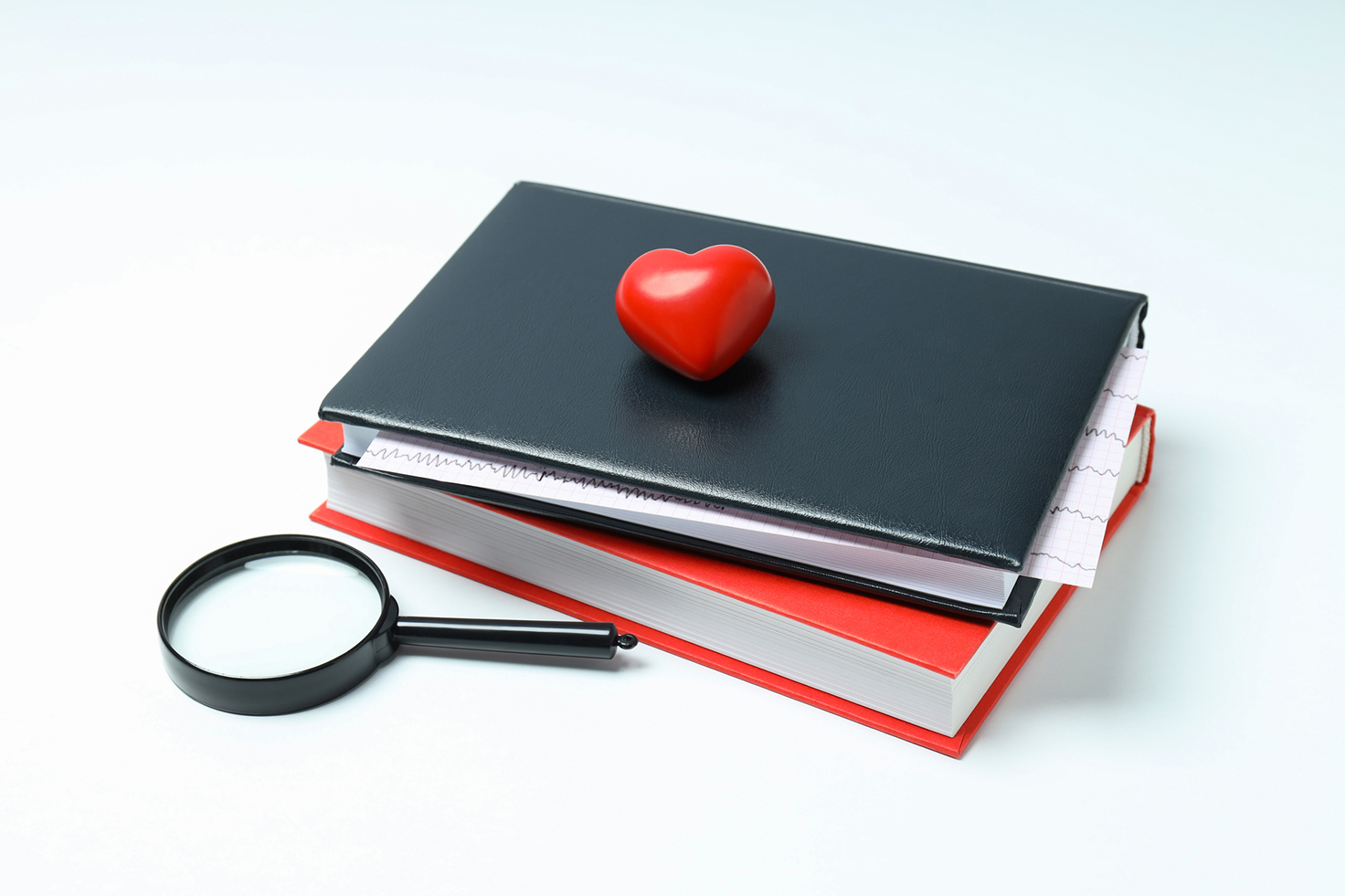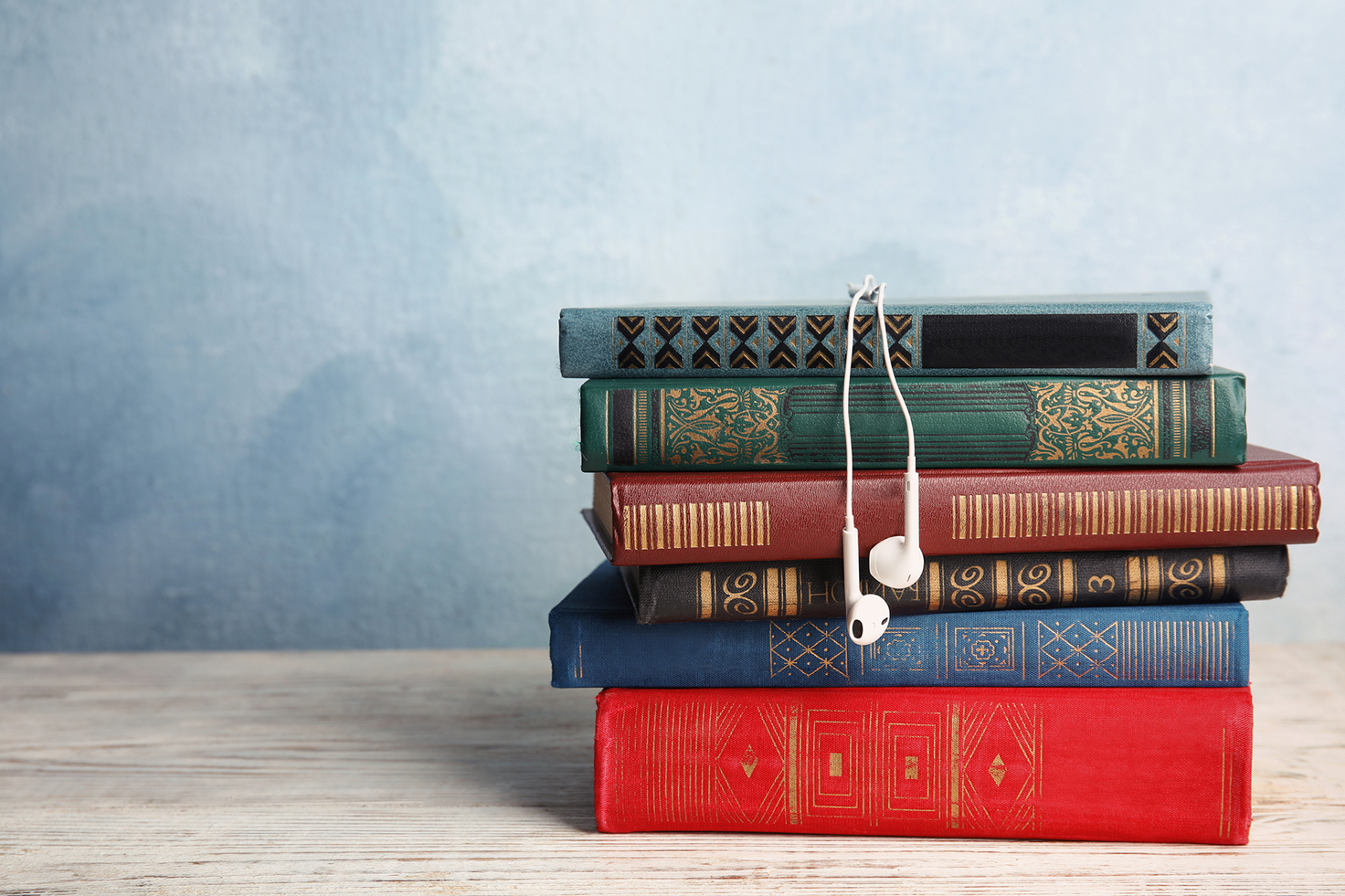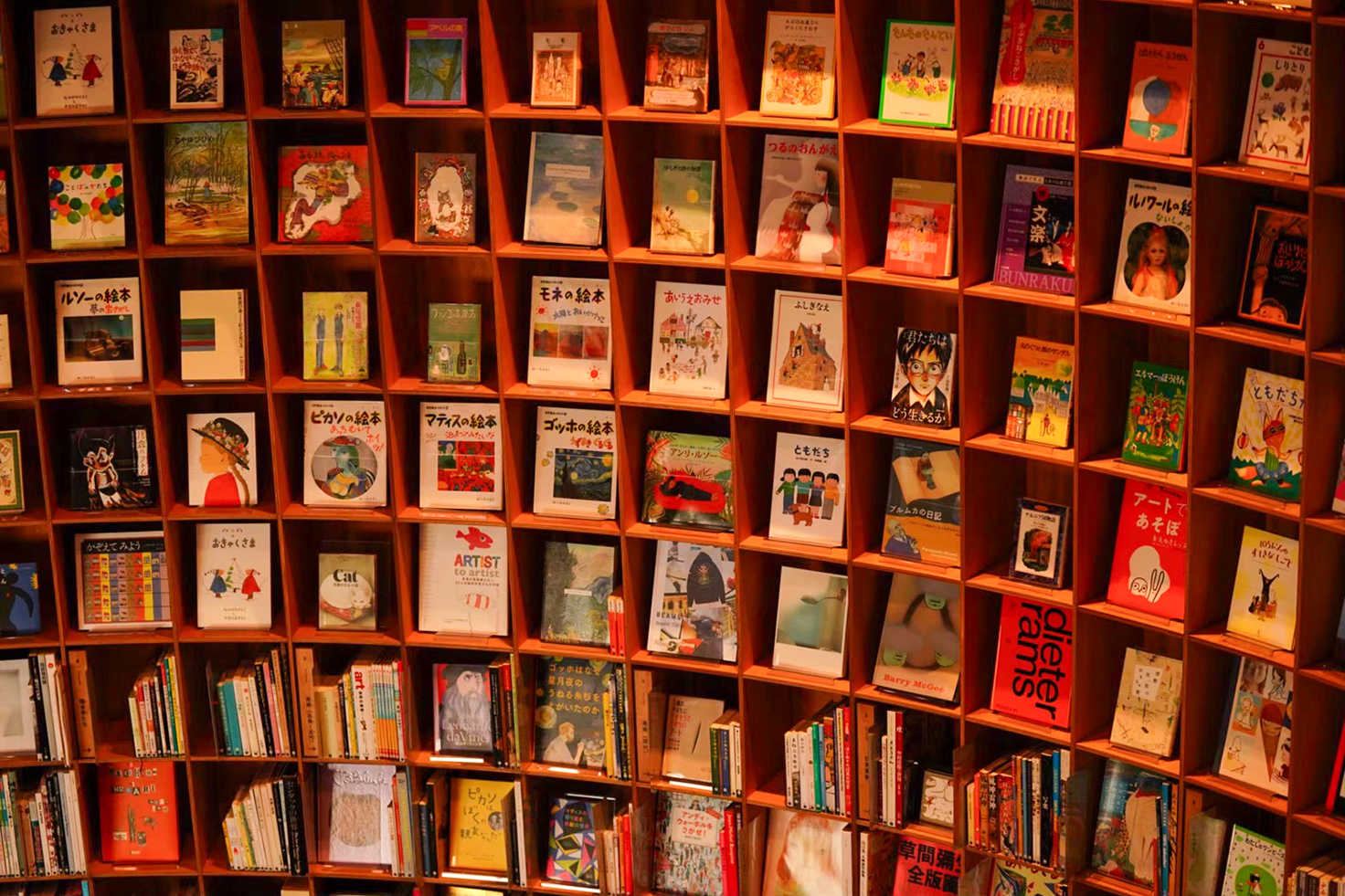経営者にいまおすすめの本6冊 「コンプライアンス」編

目次
コンプライアンスとは、法令や社会的規範を守り、倫理的に行動することを意味します。現代社会において、企業や組織にはその実践が強く求められています。コンプライアンスの徹底は、社会的信頼の獲得や企業価値の向上にもつながります。そこで今回は、コンプライアンスの基礎が学べる6冊を紹介します。
企業人として押さえておくべきコンプライアンス
『改訂版 1分でわかるコンプライアンスの基本』
コンプライアンス研究会著、臼井一廣・儀間礼嗣・木村容子監修 KADOKAWA 1,430円
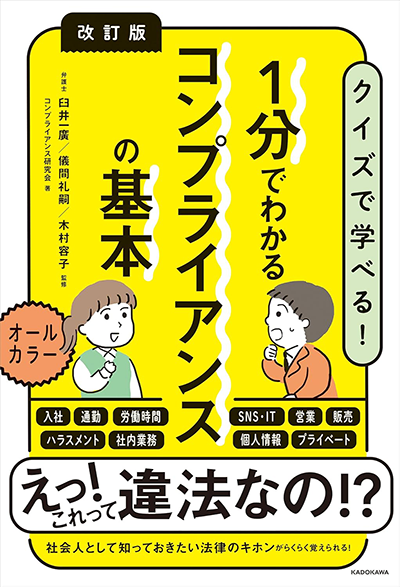
本書は、ビジネスパーソンが知っておくべきコンプライアンスの基本を、全87問の2択クイズ形式で学ぶことができる一冊です。著者は「コンプライアンス研究会」。コンプライアンスの実践による企業活性化を目指す弁護士グループです。
本書第1章は「入社・始業前編」。次いで「規則編」「社内業務編」「IT編」「外回り・接待編」「顧客・販売編」と続き、さらに「終業後・休日編」「働き方改革編」と、全8章で構成されています。ビジネスの現場で起こりうる具体的なイシュー、例えば労働時間、セクハラ、SNSの炎上、フリーランス保護法、LGBT、生成AIなどを取り上げ、リスクの回避方法をわかりやすく解説したり、関連する法令を紹介したりします。読むうちにコンプライアンスへの関心が高まり、また、理解が深まるよう工夫されています。
「通勤電車で痴漢に間違われて逮捕された社員は解雇されるか」という問い(第1章)。答えは、「逮捕されたことのみでは解雇されない」です。痴漢行為は都道府県が定める「迷惑防止条例違反」や刑法の「不同意わいせつ罪」に該当する可能性があります。しかし、無罪を主張する社員に対して即座に懲戒解雇することは、労働基準法が定める「解雇権の濫用」とされます。有罪が確定し、拘禁刑や罰金刑を受けた場合に、初めて就業規則に基づく処分を検討するのがコンプライアンス的に正しい、というわけです。
第4章には「勤務時間中のSNS投稿は問題があるか」という設問があります。答えは「懲戒処分の可能性がある」。仕事中にインスタグラムやX(旧Twitter)といったSNSに投稿する行為は、業務に専念する義務に反するという「職務専念義務違反」となり、コンプライアンスに抵触するおそれがあります。さらに、自社や取引先の情報を書き込んだ場合は「情報漏えい」、それが他社を中傷した内容であれば、刑法の「名誉毀損罪」や「侮辱罪」、「信用毀損罪」に問われる可能性も否定できません。
第8章は働き方改革に焦点を当て、昨今注目される社会的課題を取り上げています。例えば、労働者が有給休暇を取れない状況は労働基準法により会社が法的責任を問われることや、正社員と非正規社員の不合理な待遇格差が労働契約法により是正を求められることなど、現場に即した実践的な知見が得られます。
このように本書は身近なケースを題材に取って、コンプライアンスを遵守することの重要性を平易な言葉でわかりやすく解説しています。
コンプライアンスとは「ステークホルダーの期待に応えること」
『改訂版 コンプライアンスのすべて〜取り組むことが求められるこれまでとこれからのテーマ〜』
中島茂著 第一法規 3,080円
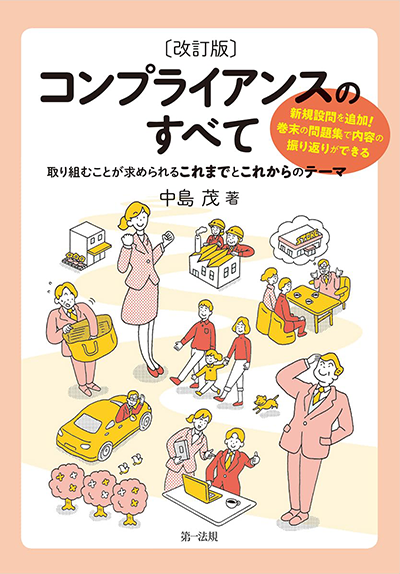
本書の著者である中島茂氏は、コンプライアンス推進活動に精通する弁護士です。中島氏はコンプライアンスを単なる「法令遵守」に留めず、その本質を「相手の期待に応えること」と定義します。
事故や不祥事を起こした企業が、社会から厳しい非難を受けることがあります。法令を遵守していても、です。それは、消費者や従業員、取引先、社会、そして株主といったステークホルダーという「相手」からの「期待」を裏切ってしまったから、つまり中島氏が定義するコンプライアンスを実現できていなかったからです。
例えば、延べ床面積が3,000平方メートル未満の店舗であれば、スプリンクラーの法的な設置義務はありません。ですから設置しなくても、ただちにコンプライアンス違反とはなりません。
しかし法的に問題なかったとしても、「建物の構造的に」あるいは「業務内容的に」、スプリンクラーを設置したほうが安全確保上望ましいケースはあります。そのときはコストをいとわず自主的にスプリンクラーを設置する。かくしてステークホルダーの「期待に応える」――。これが、中島氏の考える「真のコンプライアンス」です。
本書のUnit1ではこのように、コンプライアンスの本当の意味について整理しています。
Unit2は、企業という組織の特質と、コンプライアンスの関係について解説します。会社は、大きく捉えると「縦の線」と「横の線」で構成されています。縦の線は、事業を推進するために内規を定めて、必要に応じて指示・命令を出す「内部統制システム」を担います。横の線は、経営幹部の動きを横から観察し、時には方向性を是正するための「コーポレートガバナンス」の働きをします。
Unit3では、従業員に対するコンプライアンスをテーマに取り上げます。企業は、従業員に対する安全配慮義務を負っています。そのため、社内の設備点検や防災体制の整備はもちろん、ハラスメントや長時間労働などを防ぐことで、従業員の心身の健康を守る必要があるのです。
Unit4は取引先との正しい付き合い方を、Unit5は機密情報や知的財産を守ることの大切さを説明。Unit6では、対消費者コンプライアンスとして、消費者に安全な商品を届けるための設計、製造、指示・警告表示といった安全確保のあり方や、公正な営業活動について解説します。
最後に、社会コンプライアンスとして、SDGsや地球環境保全といった世界的課題に対しても、従業員一人ひとりが協力していくことが望まれると総括。巻末には本書の内容を振り返る問題集が付いており、理解度をチェックできます。
企業コンプライアンス実現のための思考法
『いちからわかる「コンプライアンス」Q&A~今さら聞けない社長のギモンを解決~』
鳥山半六著 第一法規 2,310円
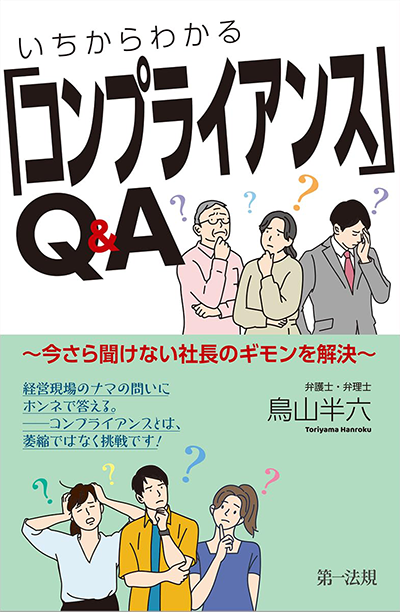
本書は経営者や経営幹部陣を主な読者層に想定した、企業コンプライアンスの入門書です。著者は、長年にわたり企業法務や経営法務、法曹倫理に関わってきた弁護士の鳥山半六氏。鳥山氏が実際に行ってきたセミナーや弁護士業務などから寄せられた現場のリアルな声を取り上げ、全44問のQ&A形式で解説します。
本書は、コンプライアンスの基本的な考え方をまとめた「理論」編と、多様なケースに対する判断基準を指し示す「実践」編の二部で構成されています。
前半の理論編では、経営者がまずインストールしておくべき「モノの考え方」として、「規範的思考」を提示します。これは「事実」と「規範」とを峻別し、事実をありのままに直視したうえで、その事実がコントロール可能かどうかを見極め、「規範」との不適合があればそれを適合へと導くための思考法です。鳥山氏は、この思考法こそがコンプライアンスの基本的な考え方であると説きます。
さらに、「企業の成長と従業員の幸せの関係は?」「コンプライアンスは大企業が考えるべきことで、中小企業には関係ないのでは?」「なぜ経営者は株主総会に力を入れる必要があるのか」といったさまざまな問いに対し、端的な結論とわかりやすい根拠を提示。経営現場で頻出する疑問に対し、明快な答えを導き出します。
実践編では、「平時」と「有事」に分け、それぞれの疑問と対処法を解説します。例えば「社内不正を防ぐには?」という問いには、行動心理学に基づく防止策や、経済産業省発行の「秘密情報の保護ハンドブック」などを紹介します。また、有事につい口に出してしまいがちな「言い訳」とその裏に潜む本音もひもときながら、「人の振り見て我が振り直せ」と痛烈なアドバイスを述べます。
鳥山氏の解説は、偉人の名言なども交えながら、端的でわかりやすく、経営者の目線に寄り添った内容になっています。法律知識や法務に明るくない人でも、コンプライアンスの本質を短時間で理解できるでしょう。
とくに、コンプライアンスに対する取り組みの意義をまだ見いだせていなかったり、姿勢を定めかねていたりする経営者にとっては、必読の一冊といえます。
『図解 コンプライアンス経営(第5版)』
浜辺陽一郎著 東洋経済新報社 2,420円
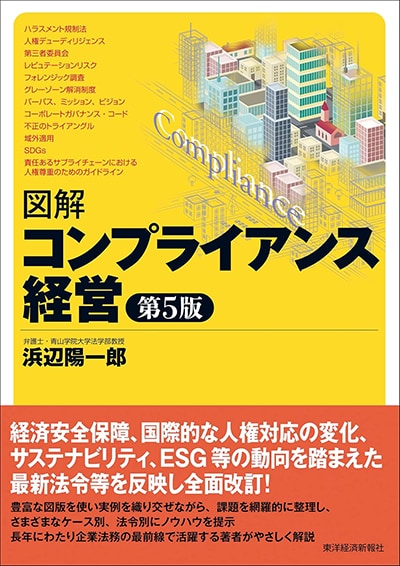
コンプライアンスに関する取り組みの形骸化や空洞化の弊害が指摘される中、あらためて根本的意味を再検証。経済安全保障や国際的な人権対応、サステイナビリティ、ESGなど、現代企業に要請されるコンプライアンスも網羅し、豊富な図版や実例、最新法令などとともに解説する。
『インテグリティ コンプライアンスを超える組織論』
中山達樹著 中央経済社 2,200円
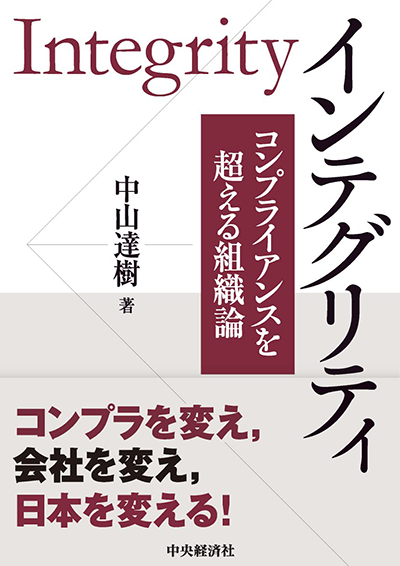
「インテグリティ」は誠実、真摯、高潔、一体性といった意味を持つ言葉だが、本書では広く「期待されたことを行うこと」と定義。コンプライアンスの延長線上にあるこの理論・戦略を取り入れることで、リーダーシップやコミュニケーションを向上させ、ひいては日本の閉塞感も打破できると著者は語る。
『コンプライアンス実務ハンドブック』
長瀬佑志・斉藤雄祐著 日本能率協会マネジメントセンター 3,080円
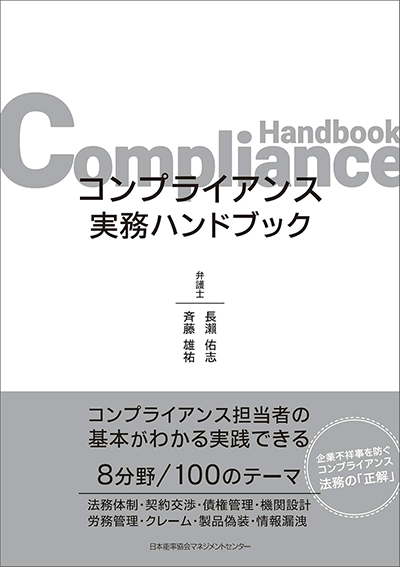
企業法務においてコンプライアンスリスクが生じやすい場面の注意点を整理。法務体制、契約交渉、債権管理、機関設計、労務管理、クレーム、製品偽装、情報漏洩という8つの分野から100のテーマを取り上げる。コンプライアンス担当者の実務に役立つ一冊。
[編集] 一般社団法人100年企業戦略研究所
[企画・制作協力]東洋経済新報社ブランドスタジオ