中小企業のためのDX実践のポイント

目次
DXの実践手順やデジタルツールの選定・導入はどうあるべきか。これからDXに挑戦する中小企業の皆様へ向けて、株式会社デジタルシフトウェーブ代表取締役社長の鈴木康弘氏に、中小企業の代表的な取り組み事例を基に、DX実践のポイントや留意点を詳しく解説していただきました。
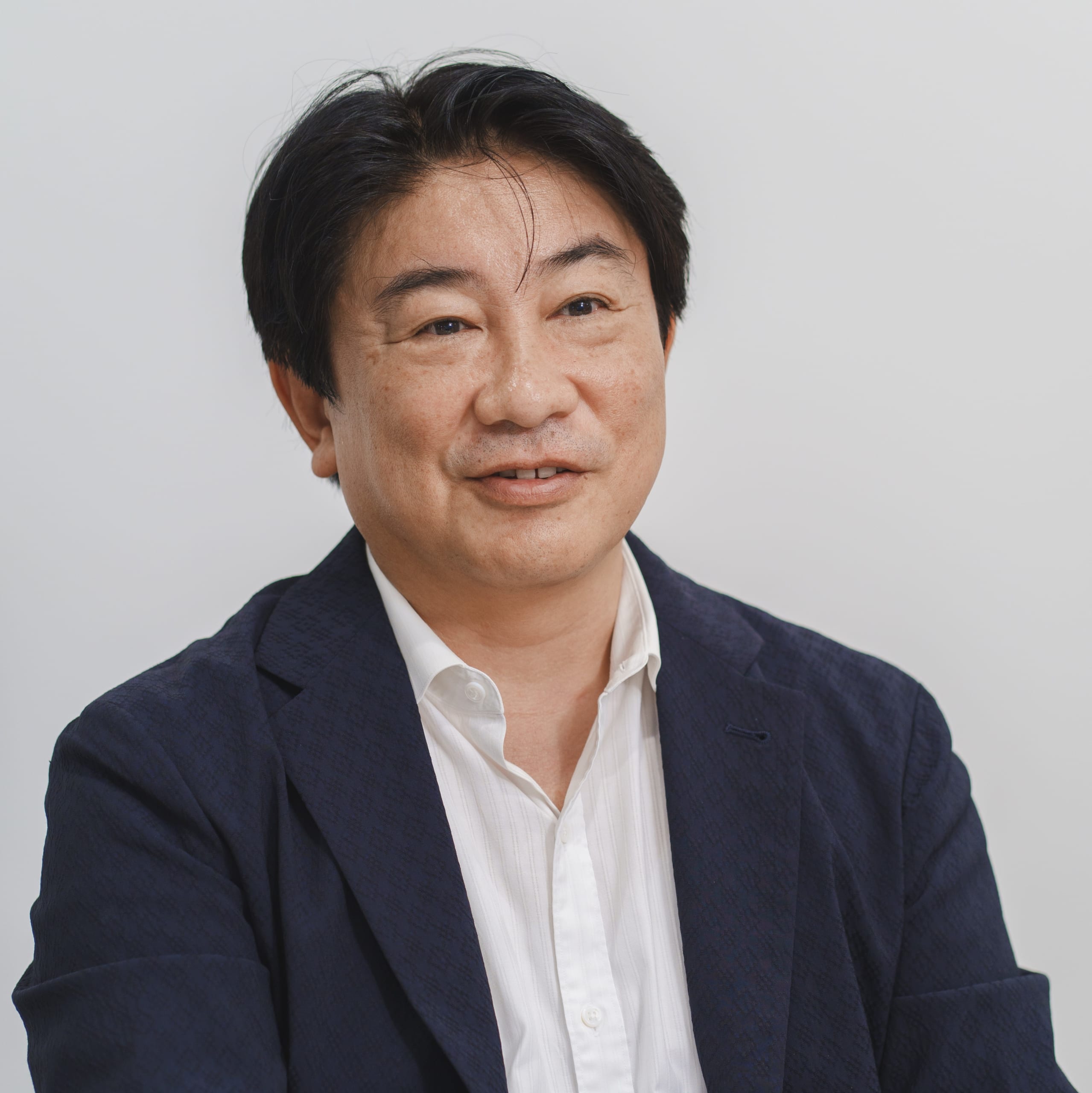
お話を聞いた方
鈴木 康弘 氏
株式会社 デジタルシフトウェーブ 代表取締役社長
1987年富士通に入社。SEとしてシステム開発・顧客サポートに従事。96年ソフトバンクに移り、営業、新規事業企画に携わる。 99年イー・ショッピング・ブックス(現セブンネットショッピング)を設立し、代表取締役社長就任。2014年セブン&アイ・ホールディングス執行役員CIO(最高情報責任者)就任。グループオムニチャネル戦略のリーダーを務める。15年同社取締役執行役員CIO就任。16年同社を退社し、17年デジタルシフトウェーブを設立。同社代表取締役社長に就任。ほかに、日本オムニチャネル協会会長、SBIホールディングス社外役員を兼任。
老舗企業S社に見るDX実践とその成果
DXが重要だとわかっていても、どこから手をつけたらいいのかと悩む中小企業の経営者の方は多いでしょう。そこでまず、DX実践の参考になる事例として、中小企業S社の取り組みをご紹介します。
同社は1900年創業の老舗企業で、着物・宝石・装飾品などの販売を手がけています。複数の県で約80店舗を展開し、のべ10万人以上もの会員顧客を抱える地域の優良企業です。ただ、同社を取り巻く環境は大きく変わりつつあります。着物の小売市場は年々縮小傾向で、持続的な成長を見込める事業モデルへの転換を迫られていました。さらに同社はこれまで、ベテラン販売社員が培ってきた顧客との信頼関係を強みにしてきたものの、顧客情報や営業ノウハウが属人化し、全社で共有できていないことも課題でした。年配の販売社員が退職すると顧客も離れ、それが業績悪化を招きかねない状況でした。
そこで同社社長は、これらの課題を乗り越えるために、DXに取り組むことを決意しました。経営トップの強いコミットメントの下、メンバーを部門横断で集めたDX推進室を発足。自社の現状と課題の分析に乗り出しました。その上で必要なデジタルツールを選定し、自社の目的にふさわしい改革を実践してきました。
具体的には、販売社員たちがそれぞれ蓄積する約10万人の会員顧客の情報を集約してデータベース化。誰もがタブレット端末を使って手軽に閲覧できるようにしました。この結果、担当の販売社員が不在でも、顧客一人ひとりの好みや過去の購入履歴に沿った接客や提案が可能になりました。データベースとLINEを連携し、顧客の属性やニーズに応じたイベントも告知できるようにしました。
さらに顧客向けのアプリも開発。顧客がどんな着物や小物を所有しているのかを、写真を使って容易に確認できるようにしました。顧客は自分の着物姿を写した写真をアップしたり、写真をもとにS社の販売社員からコーディネートのアドバイスを受けたりすることもできます。アプリを使ってコミュニケーションを図れるようにしたことで、顧客とS社の関係性はより親密になったといいます。
なお同社は、アプリを使って着物の保管をS社に申し込める新サービスも開始しました。デジタルツールを活用して顧客とのコミュニケーションを強化した結果、新規事業の創出にもつながったということです。非常にすばらしいDXの事例だと思います。
課題解決から価値創造へ〜DX成功の5つのポイント
では、S社のDXがなぜ成功したのか。そのポイントをいくつか解説します。
①「課題の明確化」がDXの出発点
「DXがブームだから」といった発想ではなく、まず自社の課題を明確化し、それを解決するには自社の業務をどう変革すべきか、どうしたら新たな価値を生み出せるかを真摯に考える。その上で、課題解決や価値創造の手段としてデジタル化を進めていくことが重要です。前述のように、S社は「国内の着物市場の縮小」と「顧客情報・営業ノウハウの属人化」といった課題を明確に認識し、これらを起点にDXを実践してきました。これが成功の最大の要因です。
②部門横断的なDX推進 チームを発足
S社では一部の社員にDX推進を任せず、経営者がしっかりとコミットメントしています。さらに、さまざまな部門からメンバーを募った横断的な推進チームも発足させています。これらもDXを成功に導いた要因の1つです。最前線で仕事を担い、現場の実情をよくわかっている人たちが参加しなければ、視点が偏りかねません。DXを必要とする機運も高まりません。
なお、私の過去のコンサルティング経験からいうと、DX推進チームのメンバーは、一定の成果を上げたら元の職場に戻すのが望ましいでしょう。DX推進で活躍した社員が伝道師となり、それぞれの現場にDXを浸透させる役割を果たしてくれるはずです。
③抵抗勢力への配慮を怠らず、真摯に説得
DXを含む大規模な変革を断行するとき、過去の仕事のやり方や価値観を否定しなければならないケースが出てきます。しかし、誰だって否定されるのは嫌なもの。変革することに抵抗感を示す人たちが必ず現れます。その際、抵抗勢力を批判したり放置したりせず、真摯に説得していくことが大切です。
変革に抵抗するのは、自分の未来がどうなるのかわからないから。さらには、自分の役割や居場所がなくなってしまうのかと不安に感じるから抵抗するわけです。S社の場合も、ベテラン販売社員たちから「自分が頑張って蓄積してきた顧客情報を奪われるのではないか」「難しいデジタルツールを押しつけて、年配の自分たちをお払い箱にするつもりではないか」などと反発の声が出たそうです。
そこでS社では、DXがなぜ必要で、働く現場にどんなよい変化が生まれるのかを丁寧に説明しました。ベテラン販売員たちが苦労して集めた宝物のような情報やノウハウを全社で共有し、顧客にもっと喜んでもらうために活用するのだと繰り返し伝え、納得してもらったそうです。
「DX」と聞くと華々しい企業変革をイメージしがちですが、実際は地道な説得作業が重要な位置を占めます。その意味でDX推進チームには、実直な性格で、人のために粘り強く行動できる社員を抜擢しておくとよいでしょう。そういう人材こそ、変革のリーダーとしてふさわしいからです。
④システム会社任せにせず、自前でDXを実践する
DXを外部のシステム会社に任せたら失敗したというケースは少なくありません。システム会社はあくまで情報システムの専門家です。自社の課題解決に必要な、変革を深く理解して提案してくれる会社とは必ずしもいえません。システム会社任せにすると、自社の社員のデジタルスキルが一向に上がらないという問題も出てきます。
S社もこの点を意識して、地元自治体の支援センターなどの助言を受けて、システム会社を選定しました。しかもシステム会社任せにするのではなく、汎用的なシステムを活用して、できるだけ自社社員主導でデータベースの構築などを進めました。これも成功の大きな要因といえます。
かつて企業が情報システムを導入する場合、外部のシステム会社に独自のシステムをイチから構築してもらうのが一般的でした。稼働に必要なサーバーや通信回線なども自社で保有して運用する「オンプレミス」という形態で構築するケースがほとんどでした。今もそのイメージを持っている方が多いかもしれません。しかし今の時代、DXに取り組むなら、できるだけ汎用的なシステムを活用することが重要です。最近は、わずかなプログラミングの知識でシステムを開発できる「ローコード」や、プログラミングの知識なしてもシステムを開発できる「ノーコード」と呼ばれるツールが台頭しつつあります。これらを利用すれば、データベースやECサイトも自社で容易に構築できるようになります。オンプレミスでイチから開発・運用するのに比べて低コストで構築できるし、外部の専門家を頼らず、自社の社員が主導することで、社員のデジタルスキル向上も見込めます。
⑤業務改善で終わらず、価値創造へつなぐ
最後のポイントは、S社の取り組みが効率化のための業務改善で終わらず、新たな価値創造につながったことです。
前述のようにデジタルツールを使って顧客とのコミュニケーション機会を増やした結果、ニーズを満たす新サービスの創出につながったのです。
経済産業省が発表した「中堅・中小企業等向け『デジタルガバナンス・コード』実践の手引き」でも指摘するように、DXを実践するには「どんな価値を創出するか」ではなく、「AIを使って何かできないか」といった発想に陥りがちです。あくまで、DXとはデジタルテクノロジーを活用して、顧客視点で新たな価値を創出していくことです。その本質を常に念頭に置いた上で、ぜひ多くの中小企業がDXに挑戦し、成果を上げていただきたいと考えています。
【編集・提供】株式会社ボルテックス ブランドマネジメント課
【制作協力】株式会社東洋経済新報社












