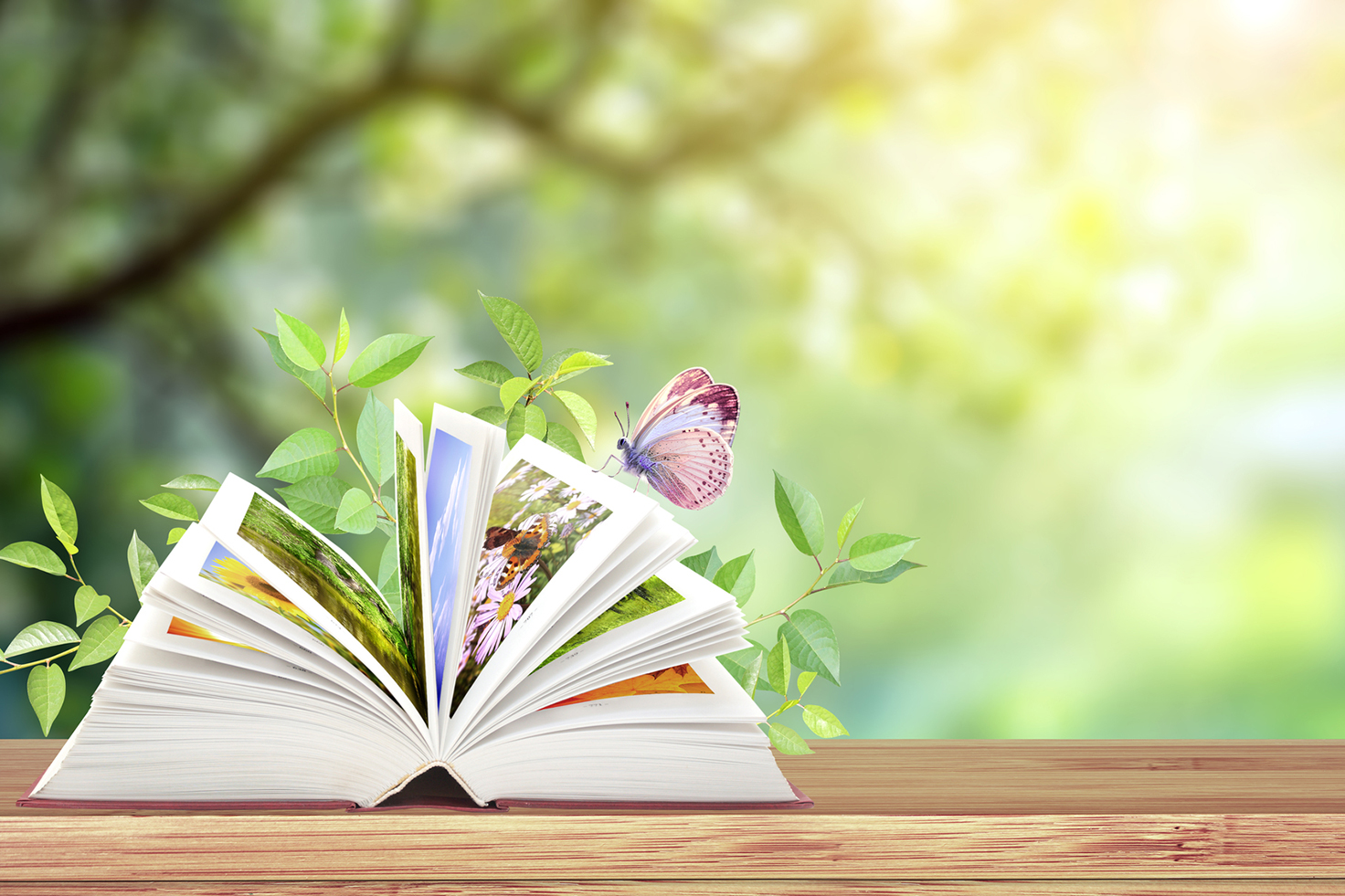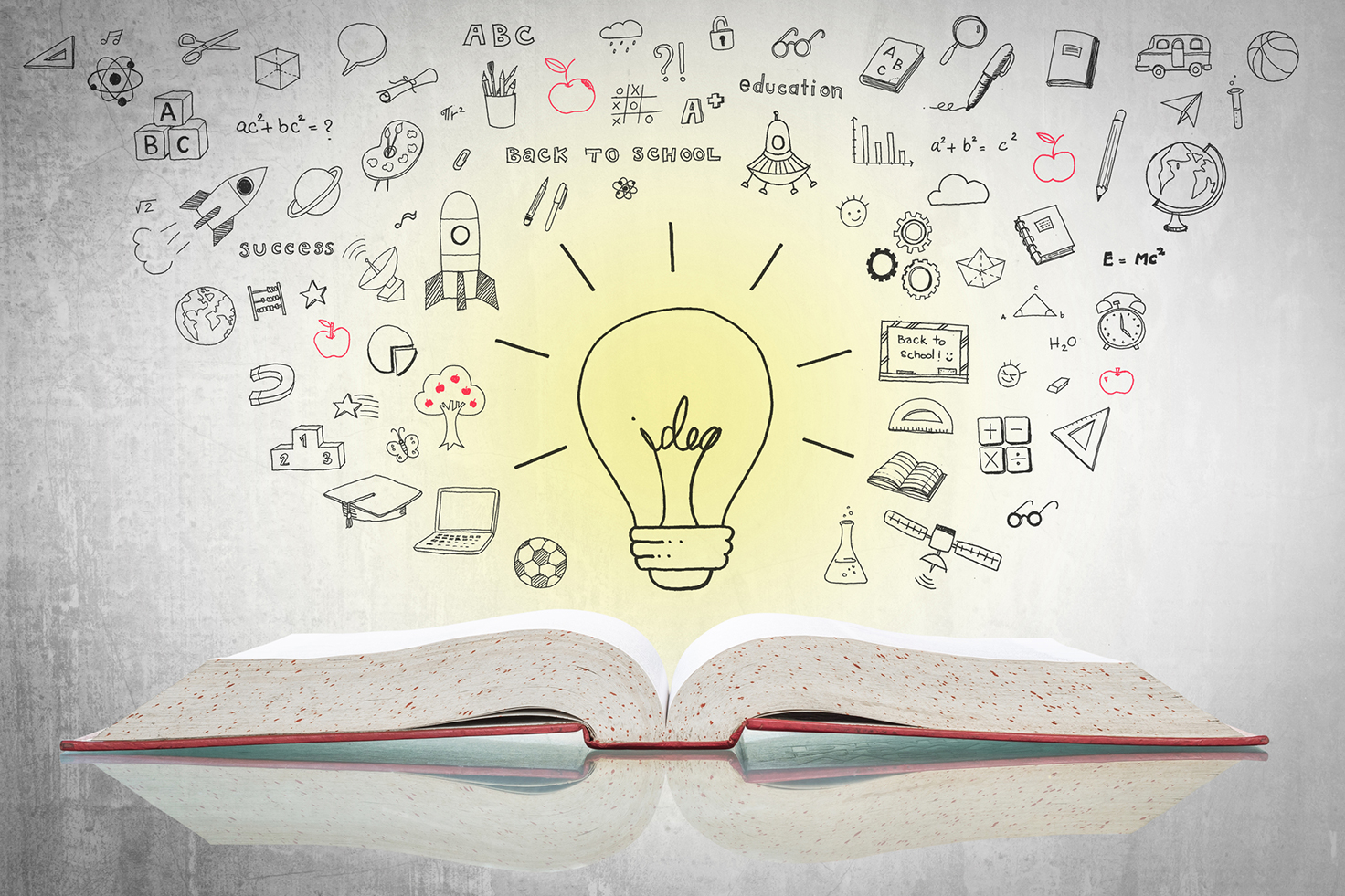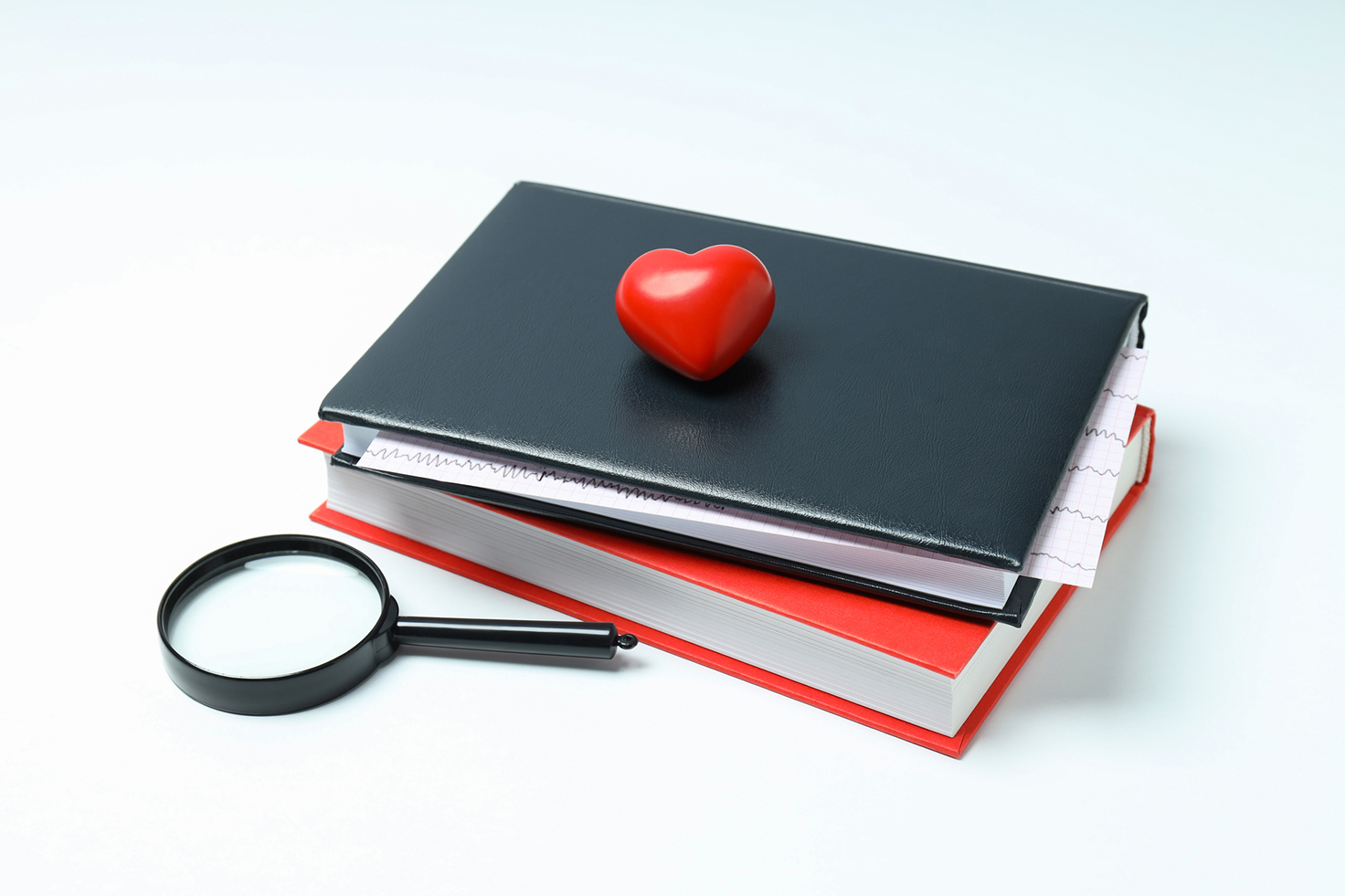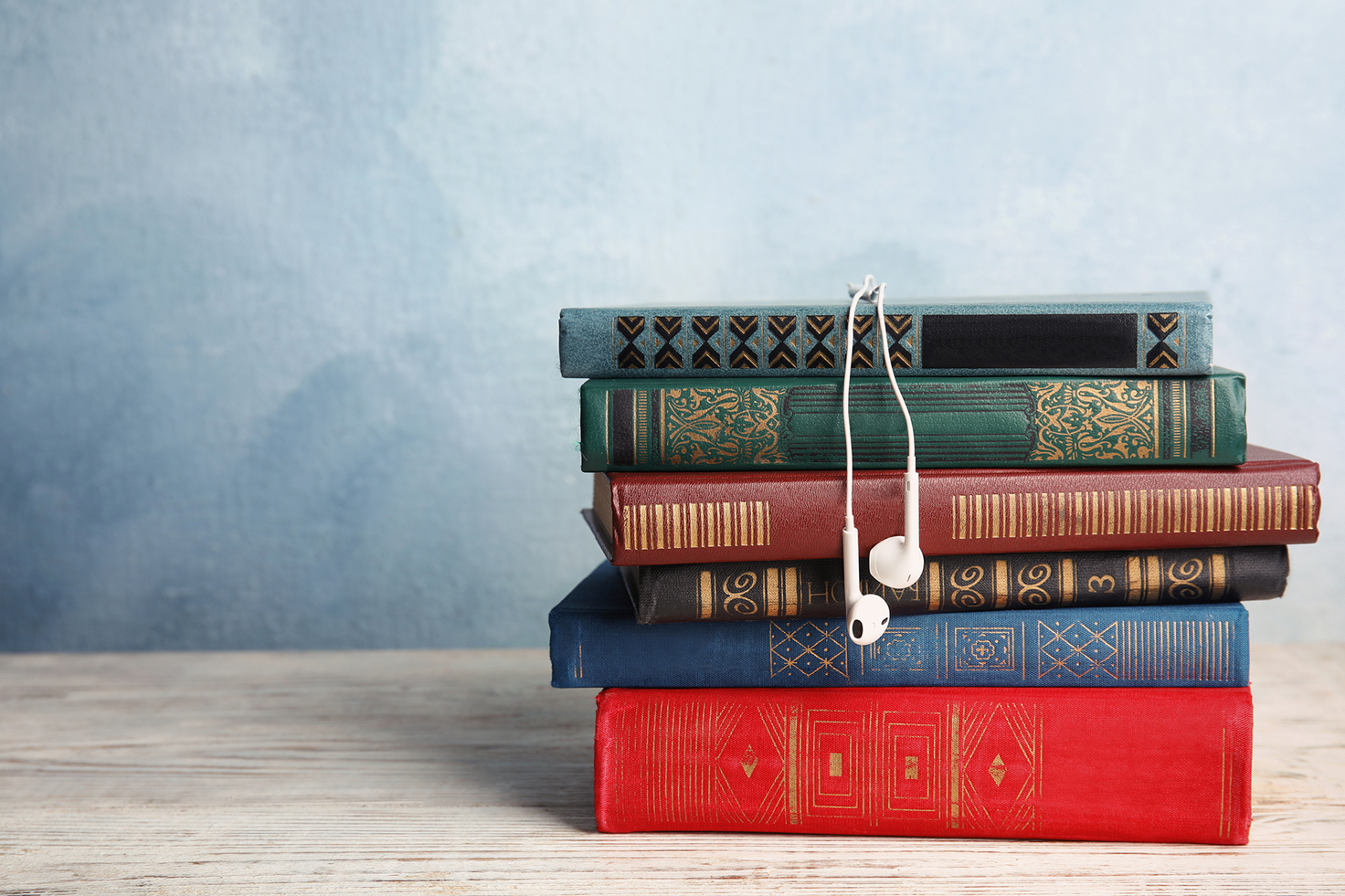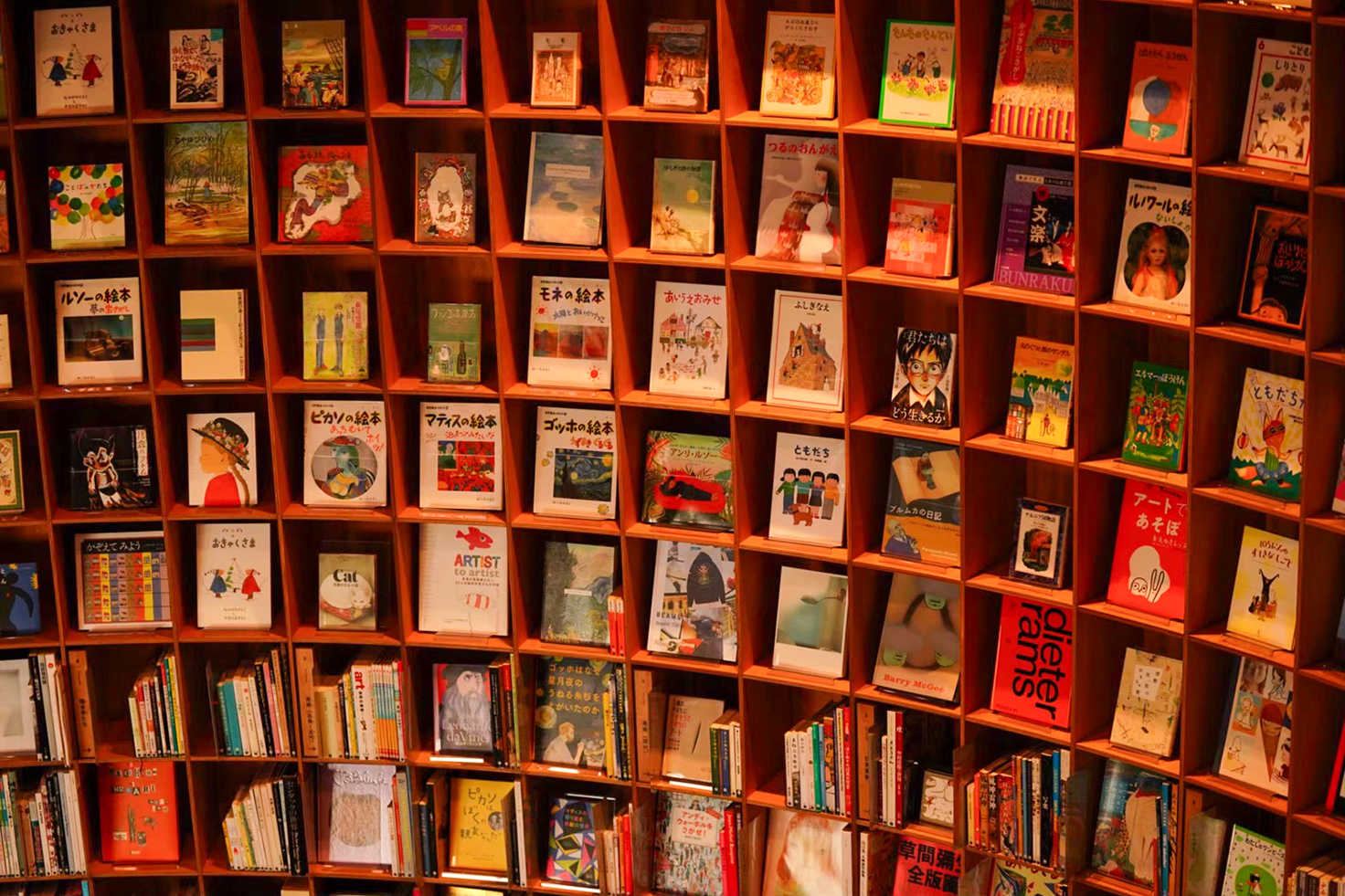経営者にいまおすすめの本6冊 「戦略人事」編

目次
2010年代後半から急速に世界に広まった「人的資本」という概念は、企業価値をはかる重要な指標となりつつあり、人事部門においては戦略性がますます求められています。国内では20年に「人材版伊藤レポート」(経済産業省)が公表されて以降、人的資本開示への関心も高まっています。ただし、これらを背景に企業が戦略人事に取り組もうとするとき、多くの誤解と障壁があるようです。それらの課題を克服するために役立つ、厳選の6冊をご紹介します。
『「業績をつくる」人事へアップデートする 経営者のための「戦略人事」入門』
古田勝久著 ダイヤモンド社 1,760円
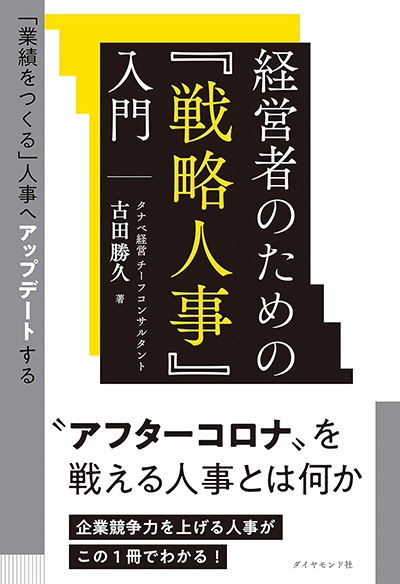
「利益を上げる、業績をつくる」ための戦略人事
日本における労働環境や人事・雇用形態は、新型コロナウイルスの感染拡大以後、大きく変化しました。テレワークが一般化したことによって最低限のITリテラシーが必須となり、業務を円滑に進めるためのソフトウェアの普及が、部署内メンバーの分業だけではなく、即席チームによるプロジェクト形成をも容易にしました。そのケースでは中間管理職を介さず、上級管理職が現場社員に直接指示を出す場合もあるなど、コロナ禍以前と比べ、労働形態の多様性は劇的に増しています。こうした状況では、現在いる「人材」を「人財」に昇華することが求められています。
著者の古田勝久氏が所属するタナベコンサルティングでは、「企業は環境適応業、変化と向き合う生き物である」と提唱しています。激変する環境下においても各企業は、経営の大前提である「利益を上げる、業績をつくる」ための事業を行うとともに、それを支える組織を変革することが重要になります。そのための人事のあり方としては、人事部門が「業績をつくる」という意識を持ち、戦略人事へと自らをアップデートし、「自社が生き残る組織や人をつくる」という使命を果たす必要があります。
「戦略人事」とは、他社との差別化や、競争優位性を発揮するための人事施策を行う人事機能を意味し、従来からある労務管理などの「ルーティン人事」、社内制度としての「インフラ人事」と三位一体で運用されるべきものだと指摘します。
古田氏は、人事部門が従来のオペレーションに留まらず、経営者のパートナーとして攻めの人事施策を行うことで事業競争力を上げ、あらゆる環境に適応する企業体質へと改善することが重要であると説明。本書では、それを実現するための人事施策を、「戦略人事とは何か」(第1章)、「採用」(第2章)、「育成」(第3章)、「評価・処遇」(第4章)、「戦略的な組織づくり」(第5章)の5章にわたって解説しています。
『再生・日本の人事戦略 失われた30年を取り戻す実践手法』
内藤琢磨著 日本経済新聞出版 2,860円
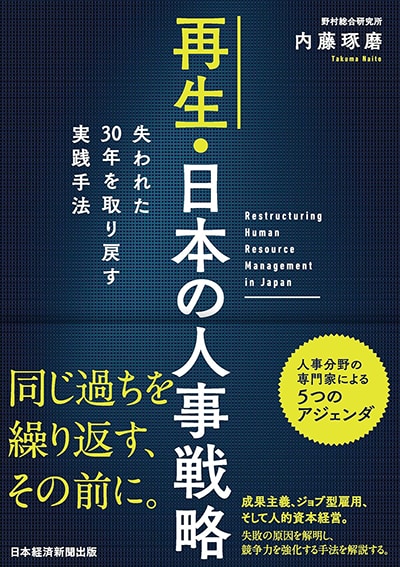
戦略人事で「失われた30年」を取り戻す
「人的資本経営」に関する認知が広がり、「人的資本開示」への関心が高まった結果、日本企業においても経営と人事部の距離感が縮まりつつある、と著者の内藤琢磨氏は分析しています。
人材戦略では「自社の人材戦略とは何か」を明確にしたうえで、その戦略に「どのように取り組んでいくか」を考えることが重要としていますが、その一方で、多くの日本企業では「開示そのものが目的化」しており、自社の組織や人材が真の強さを取り戻すような人材戦略の構築、またはその実行がなされていないと、内藤氏は指摘しています。
グローバル人事、コンピテンシーモデル、ジョブ型人事などは、手段であるにもかかわらず、いつの間にか日本企業では、それらの導入が目的化してしまい、その結果、日本の人材競争力は低下し、「失われた30年」が引き起こされた……。そう捉える内藤氏は、この事態を今一度反省し、日本企業が同じ過ちを繰り返さないために、本書を執筆したと語ります。
野村総合研究所のグローバル経営研究室のプリンシパル(主任研究者)を務める内藤氏は、第1章「既視感アリアリ、対応に追われる人事部門」において、そもそも「人的資本開示」が一般化した経緯と必要性、さらにはその指標に対する日本企業の誤解や、海外企業との雇用形態の違いなどを指摘。その結果として過去の人事改革が成功しなかった理由を、第2章「失われた30年 なぜ人事改革は失敗に終わるのか」で解説しています。
第3章から第5章では、とくに誤解されがちな「ジョブ型人事」「人への投資」「報酬の引き上げ」「インセンティブ」などへの洞察が加えられるとともに、日本企業が今後、それらの課題にどのように取り組むべきかを提言。また、より効果的な人材戦略を実行するための「見える化」や「人事部門の再活性化」が第6章と第7章で解説され、最終章である第8章では、経営者自らが実行すべき事柄が列挙されています。
『図解でわかる!戦略的人事制度のつくりかた』
株式会社フィールドマネージメント・ヒューマンリソース小林傑、山田博之、野崎洸太郎著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2,640円
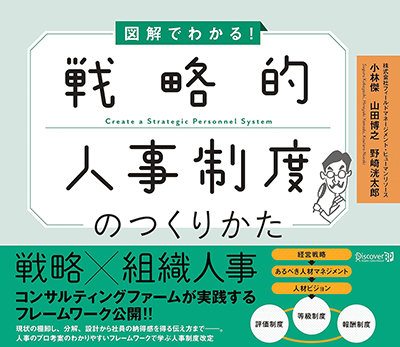
戦略人事のフレームワークとは?
人事制度を改革しようと考えたとき、またはその必要性に迫られたときに、何から考えはじめ、既存の人事制度の何を残し、何を変えていくべきかを、見極める必要があります。そんなときに役立つのが、本書の示す「フレームワーク」です。
フレームワークとは、何かしらの目的を達成しようとするときに使用される「考え方」の枠組み、または、その枠組みを「見える化」するためのツールを意味します。
経営戦略やマーケティングの世界では、SWOT分析、3C分析、5要因分析、7S分析など、欧米の研究者や企業などが考案した有名なフレームワークが多数あります。しかし、人事戦略や人事制度に関しては、そうした欧米発のフレームワークが日本で活用されていません。なぜなら欧米諸国と日本の雇用制度が大きく違うために転用が難しいからです。そんな中でも、本書では図版がふんだんに使用され、筆者の示すフレームワークがひと目で把握できるよう工夫されています。
フレームワークが満載の同書ですが、冒頭で人事の仕事を、「経営戦略を実現するために、人材の質と量を最適化する機能」と定義しています。
近年では中途採用市場の拡大、派遣労働の一般化、ジョブ型雇用の推進などにともない、経営環境の変化が加速し、迅速な経営戦略の変更を迫られています。その状況下で企業が人事制度を最適化しようとした際、「組織は戦略に従う」、または「戦略は組織に従う」という、2通りの考え方があります。
日本で多数を占める中堅規模の企業では、組織能力によって戦略が制限される局面のほうが多く、「戦略は組織に従う」傾向にありますが、その場合、戦略を実行する組織を形成する必要があります。その局面において、人材面で寄与するのが人事戦略であり、その実現のために設計されるのが人事制度だと、本書では解説しています。
本書は、高度経済成長期に創業された従業員数300~3,000名程度の企業を想定して書かれています。人事に関する必須事項が平易な言葉で語られる本書は、人事未経験の方にも最適な一冊といえます。
『人手不足時代を生き抜く地方の会社の人事戦略』
本田淳也著 労働新聞社 1,870円
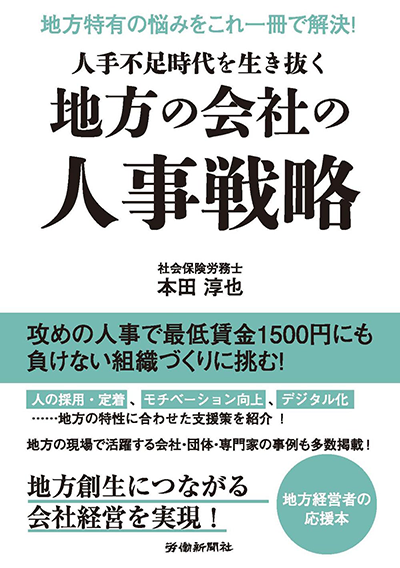
人手不足や最低賃金の上昇など、地方の企業の悩みは多い。そうした会社に特化して人事戦略を具体的に解説したのがこの一冊。採用、定着、デジタル化推進などの重要テーマに関して支援策を提示しつつ、一問一答形式で労務管理のポイントを解説。地方企業の経営者や人事担当者、社労士におすすめ。
『持続的成長をもたらす戦略人事 人的資本の構築とサステナビリティ経営の実現』
須田敏子・森田充著 経団連出版 2,200円
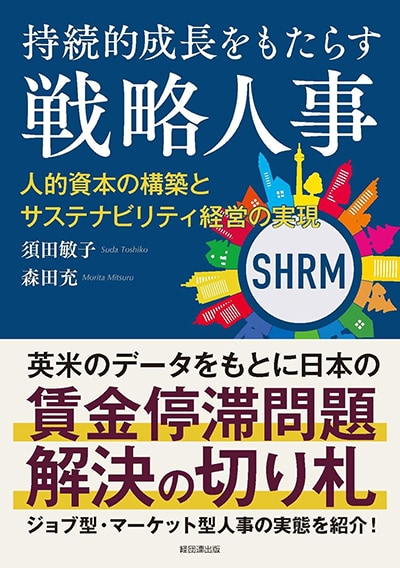
転職が少なく、解雇規制が強いことが、日本の賃金停滞の原因だとされ、その結果、英米のジョブ型またはマーケット型の人事への関心が高まっている。英米のデータをもとにその実態を紹介し、日本の賃金停滞問題の解決策と、企業が持続的に成長するための具体的方策を提示する。
『社長、事業戦略より人材戦略を優先してください!』
岡田烈司・藤崎和彦著 かんき出版 1,760円
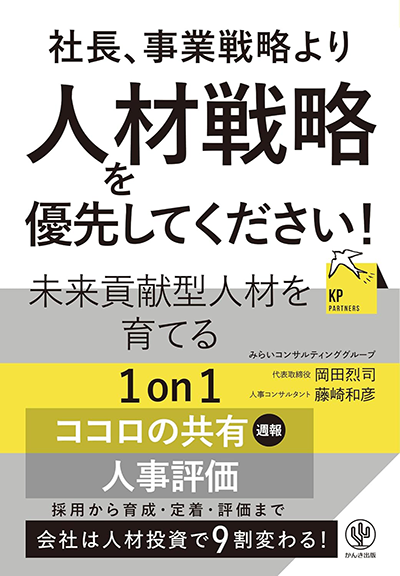
新事業や新製品を生みだす「未来貢献型人材」。中小企業においてその人材を採用・育成し、将来的に会社に貢献してもらうための取り組みや仕組みについて解説した一冊。社員のその能力を開花できるか否かは、会社の仕組みと、社長自身の社員へのコミットメントにある。
[編集] 一般社団法人100年企業戦略研究所
[企画・制作協力]東洋経済新報社ブランドスタジオ