中小企業経営者のための資産運用論
――インフレ時代のリスクヘッジを考える
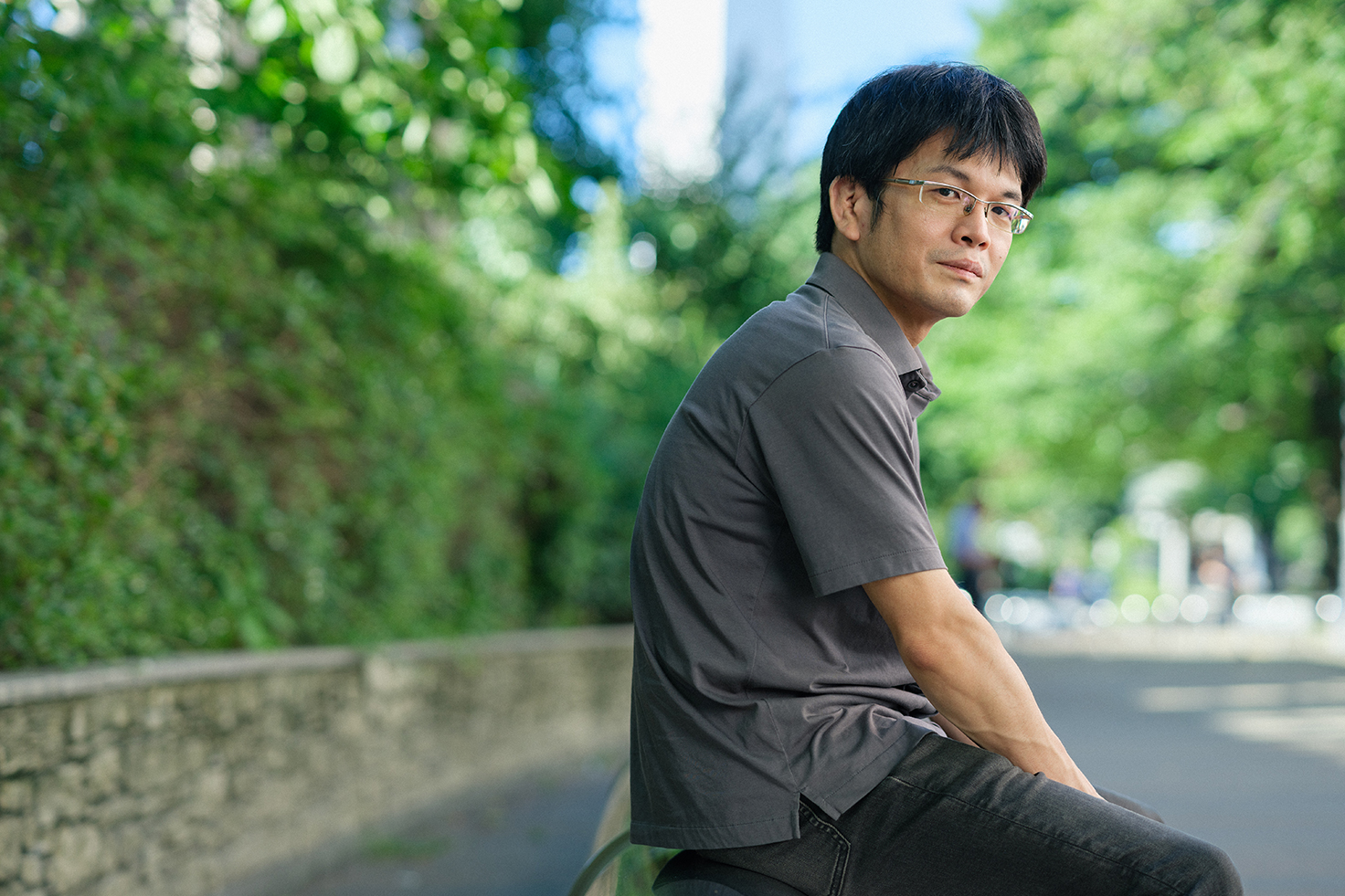
目次
「闘う経済アナリスト」として、テレビ、ラジオ、YouTubeでも活躍中の森永康平氏。独立前は証券会社や運用会社でアナリストやストラテジストとして活動し、独立後は経済アナリストとして活動しつつ、金融教育ベンチャーを立ち上げるなど幅広く活躍しています。最近になってますます激しく動く世界経済と市況のなかで、中小企業経営者が検討すべき資産運用は何か、さらに運用のリスクヘッジについて意見を伺いました。
インフレ期こそ資産運用が「必要」な理由
ひとくちに中小企業経営者といっても、経営状態はさまざまです。なかには上場企業経営者よりも高い報酬を得ている経営者もいれば、自転車操業に陥っている経営者もいます。
そのため、「中小企業経営者にとっての資産運用は?」という質問に対する答えは、「人それぞれです」としか言いようがないのですが、一つ言えるのは、本業が自転車操業になっているほど苦しい状況にある経営者は、資産運用のことを考える前に、ご自身の事業を立て直しましょう、ということです。
また、会社の経営に余裕があり、かつご自身の資産も十分に持っている経営者は、無理して投資をする必要はなく、それこそ「投資がお好きであればご自由に」という程度の話だったのですが、これからはそう言ってはいられない状況になりそうです。
なぜならここ数年は物価が上昇しているからです。
デフレ経済だった頃は、リスクを取ってまで投資をする必要は全くありませんでした。当時は物価が下がり続けていたので、現預金のまま持っていてもお金の価値は目減りせずに済んだのです。
しかし、インフレになると話は別です。物価が上がるということは、相対的にお金の価値が目減りすることを意味します。もちろん、物価上昇分の目減りを許容できる資産状況であれば、何もしないという手もありますが、仮に年3%の物価上昇が10年続けば、この間にお金の価値は30%近く目減りしてしまいます。
それを考えると、資産を大きく増やす必要がなかったとしても、インフレリスクをヘッジできる程度のリターンが期待できる投資は、経営者ご自身の資産保全という観点からも、検討する必要があります。
絶対にやってはいけない投資商品とは?
では、中小企業経営者が心がけるべき投資のあり方とは、どういうものなのでしょうか。
まず、絶対にやってはいけないのが、レバレッジ*1のかかる商品を用いた投資です。FX(外国為替証拠金取引)や各種先物取引、株式の信用取引、暗号資産あたりが、これに該当します。私がこれまで知り合った経営者で投資に失敗し、破産にまで追い込まれた人の大部分は、レバレッジのかかる商品を利用していました。
レバレッジは、当たれば効率的に利益を稼げますが、外れると大きな損失を被ります。マーケットは時々刻々と動きますから、自分の取ったポジションが気になって本業が疎かになるようなら、最初から投資などしないほうがよいでしょう。投資をして本業がダメになってしまっては本末転倒です。レバレッジのかかる商品は、投資ではなく投機であることを理解して、手を出さないことが無難です。
それを前提に、中小企業経営者に適した投資は何かを考えると、最低限、インフレ率程度のリターンを得ることで、資産の目減りを抑える投資です。富裕層はこのような運用をプライベートバンク*2にお願いすることも多いです。1,000万円程度の運用資産では、なかなか引き受けてくれませんが、億円単位の資産を動かせるのであれば、ローリスクで年3%程度のリターンが期待できる商品を、彼らなら提供してくれます。年3%は、日本のインフレ率をやや上回る程度の期待リターンです。
「さすがに億円単位の運用資金はない」という場合は、インデックスファンド*3の積み立てで十分です。「アクティブファンド*4は銘柄選択効果が期待できる」という意見もありますが、コストを考えればインデックスファンドに軍配が上がります。更にインフレヘッジという観点からすれば、インデックスファンドでもリスクが高すぎるでしょう。そこに債券や金を組み合わせることで、リスクを極力抑えながら、年間の期待リターンを3%程度に仕上げる必要があります。債券や金に直接投資するのは難しいかもしれませんので、投資信託やETF*5を活用するとよいでしょう。
ただし、言うまでもありませんが、本業に差し障るような金額での投資はしないことです。
*1 レバレッジ(Leverage)は「てこの原理」という意味で、金融においては借り入れを利用することで、自己資金のリターン(収益)を高める効果が期待できる投資を指す。大きなリターンが狙える反面、リスクも大きくなる。
*2 富裕層向けに資産管理や運用などの金融サービスを提供してくれる金融機関。
*3 市場全体の動きを表す代表的な指数(インデックス)に連動した成果を目指す投資信託。日経平均株価やTOPIX(東証株価指数)などの指数に連動する。
*4 指数(インデックス)を上回る、または指数にとらわれずにリターンの獲得を目指す投資信託。
*5 東京証券取引所などの金融商品取引所に上場している投資信託。Exchange Traded Funds の略。
儲けだけではない、経営者が着目すべき「投資の副産物」
ところで、経済や投資の教科書には「インフレヘッジには株式投資がよい」と書いてあることがありますが、必ずしもそうとは限りません。インフレヘッジ目的で年3%のリターンを狙うにしても、それを株式でやろうとすると、ダウンサイドのリスクがあまりにも大きくなるからです。
現に、昨年8月、今年4月の2回、世界の株式市場は暴落しました。TOPIXで暴落直前の高値から、暴落後の安値までの下落率は、昨年8月が-25.10%、今年4月が-20.50%です。個別銘柄の中には当然、これ以上の下落率を記録した銘柄もたくさんありました。3%のリターンを期待して株式に投資しても、20%超のダウンサイドリスクと背中合わせでは、インフレヘッジを目的としたリスクリターンのバランスに欠ける感があります。
もし、どうしても株式に投資するのであれば、それで儲けようなどと考えるのではなく、経営者ならではとも言える「投資の副産物」に注目すべきです。
株式投資で銘柄を選ぶ際には、決算書を読む必要がありますし、その銘柄が属する産業の動向や、世の中の流行にも敏感になる必要があります。必然的に興味の対象が広がっていき、さまざまな業界のことがわかるようになります。これは経営者にとって、本業に生かせる大事な知識になります。
経営者が株式投資をするのであれば、自分の持っている資産を倍にしようなどと考えず、投資の副産物として、決算書が読めるようになったり、さまざまな業界の幅広い知識が得られれば御の字という程度に構えておくのがよいでしょう。
不動産保有はインフレヘッジに向いている
また、株式と並んでインフレヘッジに有効とされる不動産ですが、価格転嫁という観点からは株式よりもインフレヘッジに向いていると考えることもできるでしょう。
たとえば100円が110円になると、たった10円の値上げでも、10%という値上がり率に換算すると分かるように、負担の重さを実感しますが、1億円の物件が1億1,000万円になったとしても、元の値段が大きいだけに、負担の重さを感じにくい面があります。数字のトリックではありますが、そういう特性があるため、単価が低い商品を扱う飲食業や小売業に比べて不動産は価格転嫁がしやすく、インフレが進んだときも値上がりしやすくなります。
その意味で、インフレ局面において不動産を持つのは合理的ではあるのですが、個別に不動産を保有すると、「負け組物件」をつかまされるリスクがあります。確かに昨今、都心ではタワーマンションの価格高騰が話題ですが、これはあくまでも勝ち組物件です。今後、人口減少が加速度的に進むなか、一部の勝ち組物件は価格が高騰する反面、負け組物件はいつまで経っても値上がりしないという状況になることは必定です。
したがって、数千万円の物件を買うと、ある意味、集中投資になり過ぎる面があるので、REITや区分所有のような小口で投資できるものを複数所有するほうがリスクを低減できるでしょう。
手札を多く持ち、歴史を読み解くことから判断力を養う
資産運用も本業も同じですが、切羽詰まると焦りから間違った選択をしてしまいがち。何事も余裕が必要です。たとえば資金繰りに窮した挙句、残る手段は自分の持ち金を入れるしかないという状況にまで追い詰められたら、身動きが取れなくなりますし、冷静な判断も下せなくなります。
どのような勝負事も、手札を多く持てた人間が勝ちます。したがって、まず金銭的な余裕を持てるように、本業で自分の資産を築くことが大事です。投資はあくまでもサイドビジネス的な位置づけで十分ですが、インフレ時代を前提にすれば、自分の大事な手札を減らさないようにするためにも、インフレリスクをヘッジできる程度の投資は考えておくべきでしょう。
最後に投資のヒントを一つ、申し上げておきます。
投資の勉強をするのに、難しい投資理論やマクロ経済分析の本を読む必要はありません。世の中は振り子のようなもので、片方に大きく触れると、その揺り戻しが必ず生じます。これは政治、国際情勢も同じで、リベラルが強くなり過ぎれば、保守主義が台頭し、グローバリゼーションが進み過ぎれば、反グローバルの動きが生じます。まさにトランプ政権の誕生や、昨今の国内情勢がそれを証明しているのではないでしょうか。
あるいはボーダレス社会を是としてグローバル化が行き過ぎた結果、現在は保護主義的な発想が生じています。
こうしたことは歴史の必然であり、パラダイムの転換点を読むことが、ビジネスや投資では重要です。
そのためには歴史に学ぶことです。何がヒットするのかをゼロから考えるよりも、歴史を学び、世の中の振り子がどちら側に振れようとしているのかを察知する能力を磨いたほうが、ビジネスにしても投資にしても、より現実的な判断が下せるはずです。難しい歴史書を読むのではなく、高校の歴史教科書で十分。そのほうが著者の主張する余計なバイアスがかかりません。歴史の事実を知り、その背後に何があるのかを洞察する力を磨くこと。そうすると、経営も資産運用も意思決定のレベルが上がっていくと私は思っています。
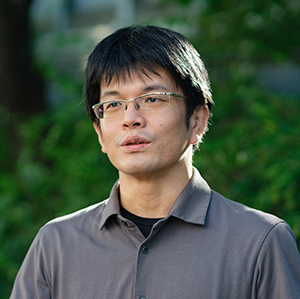
お話を聞いた方
森永 康平 氏(もりなが こうへい)
株式会社マネネ CEO/経済アナリスト
証券会社、運用会社にてアナリストとして株式市場や経済のリサーチ業務に従事。その後、業務範囲は海外に広がり、インドネシア、台湾などアジア各国にて新規事業の立ち上げや法人設立を経験し、事業責任者やCEOを歴任。2018年6月、金融教育ベンチャーのマネネを創業。現在は国内外のベンチャー企業の経営にも参画している。「森永康平のマネネTV」「森永康平のリアル経済学」の2つのYouTube番組を運営。日本証券アナリスト協会検定会員。経済産業省「物価高における流通業のあり方検討会」委員。著書は『スタグフレーションの時代』(宝島社)や父である故・森永卓郎氏との共著『親子ゼニ問答』(KADOKAWA)など多数。
[編集]一般社団法人100年企業戦略研究所
[企画・制作協力]東洋経済新報社ブランドスタジオ












