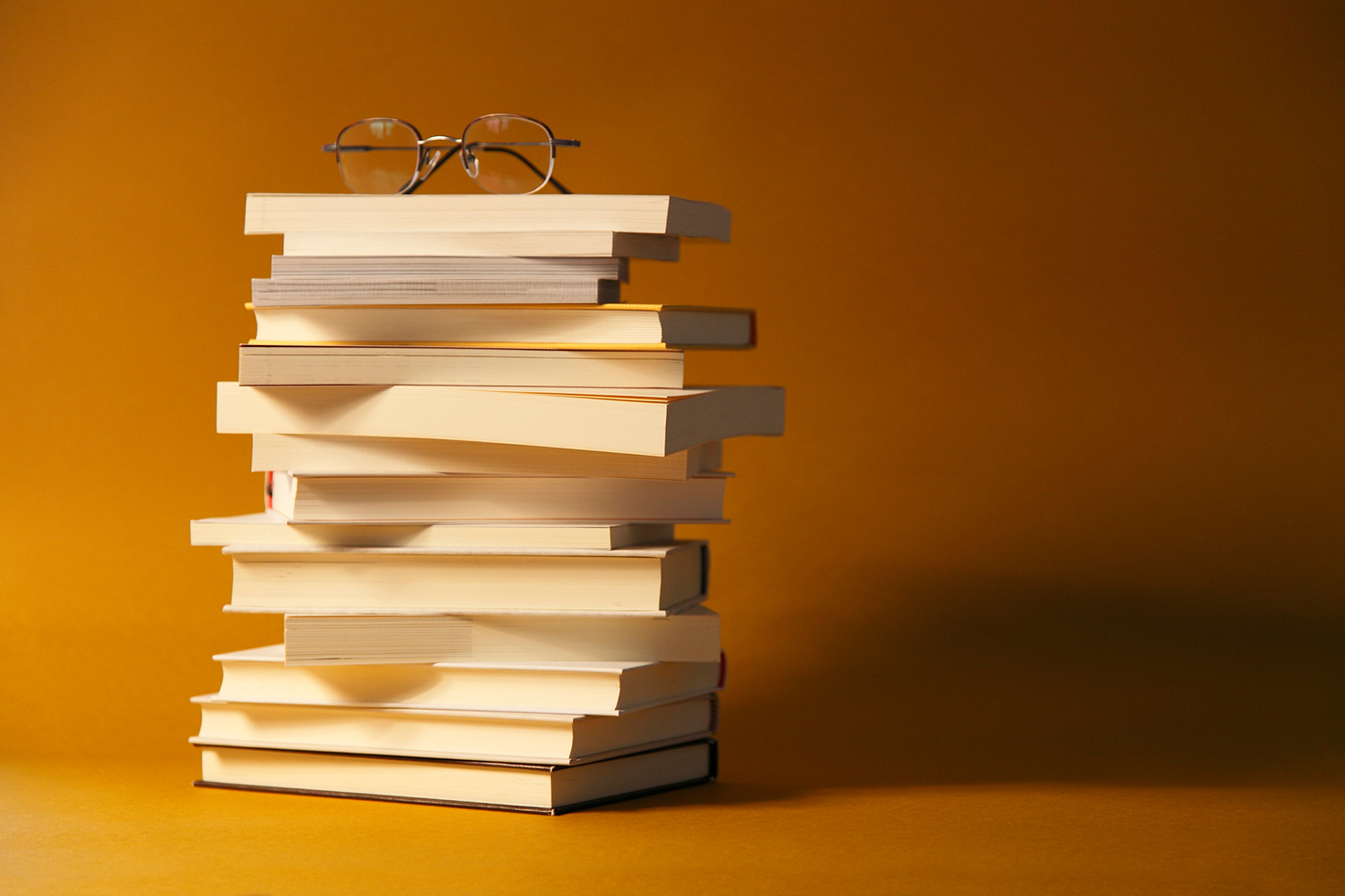経営者にいまおすすめの本6冊 「クレーム対応」編

目次
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客や取引先などからの理不尽なクレームや言動、暴行、脅迫などの迷惑行為を指します。カスハラが社会問題化している昨今、従業員をカスハラから守り、安心して働ける環境を整備することは、経営者にとって急務と言えるでしょう。そこで今回は、クレーム対応の基本から組織づくりまで、カスハラに立ち向かうための知識と対応力を養える厳選6冊を紹介します。
➀『カスハラ対策実務マニュアル』
香川希理編著、島岡真弓・松田優・上田陽太著 日本加除出版 3,190円
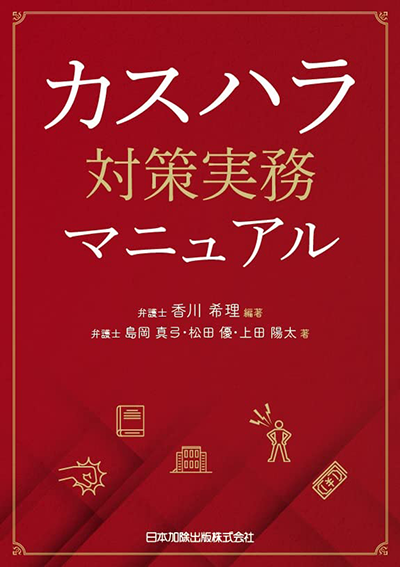
カスハラは「モノ」か「ヒト」かに分類可能
カスハラが深刻な社会問題となっている現状を受け、2022年2月に厚生労働省は「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公表しました。本書はその内容に対応しつつ、実務に必要な知識や業界別のケーススタディなどを網羅的にまとめた1冊です。
第1編では、カスハラが社会問題化した背景や、一般的なクレームとの違い、クレーム対応プロセスの基本について解説します。続く第2編では、電話やメール、面談時などの具体的な状況下における対応のポイントを詳しく説明。また「誠意を見せろ」「土下座をしろ」といった要求や、従業員への処分を求められたときなど、さまざまなパターンの対処法を、事例を交えて紹介します。さらに、多くの経営者や担当者を悩ませる、インターネット上での誹謗中傷や、いわゆる「炎上」したときの対応、法的措置なども取り上げます。
第3編では、厚生労働省のマニュアルを踏まえた企業独自のマニュアル作成の必要性を説き、目次案や作成時のポイントを提示。加えて、相談体制の整備や従業員への配慮、研修など、企業や組織として取り組むべき点を提案します。
第4編では、小売、食品、介護、不動産、マンション管理、建設、金融、システム等開発、冠婚葬祭といった、カスハラが起こりやすい9つの業界のケーススタディを紹介。業界ごとの特徴や慣習にも触れられており、実際の現場での対応がイメージしやすい実践的な内容になっています。該当する業界だけでなく、類似の業界においても参考になるような視点やヒントが得られるでしょう。
例えば小売業界のクレームは、主な原因を「モノ」か「ヒト」かに分類できると著者は分析します。「モノ」が原因であれば返品、交換など対策フローが策定しやすい傾向にあります。しかし、後者は謝罪をしても納得が得られないケースが多く、その場合は対策を打ち切って当該人物を粛々と退店させるといった、毅然とした方針を定めるべきだと著者は説いています。
クレーム対応に詳しい弁護士4名によって書かれた本書は、謝罪文をはじめとする書面の文例や、関連する法令、裁判例なども収録。企業の経営者や法務担当者、現場担当者はもちろん、弁護士や社会保険労務士など、カスハラ対策に取り組むあらゆる人にとって必読書と言えます。
②『カスハラ、悪意クレームなど ハードクレームから従業員・組織を守る本』
津田卓也著 あさ出版 1,650円
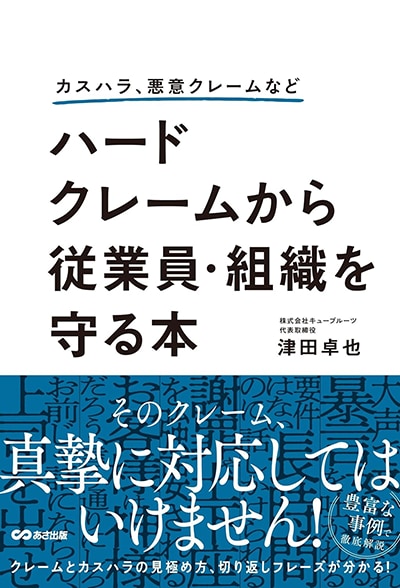
クレーム対応はリスクマネジメントの根幹
「クレームはお客様からの愛」と捉え、真摯に対応してきた組織は多いのではないでしょうか。しかし現在、クレームの性質は多様化、悪質化し、今までのような姿勢では通用しないケースが増えてきました。本書では、要求の内容や手段に合理性のないクレームを「ハードクレーム」と呼び、その対応方法を事例とともに解説します。
第1章では、一般クレームとハードクレームの見極め方を説明します。初めに重要なのは、寄せられたクレームが「正当な要求」なのか、それとも「不当な要求」なのかを判断することです。
そのためには、まず組織として、企業が求めるお客様である「顧客」と、商品やサービスを利用してほしくない「非顧客」を定義しておく必要があります。この「非顧客」に過剰な時間を費やさないことで業務効率が上がり、従業員にとって働きやすい環境を作ることができます。
第2章では、ハードクレームに対して現場スタッフがどのように行動すべきかを解説します。まずクレーム対応の心構えとして、①自分を守ること、②スタッフを孤立させないこと、③組織の方針・ルールに沿って行動すること、の3点を挙げます。そして、ハードクレーム対応のプロセスを①相手の話を聞き出す、②謝罪は部分的にする、③毅然として断る、④現場で連携して解決にあたる、という流れに分け、事例やテクニックとともに詳説していきます。
第3章は、実際に発生するハードクレームの事例と、適切な対応方法やNG対応を紹介。さまざまなシーンでの対応におけるポイントと、具体的な「切り返しフレーズ」が提示されており、自身に置き換えてイメージしながら読み進めることができます。
第4章では、クレーム対応を現場スタッフだけに任せることへのリスクを指摘。クレーム対策は組織のリスクマネジメントの根幹であるとし、①ハードクレームの定義と対応方針を決めること、②具体的な手順までマニュアル化すること、③バックアップ体制を整えること、の3点を徹底すべきであると提言します。
第5章では、ハードクレームに悪質な言動が伴うカスハラについて取り上げ、その最新動向や従業員を守るために必要な対策について言及。巻末にはハードクレームの対応手順や法的知識、クレーム報告書のフォーマット例などが収録されています。
➂『役所窓口で1日200件を解決! 指導企業1000社のすごいコンサルタントが教えている クレーム対応 最強の話しかた』
山下由美著 ダイヤモンド社 1,540円
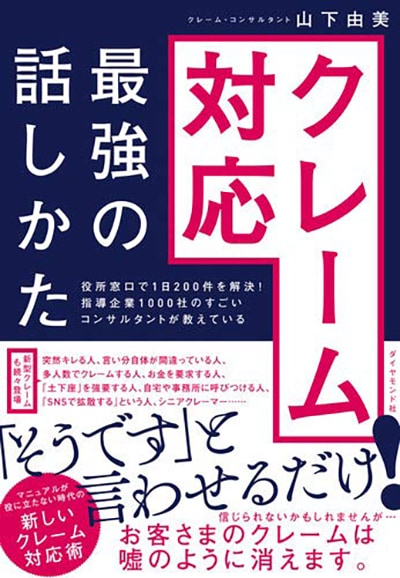
クレーム対応の初動が「言い訳」や「正論」だとこじれる
本書は、クレーム・コンサルタントである山下由美氏が提唱する新たなクレーム対応術「超共感法」を紹介するものです。このメソッドは多くの企業で導入され、さまざまな現場で効果が実証されていると山下氏は述べます。
多くの人は、クレーム対応の初動を「言い訳」や「正しい説明」から始めてしまいがちです。しかし、それはクレームをこじらせる原因になりかねないと指摘します。というのも、クレームを言う顧客の大半は「自分の困りごとを迅速に解決してほしい」と思っているのであり、言い訳や正論を聞きたいわけではないからです。とくに否定的な感情を持つ顧客はなおさらです。
超共感法とは、顧客にまず「そうなんです」(YES)と言わせることで状況を打開する、というシンプルな手法です。一般的なクレーム対応では、まず「傾聴」をすることが推奨されますが、超共感法では傾聴はせず、顧客に「そうなんです」と言わせることだけに集中します。その後、できるだけ顧客の望む答えを提示します。このステップで顧客の怒りを鎮め、問題解決をスムーズに進めるというのが山下氏の考えです。
では、実際にどうやって顧客から「そうなんです」という言葉を引き出すのか。そこで本書の後半では、心理学の原理や、著者の経験と知見に基づいた「そうなんです」を言わせるコツと、顧客タイプ別の対応方法が解説されています。
例えば怒鳴る顧客に対しては、ファーストアクションで同じくらいのトーンで謝罪することで相手をたじろがせ、その隙に冷静な対話へと移行させる手法が紹介されています。ほかにも、理詰めで迫る顧客や、見当違いなことを言う顧客、高齢者による長時間のクレームなど、よくあるパターンを例に挙げ、実践的かつ画期的な対応策を提示します。
人は「そうなんです」とうなずくとき、「共感してもらえた」という感情が生まれます。このことで敵対的な関係が解消され、クレーム対応がスムーズに進むだけでなく、最終的には怒っていたはずの顧客と信頼関係を築くことができると山下氏は主張します。
④『小さな会社・お店が知っておきたい SNSの上手な運用ルールとクレーム対応』
田村憲孝著 同文舘出版 1,980円
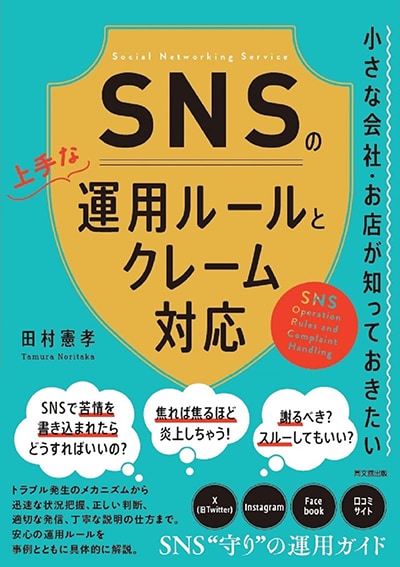
SNS運用のコンサルタントである著者が、主要SNSの特徴からトラブル発生のメカニズム、トラブル時の正しい対応や防止策などを解説。SNS運用で知っておくべき基礎知識が、具体的事例とともに網羅されている。
➄『社長、クレーマーから「誠意を見せろ」と電話がきています 「条文ゼロ」でわかるクレーマー対策』
島田直行著 プレジデント社 1,650円
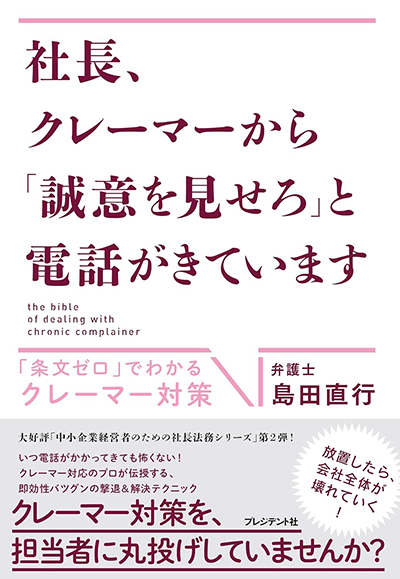
クレーム対応は担当者のスキルアップだけでは不十分であり、経営者がクレーマーに対する戦略を立案し、組織全体の力を上げることが不可欠である。そう考える著者が、中小企業の経営者が押さえておくべきクレーム対策の基本の型を解説する。
⑥『カスハラの犯罪心理学』
桐生正幸著 集英社インターナショナル 979円
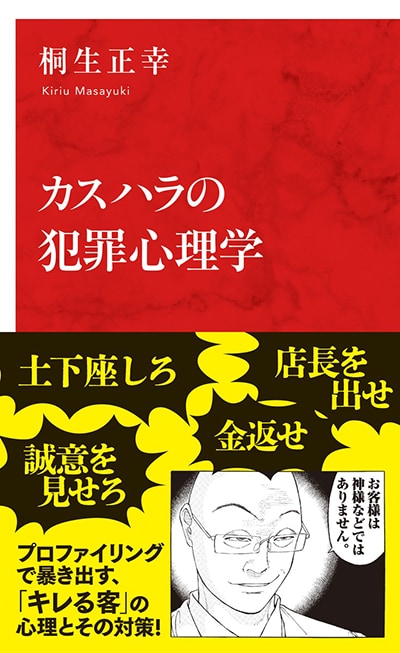
犯罪心理学の観点からカスハラを研究してきた著者が、なぜカスハラが起こるのか、加害者の心理や社会構造を分析し、カスハラ防止のための対策を提言する。実際に起きた刑事事件や、深刻化したカスハラの実例を多数収録。
[編集] 一般社団法人100年企業戦略研究所
[企画・制作協力]東洋経済新報社ブランドスタジオ