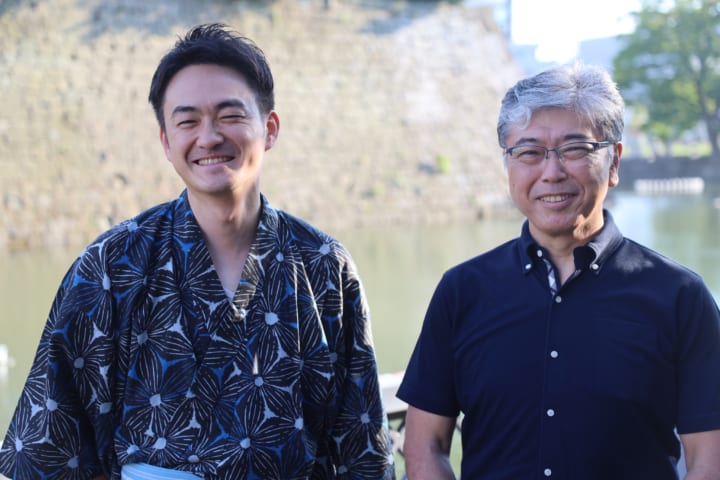組織文化は企業の強力な武器になる ~迫る大転職時代における人材確保の秘策~

目次
独自の企業風土や文化はあっても、それが明確な組織文化にまで至っていない日本企業は少なくありません。しかし組織文化の希薄さは日本企業の弱みであり、深刻な問題をはらんでいます。なぜ組織文化が必要なのか、組織文化を戦略的につくりあげていくためにはいったい何が必要なのか。経営戦略やグローバル経営を専門に研究を続けている経営学者の入山章栄教授にお聞きしました。
よい組織文化がなければ人が取れない
皆さん、「うちの会社は風通しがいいのです。これが弊社独自の組織文化です。」と思ってはいませんか。しかしこれは組織文化ではありません。組織文化とは戦略的につくるものです。気がつけばなんとなくできていた、または自然に醸成されていたなど、こういったものは組織文化とは呼べません。
今、ミッション、ビジョン、バリューを掲げようとする企業は増えています。しかし、多くの企業では組織文化がありません。
では、組織文化とは何でしょうか。それは、会社の存在意義や目指している未来、会社が提供している価値そのものを指します。ミッションやビジョンが未来に向けてのアクションを示す「動詞」だとすれば、組織文化は「こうありたい」という状態を表す「形容詞」に例えられます。企業には「動詞」も重要ですが、「明るい」「前向き」などの「形容詞」が必要です。
例えば、「失敗をちゃんと受け止め、失敗を許容できる」という組織文化があればこそ、失敗をしても何度もチャレンジを続けられるというものです。イノベーションはそうしたチャレンジの連続から生まれます。イノベーションが生まれにくい現在の状況は、日本企業の弱点といってもいいでしょう。
日本企業は失敗をするとすぐにやめてしまいます。失敗が許されなければイノベーションなど生まれようがありません。チャレンジの多くは失敗に終わるのが当たり前なのです。その先へ行くためには、従業員全員が自社の描く未来像に対して「腹落ち」していなければなりません。そして、その未来に進むためにも、それを支える組織文化が不可欠なのです。
これからの時代、優秀な従業員を獲得し、採用した従業員に働き続けてもらうには、特に戦略的な組織文化づくりが必須だと考えてください。若い世代ほど組織文化を重視しています。お金ではなく、「この会社で働きたい」と思える組織文化が、選ぶ決め手になるのです。少子高齢化と人手不足が進んでいる日本も、まもなくアメリカ同様に大転職時代を迎えるでしょう。副業活動が増えている中で、コロナが収束すれば転職に踏み切る人も間違いなく増えていくはずです。そうなると会社へのエンゲージメントは下がっていくでしょう。
その状況下で物を言うのが組織文化です。雇用が流動化していく中で、よい組織文化がなければ人が採れない、人が逃げ出してしまうと覚悟してください。
明文化してこその組織文化
では、組織文化はどのようにつくればよいのでしょうか。それには明文化することが必須です。絶対に「これだけは守る」「何があっても死守する」といった内容を文章としてまとめるのです。
代表的な例として、動画配信サービスのNetflixをあげましょう。この会社は組織文化を最重要課題と考え、「カルチャーデック(Culture Deck)」として集約しています。少しやりすぎと思えるところもありますが(笑)、議論を尽くして練り上げています。
日本の会社では、IoTプラットフォームを提供しているグローバルベンチャーの株式会社ソラコム(SORACOM)も好例です。「自分たちはどう行動すべきか」、という行動指針をはっきりと明文化しています。ベンチャー企業は往々にして戦略的に組織文化をつくっていますが、それは組織文化が明確であれば従業員の獲得につながり、投資家にもアピールできるからです。
もっとも、現代の伝統的な日本企業は言語化されていないものを言語に変換する、いわゆる暗黙知から形式知への変換はあまり得意ではありません。経営学者の野中郁次郎氏が提唱した「SECI(セキ)モデル」でいうところの「表出化(Externalization)」ですね。
日本人は同質性が高く、空気を読むコミュニケーションをしています。しかし組織文化に関していえば、「話さなくともわかる」はアウト。ふわっとした言葉ではなく、「うちの会社は何をしたい会社なのか」「存在意義は何か」を明確に表現していくことが重要です。
この作業は一足飛びにはできません。たとえば、身体が冷えている人に対症療法的に薬を出しても根本的な解決にはなりません。一時的に治っても、また元に戻ってしまうからです。ここで大事なのは、身体が冷えにくい体質づくりを行うことでしょう。
組織文化もこれとまったく同じです。西洋医学ではなく、東洋医学のような根本的な改善方法を考える力が必要なのです。
30年先を見つめよう
よい組織文化を醸成するには、私は大企業よりも、実は中小企業や老舗企業が向いていると思います。
行動指針を明確にし、組織文化をつくっていくには経営者の「行動」と「感情」の両方が必要です。大企業では経営者の「感情」は遠くの従業員には届きません。だから、大企業は組織文化を浸透させることが難しく、時間もかなりかかります。
一方、中小企業はどうでしょうか。サイズが小さいので、社長の「行動」と「感情」から組織文化や行動指針がすぐに社員に浸透します。社長が行動を変えれば、役員、部長、課長、一般の社員へと伝わっていく。つまり影響が連鎖しやすいのです。会社の組織文化醸成の起点となるのは社長の行動、といっても過言ではありません。だからこそ、社長が変わらなければ組織文化をつくることは難しいともいえます。
加えて、ファミリービジネスの多い中小企業や老舗企業が組織文化の醸成に向いている点として、長期的な視野で経営を考えられることもあげられます。組織文化をつくるには最低でも10年、長ければ30年以上の時間軸が必要ですが、上場している大企業は短期思考になりがちでなかなかそうはいきません。30年先の未来を見据えることができるのは中小企業や老舗企業ならではの利点でしょう。
では、30年先を見つめるためには何をすればいいのか。ポイントは3つあります。1つ目はいろいろな人と会って、想像力を働かせること。そしてさまざまな情報を受け取ること。会議室に閉じこもっていては長期的な視点は生まれません。
2つ目には、20年、30年経っても変わらないものにフォーカスすること。たとえば、日本の人口は減り続け、2115年には約5,000万人にまで減少します。人口減少は30年先でもおそらく解決できない日本の問題です。貧困問題も同様でしょう。30年先でも日本が抱えているであろう課題に着目し、そこにどのように貢献して、会社として価値を提供していくのか。それを考えていくのです。
3つ目が、「SECIモデル」でいう「表出化」を図ること。つまり会社の未来・ビジョンや、ありたい組織文化を暗黙知ではなく、形式知にすることです。最近では「表出化」の一環として、暗黙知を映像で形式知する取り組みも増えています。暗黙知を暗黙知のままにせず、言語、映像などさまざまな方法を検討して、形式知に変換し、表出化を試みましょう。
このように組織文化を戦略的につくり、よい人材を採用してよいコミュニティをつくる。この一連の営みが企業に変革をもたらし、未来に向けてのイノベーションにつながります。

お話を聞いた方
入山 章栄氏
早稲田大学 大学院経営管理研究科 教授
慶應義塾大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了。三菱総合研究所を経て2008年に米ピッツバーグ大学経営大学院よりPh.D.を取得。同年より米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授。19年4月より現職。『Strategic Management Journal』『Journal of International Business Studies』など国際的な主要経営学術誌に論文を発表している。著書に『世界の経営学者はいま何を考えているのか』(英治出版)、『ビジネススクールでは学べない 世界最先端の経営学』(日経BP)、『世界標準の経営理論』(ダイヤモンド社)ほか。
[編集]株式会社ボルテックス100年企業戦略研究所
[企画・制作協力]東洋経済新報社ブランドスタジオ