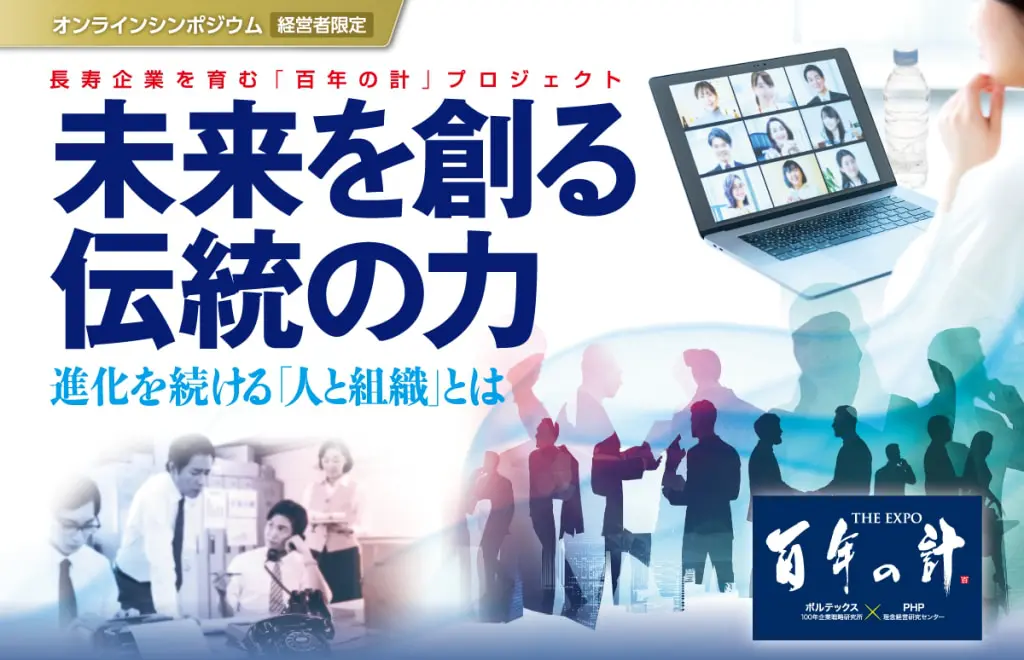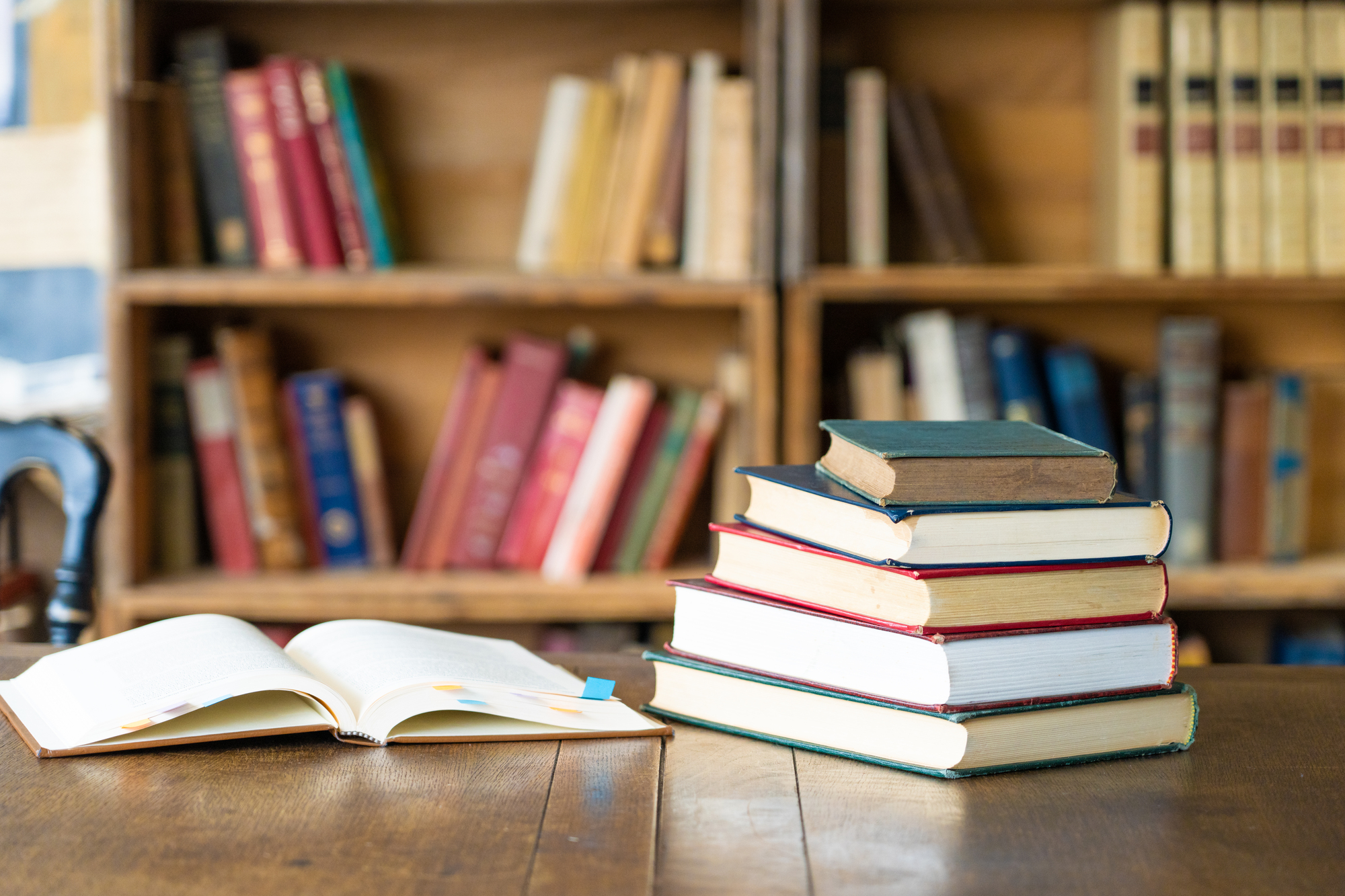三方よしの現代ビジネスへの影響と成功事例

目次
記事公開日:2021/07/21 最終更新日:2025/03/01
「三方よし」とは、「売り手よし、買い手よし、世間よし」の三つの利益を同時に追求するビジネス哲学です。この概念は、江戸時代から続く日本の商人である近江商人によって培われました。100年以上続く長寿企業には、近江商人にルーツがあり、その経営哲学「三方よし」を大切にしている事例があります。企業存続と社会・地域への貢献との関係、現在ビジネスのESG・SDGsにも通じる「三方よし」とは?近江商人の「三方よし」の普遍性を解説します。
三方よしとは? その歴史と背景を理解する
「三方よし」は、大阪商人、伊勢商人と並び称される日本三大商人の一角・近江商人の経営哲学を表した言葉で、「三方」とは、売り手・買い手・世間を指します。「売り手よし、買い手よし、世間よし」の三つの利益を同時に追求し、満たす商売こそ、理想であるという意味が込められています。
「三方よし」を経営哲学とする近江商人とは?
近江とは、琵琶湖(淡水の海=湖、淡海(あわうみ))がある現在の滋賀県の旧国名です。京都や大阪に近いことから交通の要衝として古くから栄えました。一般的に近江商人と呼ぶ場合は、拠点が近江にあるだけでなく、他国(近江国以外の日本各地)へ行商した商人をさします。江戸時代から明治時代にかけて全国へ出向き活躍しました。
なぜ近江商人が「三方よし」の代名詞なのか
日本には、「三方よし」に代表される商業道徳が古くから根付いていたと考える向きもありますが、日本の商い全体が他国に先行して三方よしを実践していたわけではありません。渋沢栄一は、1867年に徳川慶喜の弟・昭武に随行してパリ万博に参加した際、イギリス人から「日本の商人は自分の利益ばかり追求するので、まともな商売ができない」と苦言を呈されてショックを受け、『論語と算盤』を提唱するに至ったといわれています。
一方で近江商人は、商売を通じて地域社会全体に貢献することを目指し、長期的な信頼関係を築くことの重要性を説いていました。江戸時代から全国各地で行商したり定住したりするなかで、「よそもの」が遠地で受け入れられるには、その地域での信用や貢献が必要であることを学び、実践したのです。その結果、近江商人のビジネスは単なる利益追求に留まらず、地域社会の発展や安定にも寄与しました。
近江商人の歴史を辿ると、彼らが如何にして地域文化や伝統を尊重し、これをビジネスに活かしてきたかが分かります。近江商人の商人道は、商売を通じて地域社会に恩返しするという理念のもとに成り立っています。近江商人は利益追求や単なる経済活動にとどまらず、地域社会や取引相手の満足度を重視し、地域社会の発展にも大きく貢献しました。このようなビジネスモデルは、現代の経営環境においても非常に重要であり、企業が持続可能な成長を遂げるための礎となっています。
さらに、近江商人は、商売を通じて地域社会の文化や伝統を尊重することに努め、これが長期的な信頼関係の構築に繋がりました。このような価値観は、現代のグローバルな市場においても通用する普遍的なビジネス哲学として注目されています。近江商人の地域社会での活動は、単なる商取引を超えて、文化的、経済的な発展にも寄与しており、これが成功の秘訣であると言えます。 また、近江商人の考えには商売と哲学の融合を説いた石田梅岩の石門心学も影響しているといわれます。哲学に重きをおいて各地に貢献した近江商人の事例が多数残っています。
このようにして近江商人は「三方よし」の代名詞となったのです。なお、近江商人誕生の地、滋賀県は100年企業の輩出率で上位に位置しています。
石門心学とは?石田梅岩の教えを継ぐ超長寿企業の事例
滋賀県は100年企業輩出率が高い
なぜ三方よしは現代ビジネスで重要なのか?
今日のビジネス環境では、企業の社会的責任(CSR)や持続可能性が求められています。「三方よし」の「世間よし」は、これらの価値観と一致しており、企業が長期にわたって成功するための不可欠な視点となっています。企業は利益を追求するだけでなく、社会全体に対しても貢献することが求められています。「世間よし」の考え方は、「買い手」である顧客や地域社会との関係をより良くし、企業のブランド価値を高めることにつながります。また、企業が「三方よし」を実践することで、「売り手」である従業員のモチベーションが向上し、結果として企業全体の生産性が高まることも期待できます。
このように、「三方よし」は企業の内部と外部の両方でポジティブな影響をもたらし、持続可能なビジネス運営を可能にします。現代のビジネスにおいては、ステークホルダーとの信頼関係を築くことが成功の鍵となっており、「三方よし」の理念はその礎となっています。
グローバルビジネスにおける「三方よし」の実践とその効果
グローバル化が進む現代では、企業が複数の文化や価値観の中でビジネスを展開する必要があります。このような環境で成功するためには、「三方よし」の哲学が大いに役立ちます。
サプライチェーン全体で環境保護に取り組み、社会と調和した成長を実現し、拠点がある地域経済の活性化、商品を通じて世界中の顧客に幸せをもたらすことができます。 「三方よし」は、CSRやSDGsといった現代の経営課題とも一致し、企業が持続可能な成長を遂げるための指針となります。この哲学を実践することで、企業は信頼と共感を得ながら、地域や社会全体により良い影響を与えることができるのです。
多文化社会でのビジネス成功に「三方よし」の柔軟性を活かす
多文化社会では、顧客のニーズや期待が多様化しています。「三方よし」の考え方を取り入れることで、企業は各地域や文化の特性を尊重しながら、持続可能な成長を実現することができます。さらに、地域社会との良好な関係を築くことで、企業は現地での信頼を獲得し、長期的な成功を収めることができます。
三方よしや近江商人にルーツがあり実践する企業と成功事例
「三方よし」や近江商人にルーツのある企業が、日本の各地で長寿企業となり、いまも優れた経営を続けています。伊藤忠商事、西川株式会社、たねやグループは、「三方よし」の哲学を実践することで、利益だけでなく、地域社会にも貢献しています。この成功は、他の企業にとってもモデルケースとなり得るでしょう。さらに、これらの企業はそのビジネス活動を通じて、地域と深いつながりを築き、地域社会のニーズに応えることで、長期的な信頼関係を構築してきました。これにより、彼らは単なる商業的成功を超えて、地域の発展や社会的課題の解決に寄与しています。
伊藤忠商事
国内を代表する総合商社の1つ、伊藤忠商事の創業者で近江商人だった伊藤忠兵衛氏も、「三方よし」の理念を大切にしていました。同氏は「商売道は、売り買いのいずれにも益があり、さらに世の不足をうずめ、御仏の心に叶うものであってこそ尊い」という趣旨の言葉を遺しています。伊藤忠商事は、2020年4月から「三方よし」を経営理念に掲げ、創業の精神を受け継いでいくことを改めて表明しました。
西川株式会社
寝具の老舗ブランドである西川株式会社は、初代仁右衛門(にえもん)氏が近江地方で始めた布織物や蚊帳の行商が祖業です。
社是は
「誠実」「親切」「共栄」。
「共栄」の実現は人間性の尊重を基本とした人間関係の中で、「誠実」「親切」を通してのみ実現できるとしています。
「三方よし」の精神を引き継ぐ老舗、西川株式会社のコラム
15代目当主、西川八一行氏登壇イベントのレポート
たねやグループ
たねやグループは、滋賀県近江八幡市に本社がある菓子の老舗です。相手が喜ぶことをすれば数字はあとからついてくるという意味の「先義後利」に象徴される商いの哲学を掲げ、市場が縮小傾向にある和菓子産業にあって、「現代の近江商人」として成長を続けています。
経営理念(パーパス)は
「地元への貢献」
地域や社会に貢献し、環境を保護し、持続可能な発展のあり方を考える経営を実施しています。
たねやグループが登場するおすすめコラム・書籍を紹介
100年企業が示す三方よしの力
資生堂、ミツカン、任天堂は、「三方よし」の哲学を実践することで、100年以上もの間、企業の信頼とブランド価値を維持してきました。さらに、これらの企業は、革新的な製品やサービスを通じて世界中の顧客に感動を提供し、持続可能なビジネスモデルを構築しています。これにより、彼らは地域社会と共に成長し続けることができ、次の世代へと持続可能な未来を繋げています。これらの企業の成功事例は、「三方よし」がどのようにして長期的な企業の繁栄と社会的貢献を両立させるかを示しています。
資生堂 ~サステナビリティ促進を目指す
1872年に創業し、信頼の化粧品メーカーとして定評のある資生堂は、スキンケアブランド「エリクシール」のつめかえ用パッケージ紹介活動を通じ、プラスチックごみの削減を目指す「グローバルサステナビリティキャンペーン」を、2021年4月にスタートさせています。
高い認知率と好感度を誇る「ドラえもん」をキャンペーンキャラクターに迎え、TVCMも放映。今後は日本のみならず、アジアの国・地域全体にキャンペーンを拡大していく予定だそうです。
「エリクシール」の化粧水・乳液つめかえ用パッケージは、約10年前から発売されており、同社のサステナビリティ活動の柱となっています。資生堂は環境負荷低減に向けた取り組みを加速し、2023年には年間約400トンのプラスチック使用量削減を目指すほか、2025年までに、プラスチック製容器包装について100%のサステナブルを目指し、環境への影響を最小限に抑えるとしています。
ミツカン ~長い歴史の中で培った「水」についての啓発活動
1804年創業と、国内の酒造業の中でも長い歴史を持っているのが、ミツカン。同社は良質な醸造酢を作るために私設水道を敷設し、廻船で尾張半田から江戸、大阪まで食酢を運ぶなど、水と深く関わってきた歴史があります。そして1999年、東京都中央区に「水の文化センター」を設立。「水」をテーマとした社会貢献活動を開始するに至りました。
同センターでは水に関する企画展や専門家と連携したイベントなどの開催や機関誌・書籍の発行を行い、「人間の生活には欠かせない、水の大切さ」を啓発しています。
任天堂 ~多様な人材の働きやすさを整備する
任天堂も1889年創業と長い歴史を持つ企業であり、同社が築いたネットワークは世界中に広がっています。このため同社は2018年9月に、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」を参考に「任天堂人権方針」を制定しました。一部を抜粋すると、「人種や宗教、出身や社会的身分、性別や年齢、性的指向や障害の有無などによる差別、または差別につながる言動をしない」などの行動規範が掲げられています。
また2019年9月には、すべての事業所を対象に「日々の出退勤時間を各自でコントロールできる制度」や「勤務間インターバル制度」を導入。さらに女性の活躍推進や高齢者の安定雇用にも、積極的に取り組んでいます。こうした任天堂の姿勢からは「人材を大切にすることで、社会に貢献する」というメッセージが伝わってきます。
三方よしとCSR、CSV、SDGs、ESGの関連性
「三方よし」には、現在の企業活動に欠かせないCSR、CSV、SDGs、ESGに通じる精神があります。ここ数年は、より包括的な概念であるSDGs・ESGを掲げる企業が多くなっていますが、まず、それぞれの言葉の意味を整理し、違いや関連性をみてみましょう。
CSR(Corporate Social Responsibility)とは
「企業の社会的責任」を意味する言葉です。企業が社会の中で業務を営む以上、顧客や従業員、株主や投資家といったステークホルダーはもちろん、法律や道徳、そして環境配慮など幅広い対象に対し、適切な意思決定を行う責任があることを意味しています。
CSV(Creating Shared Value)とは
「共有価値の創造」を意味する言葉です。自社の強みを用い、社会的課題の解決を目指す考え方を指しています。社会貢献と自社の収益を結び付けた事業や起業も、この言葉の中に含まれます。アメリカの経営学者、マイケル・ポーター氏によって提唱されました。
SDGs(Sustainable Development Goals)とは
2015年に国連総会で採択された、「持続可能な開発目標」の略称です。2030年までに達成すべき17の目標が設定され、持続可能な開発に関する包括的なアジェンダとして世界中で採用されています。
SDGsは、政府、国際機関、民間企業、市民社会などが協力して、貧困や格差、気候変動などの世界的な課題に取り組み、持続可能な開発を促進することを目指しています。
ESG(Environmental, Social, and Governance)とは
企業や投資家が取り組むべき重要な要素、「環境、社会、ガバナンス(企業統治)」の頭文字をとったものです。「環境」は、温室効果ガスの排出削減や再生可能エネルギーの利用など、企業活動において持続可能性を考慮すること、「社会」は、働き方や多様性、人権に配慮したサプライチェーンの確立など、人権や労働問題への取り組み、「ガバナンス(企業統治)」は、企業の行動規範やステークホルダーの権利保護など、企業の透明性やコンプライアンスを重視した責任ある経営を指します。
CSR、CSV、SDGs、ESGとは? それぞれの違いと共通点
CSRは企業の社会的責任を果たすための取り組みであり、CSVは企業と社会の両者に価値を生み出すことを目指します。SDGsは国際的な持続可能な開発目標を示し、ESGは環境、社会、ガバナンスの観点からの投資基準です。これらは全て「三方よし」の理念と深く結びついています。これらのコンセプトは、企業が社会に対してどのような貢献を果たすべきかを示しており、企業の長期的な成長と成功に不可欠な要素と言えます。さらに、企業がこれらの価値観を取り入れることで、ステークホルダーとの信頼関係が強化され、企業の持続可能性が向上します。これにより、企業は社会的責任を果たしつつ、利益を上げることが可能となり、長期的な企業の成長を支えることができます.
三方よしが示すビジネスの普遍性と持続可能性
「三方よし」は、単なるビジネス戦略ではなく、企業が持続可能な成長を遂げるための普遍的な哲学です。これにより、企業は利益を追求するだけでなく、社会全体に貢献することが求められます。この哲学は、企業が社会との信頼関係を築き、長期的なパートナーシップを築くための基盤となります。
さらに、「三方よし」は企業が地域社会と共に成長し、共生することを可能にします。これにより、企業は地元のコミュニティと強固な絆を築き、地域の発展に寄与することができるのです。この理念は、企業が単なる利益追求に留まらず、社会との調和を図ることで持続可能な成長を遂げるための指針となります。
まとめ ~企業の存続には「三方よし」の視点が不可欠
パナソニックの創業者である松下幸之助氏は、『企業は人、土地、資源といった社会からの借りもの・預かりものでできており、また、企業の役割は、社会の足らざるところを補い、これを潤沢に作りだすことで、世の貧困を失わせるものでなければならない』とし、「企業は社会の公器」であると表現しました。
また、京セラを世界的企業に成長させJALの経営再建も手がけた稲森和夫氏は、実践を通して得た経営哲学をフィロソフィとして掲げ、そのベースとなる考え方のひとつに「利他の心を判断基準にする」ことをあげています。
日本の長寿企業やファミリービジネス研究の第一人者である後藤俊夫氏によると、こうした思想のルーツをたどると、渋沢栄一、そして石田梅岩にさかのぼり、「三方よし」や「企業は社会の公器」とする経営思想が企業の長寿要因になっているといいます。
日本における長寿企業研究の第一人者、後藤俊夫氏のコラム
「三方よし」の視点で社会と地域に貢献する意味
企業が長期的に存続するためには、「三方よし」の視点で社会や地域に貢献することが不可欠です。この哲学を実践することで、企業は信頼と共感を集め、持続可能な成長を実現します。「三方よし」の理念を取り入れることで、企業は単なる利益追求にとどまらず、社会全体に貢献し、地域社会との調和を図ることが可能です。これにより、企業は地域社会との共生を果たし、長期的な繁栄を築くことができます。
さらに、「三方よし」は企業が社会の一員としての責任を果たし、未来に向けた持続可能なビジョンを描くための道標となります。企業がこの理念を実践することで、次世代にわたる信頼と成長の基盤を築くことができるのです。このように、「三方よし」は企業が社会における役割を再確認し、持続可能な未来を創造するための重要な要素として認識されています。
100年以上の歴史を持つ長寿の大企業の事例を見ていると、社会や地域への貢献活動には様々なかたちがあることが分かります。中小企業が同規模の試みを実践するのは、なかなか難しいかも知れません。しかし自社の規模や事業体系、独自性などを鑑みて応用するための、ヒントが隠されているのではないでしょうか。
これからの社会で事業を継続していくためには、自社と顧客だけでなく、社会や地域への貢献が欠かせません。企業の事例も参考に、改めて自社の存在意義に思いを巡らし、「三方よし」の経営を追求していきましょう。