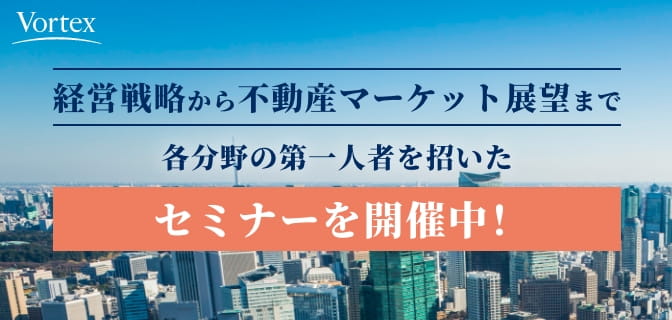不動産市場展望~ポストコロナ時代のオフィス市場

目次
新型コロナウイルスは、生産活動や消費活動に甚大な影響をもたらしました。内閣官房が公表している「人の動き」と「地域別の消費額」の変化を見てみると、2020年の最初の緊急事態宣言が出たあとは、日本においては月の消費額が前年同月比で50%以下になった地域が目立ちます。とりわけ影響が大きかったのが、3大都市圏でした。また、消費だけでなく、オフィスの利用についても変化が見られました。リモートワーク(在宅勤務)や時差出勤を多数の企業が導入し、出勤が大きく制限されました。2020年を振り返ると、出社率は従来のおおよそ4割程度であったことが分かってきています。「今後もこれは定着していくのか?」という視点が、オフィス市場の未来を占ううえで極めて重要になってきます。
未来を占ううえでは、原理原則から整理していかないといけません。経済学の基礎理論に立ち戻れば、企業は、生産要素市場から労働力を投下して、商品やサービスを生産し、販売しています。オフィスは、平均的には9時から18時まで、生産や販売活動の拠点として活用されていました。労働力を投下して、財やサービスを生産する以上、オフィスビルは必要不可欠です。その利用する時間帯が短縮化などによって変化するからといって、需要が減ることはありません。
しかし、新型コロナウイルスの影響によりオフィス稼働率が低下することは明らかです。稼働率が下がると、空室率ではなく、オフィス賃料単価に影響を与えることになります。ですが、ここに空間要素を入れて考えなければなりません。たとえば、東京の市場を見ると、2021年に入り都心部においても空室率が上昇し始めています。しかし、出ていく企業だけでなく、この機会に床を増やしている地域やビルがあります。少し離れたところに分散してオフィスを借りていた企業が集約化を進めているのです。その意味で、出ていく企業もあれば、特定の地域やビルでは床を増やしている企業もあります。今後は、このような集約化が一層活発化していくものと考えられます。そうすると、オフィス市場の中でも企業の勝ち負けが明確になってきます。どこに集約化が進むのか、勝ち組がどこであるのか、これから慎重に市場を観察していくことが求められています。

著者
清水 千弘
一橋大学教授・麗澤大学国際総合研究機構副機構長
1967年岐阜県大垣市生まれ。東京工業大学大学院理工学研究科博士後期課程中退、東京大学大学院新領域創成科学研究科博士(環境学)。麗澤大学教授、日本大学教授、東京大学特任教授を経て現職。また、財団法人日本不動産研究所研究員、株式会社リクルート住宅総合研究所主任研究員、キャノングローバル戦略研究所主席研究員、金融庁金融研究センター特別研究官などの研究機関にも従事。専門は指数理論、ビッグデータ解析、不動産経済学。主な著書に『不動産市場分析』(単著)、『市場分析のための統計学入門』(単著)、『不動産市場の計量経済分析』(共著)、『不動産テック』(編著)、『Property Price Index』(共著)など。 マサチューセッツ工科大学不動産研究センター研究員、総務省統計委員会臨時委員を務める。米国不動産カウンセラー協会メンバー。