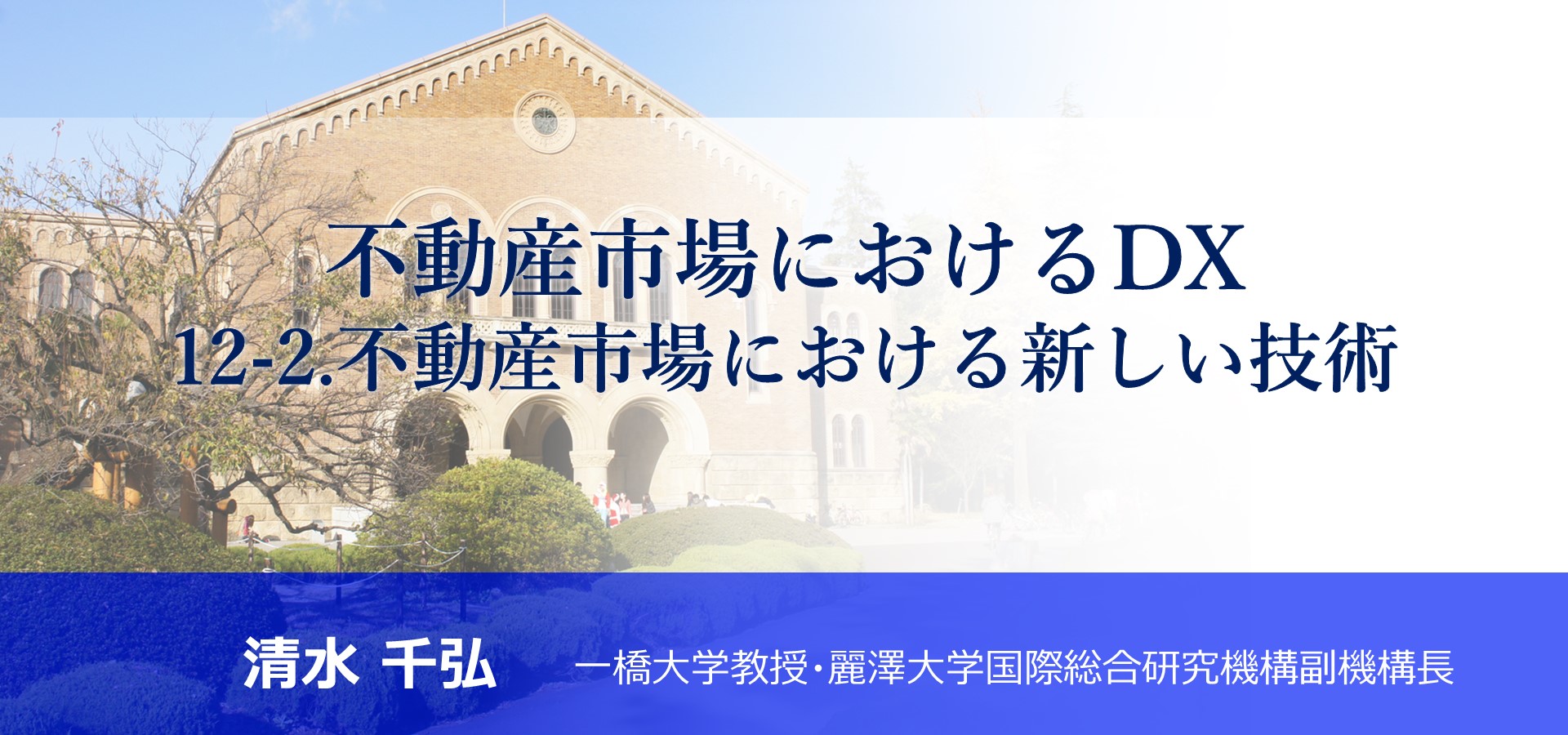不動産市場におけるDX
12-1. DXを推進する意義
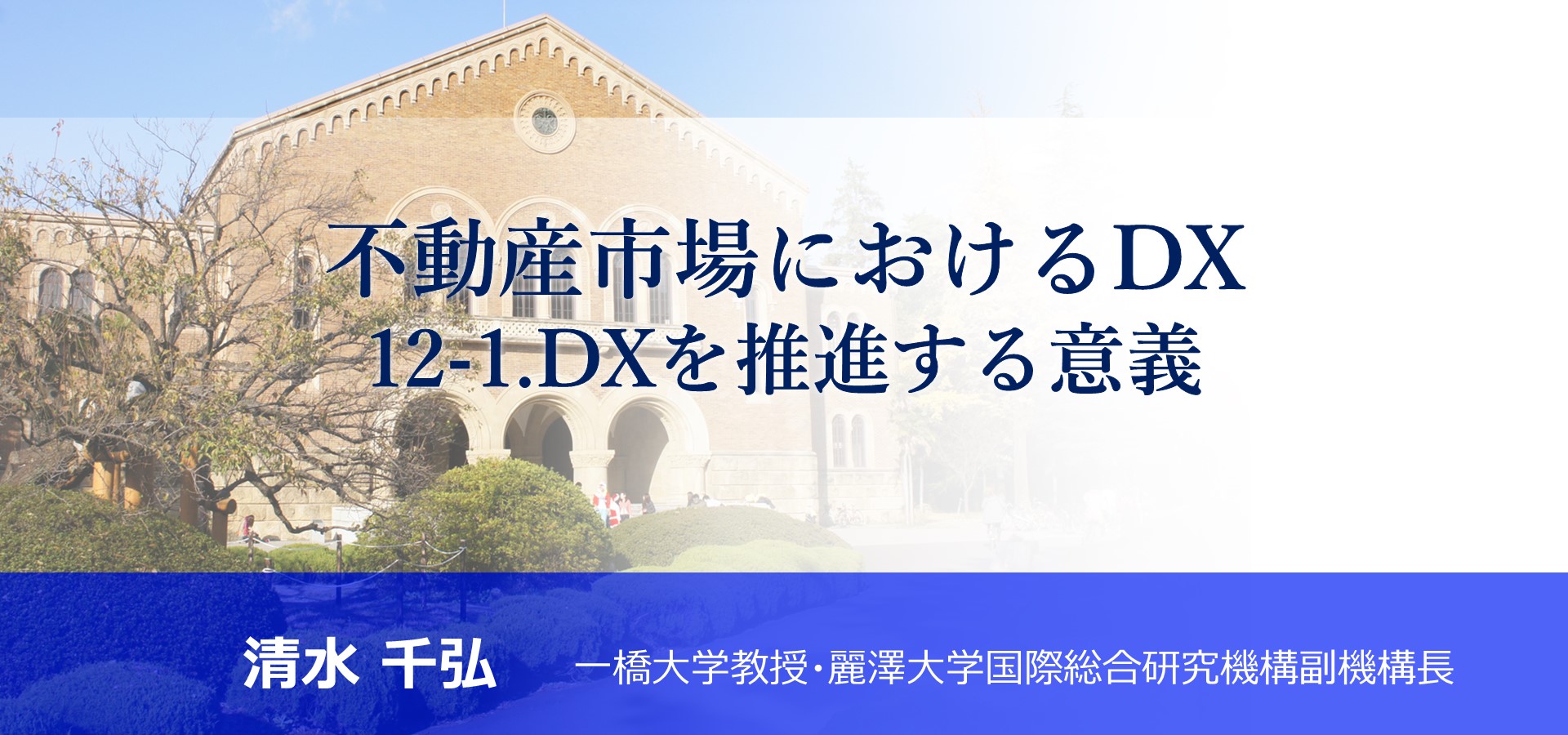
目次
2023年に入って日本でも、生成AI(人工知能)への注目が高まり、さまざまな分野でAIやDXなどの新しいテクノロジーを応用する動きが活発化してきました。不動産市場でも以前から新しい技術が取り入れられていますが、DXの進展について過去、現在、そして未来を展望してみたいと思います。
2010年代になって、「AI」「データドリブンな組織」「DX」という言葉がよく使われるようになりました。データドリブンな会社といえば、以前の経験や勘で行っていた経営から、データに基づいた意思決定に変えていくことを意味します。これを政策に適用すれば、エビデンスベースド・ポリシーメイキング(Evidence-based Policymaking)となります。
DXは、デジタル・トランスフォーメーション(Digital Transformation)の略語ですが、「ITの浸透が人々の生活をあらゆる面でよりよい方向に変化させる」という概念として使われるようになりました。2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン氏が提唱したといわれています。ビジネス用語としては、定義と解釈が非常に広い範囲で使われていますが、一言でいえば「企業がテクノロジーを利用して事業の業績や対象範囲を根底から変化させる」という意味合いで使われていると考えればよいでしょう。
DXのテクノロジーには、ITやAIなどが含まれますが、ITやAIを使って意思決定していくためには「データ」が必要になります。それが、データドリブンな企業経営、エビデンスに基づくポリシーメイキングに繋がってきたのです。
新しい技術はダイレクトに生産性の向上に繋がるのか?
DXが注目されるようになったのは「第4次産業革命」という新しいステージに向かって、経済構造が変化していくと考えられるようになったからです。
「第1次産業革命」は、18世紀後半から19世紀初頭にかけて、蒸気機関などに代表される新しい技術が登場したことによる経済変革を通じて、農業など第1次産業が中心だった社会経済構造が工業社会、そして第2次産業へと大きく変革しました。
19世紀からこの20世紀にかけて、電力や自動車産業、そして化学工業などの新しい生産技術が開発され、工業製品の生産性が大幅に向上することで工業化が一気に進んだのが、いわゆる「第2次産業革命」です。
そして「第3次産業革命」にシフトしていく。1946年に大型コンピューター「ENIAC(エニアック)」が誕生し、その後はインターネットやロボットなどの新しい技術が発明され、情報・知識の伝達速度が著しく向上し、情報の取得や処理速度が大きく改善されました。これらのテクノロジーを使って工業社会から、第3次産業である金融、不動産などサービスを中心とした産業への移行が進んできました。
そして、今「第4次産業革命」を迎えています。今から数十年後に歴史を振り返った時、「あの時から第4次産業革命が始まった」と言われるだろうと思います。
これらの新しい技術が登場してきた時に、すぐ生産性の向上に繋がるのかといえば、そうではないでしょう。第3次産業革命の経験を振り返ると、著名な経済学者のロバート・ソローは、1987年のNew York Book Reviewでこう述べています。
「コンピューター時代の到来があらゆる場で目にする。しかし、生産性の統計だけは別だ」
私が大学入学したのは1986年でしたが、当時の日本では「ワープロ(ワードプロセッサーの略語)」と呼ばれる機械が一般的でした。それまでタイプライターで打っていた文章を簡単に修正・印刷できるようになり、社会に浸透し始めた時期でした。
パーソナルコンピューター(パソコン)もIBMが1981年に発売し、日本ではNECなどがデスクトップ型の大きなパソコンを発売していました。コンピューターが一般的になってきた時代でしたが、それが生産性の改善に繋がるまでには時間が掛かりました。
私が大学院に進んだ1990年代になると、パソコンが当たり前になってきましたが、大きな計算はパソコンではなく、当時はIBMの大型汎用コンピューター「AX400」という機械を使っていた覚えがあります。いま手元にあるiPhoneは、その当時の汎用コンピューターの計算処理速度の何百倍になっています。
ビジネスにAIを装着させるために必要な技術とは?
新しい技術が誕生しても、必ず生産性の改善に繋がるわけではなく、それをビジネスの生産性改善へ装着させていくための技術が必要になります。
AIに関する代表的な図書に2018年に発刊された『Prediction Machines』があります。著者の1人であるアジャイ・アグラワル氏は、トロント大学のロットマンビジネススクールの学部長をしています。
AI革命は、ジェフェリー・ヒントン氏の「バックプロパゲーション(Backpropagation)」という技術が浸透し、従来の予測精度を著しく向上させたことで一気に注目されました。この技術が世の中に認知されたのは2006年です。
アジャイ氏は、私と同じブリティッシュコロンビア大学の経済学部を卒業し、現在はトロント大学でAIなどの技術を企業に装着させたり、企業が発明した技術を新しいビジネスに転換させたりする活動を行っています。日本でもいくつかの企業のアドバイザーをしています。
私自身は彼の本をAIのバイブルとして扱っていますが、日本の読者に向けて分書き下ろした『AIビジネスの基礎と倫理的課題』という本を2022年9月に出版しました。麗澤大学の同僚である高 巌氏との共著で、高氏は内閣府消費者委員会の委員長を務めているほか、大手デベロッパーの社外取締役も務めている経営学者です。
アジャイ氏の『Prediction Machines』では、「AIとは、一体何であるか」という定義から始まります。彼はAIを「予測マシン」と呼んでいて、予測マシンを企業のワークフローの中にどのように落とし込んでいくのかを考察しています。不動産業におけるDXを、どのような技術を使って、どのように進行させていったらよいのでしょうか。
「予測」は意思決定に不可欠な入力情報
AIは、広い意味で「予測」の技術です。正確には「予測」と「分類」の技術ですが、「予測」とは意思決定に必要な入力情報になります。我々は意思決定するときに、先を予測して、その予測をもとに現在の意思決定を行っていて、その「意思決定」を科学として解明してきたのが経済学です。
ノーベル経済学賞を受賞したジョセフ・スティグリッツ氏は「経済学というのは選択の科学である」と言っています。我々の経済活動は、1つを選択し、意思決定を行い、行動を起こすことで回っています。
この選択が、どのようなメカニズムで、どのような基準で行われているのか。その答えは、経済学の中にあります。現在、AmazonやGoogleなどの企業では、チーフエコノミストのポストがあります。チーフエコノミストの役割は、マーケットをデザインし、組織をデザインすることです。そのために、どのような予測マシンを作って意思決定をサポートするのかもデザインすることになります。
ハーバード大学のグレゴリー・マンキュー氏は、「経済学は日常生活を科学する」と言っています。日常生活の中には様々な選択があり、その選択の中では、我々は様々な予測をしており、この予測に対してAIが貢献してくれるようになったのです。
「今日では人工知能の進歩が目覚ましいが、その結果として知能がもたらされているのではない。実際にもたらされているのは、知能の大事な構成要素の1つである予測である」と、アジャイ氏は述べています。
予測は意思決定に欠かせない入力情報であって、経済学では意思決定を理解するための研究が発達してきました。予測技術の進歩に込められた意味を理解するには、経済学で採用されてきた「意思決定理論」と組み合わせればよいことになります。これがDXを成功させている企業に共通する仕組みです。
そう考えると、何が最善のAI戦略であるのか。「AIのツールをどのように組み合わせれば最善の結果を得ることができるのか」の正しい答えは、1つだけではありません。
AIにはさまざまなトレードフがあり、そのトレードフを考慮しながら経営的な意思決定を行い、何を優先し、何を諦めるのかを考えなければなりません。スピードを上げれば予測の精度が落ちます。自律性を重んじれば、統制が効かなくなります。データを増やしていけば、プライバシーが失われていくことになります。
AIを導入する決断を下すには、どのようなトレードフが発生するのかを確認する必要があります。組織の使命や目的を考慮しながら、よい面と悪い面を丹念に評価することで、最善の決断を下すことが可能になります。
AIによる予測コストの低下がもたらす効果
「安さはすべてを変化させる」という経済学の言葉は、人々がインセンティブに応じて行動を変化させるということです。インセンティブとは、価格であればより安い方向に、賃金であればより高い方向に働きます。
誰もがAIモーメント(AIが社会にもたらす変化)を過去に経験しており、まだ経験していない方も未来において確実に経験します。最近は、テクノロジー関連のニュースで溢れ返っている時代ですので、我々もそれらの情報に慣れきってしまって、テクノロジーの変化に影響されないのは変化に対する感覚が麻痺してしまっているからでしょう。
経済学者は、普通とは異なる視点で世界を眺めています。需要と供給、生産と消費、価格と費用などから見ていて、経済学者の間で意見が分かれることはありますが、共通の枠組みからは逸脱しません。だからこそ、普遍的なモデルや構造を知ることができるのです。
世間の熱狂とは少し離れたところでモデルを考えると、AIが組織にどのような影響を及ぼすのかを理解するには、具体的にどの製品の価格が変化して、それが広い経済にどのようなカスケード効果(ほかの人の決断に引きずられること)をもたらすのかを正しく定義し、小さな事象が次々と連鎖・増幅して大きな影響を及ぼしていくことを正確に測定する必要があります。テクノロジーが変化しても、経済の法則は変化しませんので、需要と供給の原則といった既存の原則で影響を測定することで予測は可能になります。
予測コストの低下がビジネスにもたらす影響も、重要になってきます。予測に関連する従来のタスク、例えば「在庫の管理」や「需要の予測」などを我々は行ってきましたが、例えば「自動運転」や「翻訳」などといった新しい問題にも予測マシンが使われるようになっていきます。
予測のコストの低下は、他の事象の価値にも影響を及ぼしていきます。データ、判断、行動などの補完財は価値を高めていきますし、人間による予測などの代替財の価値を低下させていくように作用します。
組織において、AIなど広い意味での機械が導入された時に、補完財が何で、代替財が何であるのかを考えると、組織における人間と機械との「分業と協同」が実現できるようになります。
AIを利用するための組織が新しい戦略を追求するようになると、AIが社会に及ぼす影響に関して新しいトレードオフが発生するようになります。トレードオフの選択の仕方に左右され、国や文化によってニーズや好みも異なってきます。その時にどのような仕組みを作って、企業や産業の中にAIという新しい技術を落とし込んでいくのか。これがDXとなります。
我々は予測を正しく理解し、意思決定を理解し、どのようなツールを使って新しい技術を装着させ、どのような戦略の下でDXを進めていくのか、企業の革新を進めていくのかを考えていく必要があります。その結果として生まれてくる社会をデザインしていく必要もあります。
デザインした社会から逆算して、どのような予測をしなければならないのか、どのような意思決定をしなければいけないのか、どのようなツールを作らなければいけないのか。「予測」から始まり、「意思決定」、「ツール」、「戦略」、そして「社会」というピラミッド構造を理解する必要があります。
社会課題を設定してマーケット・デザインを考える
予測の技術として、先に紹介したヒントン氏が「ディープラーニング」を提唱しました。ディープラーニングの特徴は、バックプロパゲーションという「誤差逆伝播法」に依存しています。予測して誤差があれば、それを元に戻してその誤差を修復するように学習し直していくことを繰り返します。
1986年にこの論文が出たときは、ディープラーニングを検証するのにとても高いコストが掛かりました。私が学生、大学院生の時代は、どれほど優れた手法が生み出されても、実際に計算するコストが高く、データそのものも不足していました。
我々は、すべてのデータを使うことができるとは限りません。しかし、確率論という統計的な技術を用いれば、小サンプルから母集団を類推することはできます。
日本は、これから不確実な「未知の世界」に突入していくと言われています。急速な人口減少や高齢化のような、今まで誰も経験したことがない社会に突入することで、我々はさまざまなリスクを抱えることが予測されます。新しい技術によって、これらの社会課題にどのように立ち向かうことができるのかについても考えてみたいと思います。

スピーカー
清水 千弘
一橋大学教授・麗澤大学国際総合研究機構副機構長
1967年岐阜県大垣市生まれ。東京工業大学大学院理工学研究科博士後期課程中退、東京大学大学院新領域創成科学研究科博士(環境学)。麗澤大学教授、日本大学教授、東京大学特任教授を経て現職。また、財団法人日本不動産研究所研究員、株式会社リクルート住宅総合研究所主任研究員、キャノングローバル戦略研究所主席研究員、金融庁金融研究センター特別研究官などの研究機関にも従事。専門は指数理論、ビッグデータ解析、不動産経済学。主な著書に『不動産市場分析』(単著)、『市場分析のための統計学入門』(単著)、『不動産市場の計量経済分析』(共著)、『不動産テック』(編著)、『Property Price Index』(共著)など。 マサチューセッツ工科大学不動産研究センター研究員、総務省統計委員会臨時委員を務める。米国不動産カウンセラー協会メンバー。
【コラム制作協力】有限会社エフプランニング 取締役 千葉利宏