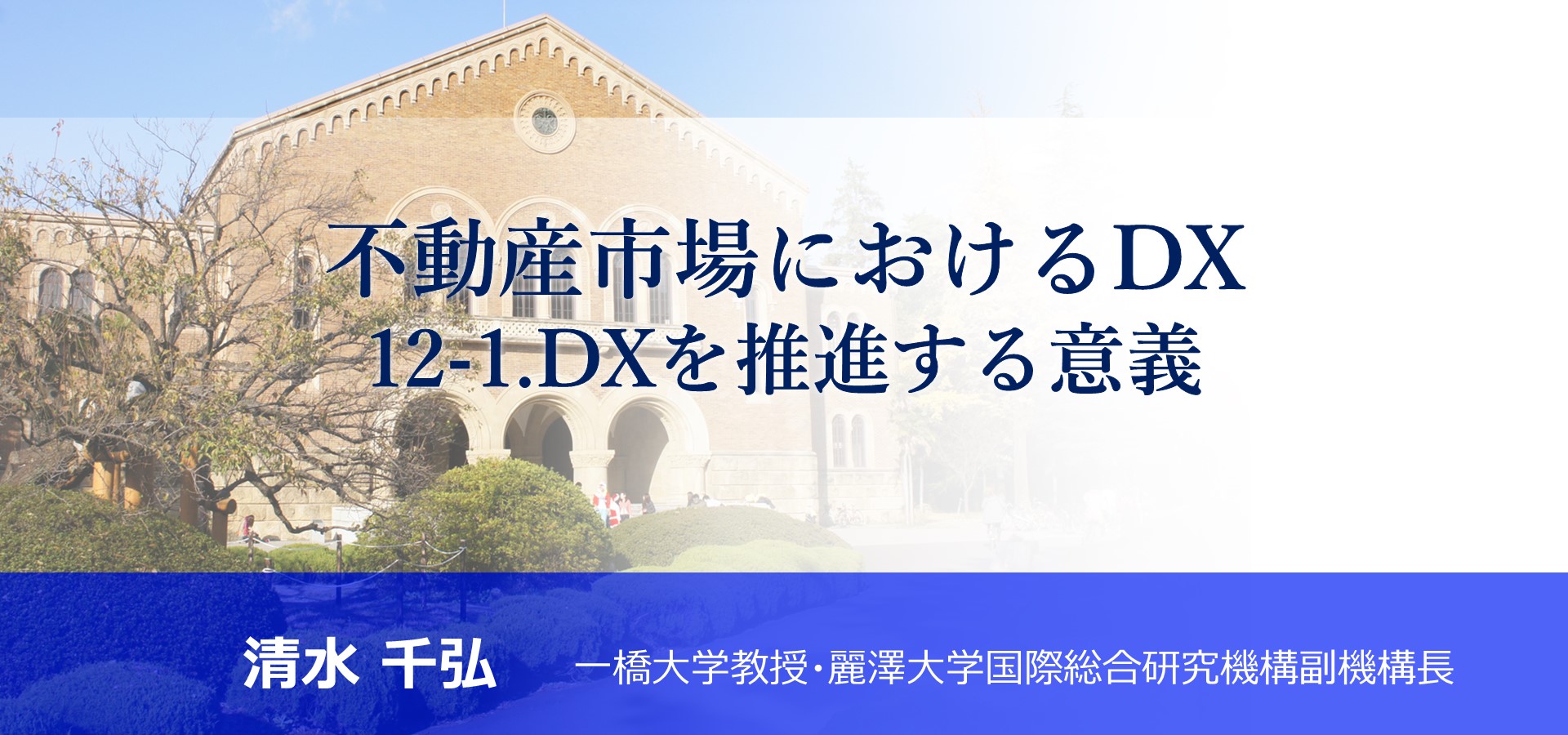ビッグデータでみる都市・不動産市場の未来
11-3.ビッグデータでみる「不動産市場」の未来②

目次
ビッグデータでみる「不動産市場」の未来①はこちら
住宅取得能力からアジアの主要都市の住宅市場を比較
住宅・不動産市場と人口との関係から、MIT(マサチューセッツ工科大学)のレポートでは「Affordable Housing(住宅取得能力)」の問題が重要であると指摘しています。未来においては、所得と財産の格差が一段と拡大していくと予測されるためです。
「住宅の取得に、所得の30%以上をかけるべきではない」と、経済学者のペルティエール氏は2008年の研究で示しました。この研究では、住宅の負担能力を「Price to Rent Ratio(家賃に対する住宅価格比率)」という指標で世帯別に見ています。
低所得者は、住宅の費用が相対的に高くなります。米国の学術雑誌のJournal of Financeに掲載された論文では、「過去20年間のデータから、低所得者と中所得者層において所得と財産の成長が非常に鈍くなっている」と明らかにしています。
住宅取得能力を新築住宅で考えると、建築費の高騰が大きな問題になっています。人材不足や、エネルギーコストの上昇、鉄やコンクリートなどの部材コストの値上がりで建築コストが高くなり、2次流通マーケットの既存住宅価格も上昇しています。
「Housing Affordability(住宅の手頃な価格)」について、2022年に不動産・土地利用に関する国際的非営利研究機関であるUrban Land Instituteが、アジアの主要都市を対象に比較研究プロジェクトを立ち上げました。
その依頼が私に届いたことから、シンガポール国立大学でリサーチチームを率いているクワン・リー氏、香港大学の建設不動産学部長をしているケルビン・ウォン氏、上海の復旦大学から北京の清華大学に移ったシャオ・ユー・ギオ氏などに声をかけてチームを立ち上げ、オーストラリアも含めて5カ国、28都市を対象にHousing Affordabilityのインデックス(指標)を作成するプロジェクトを行いました。
このプロジェクトで非常に難しかったのは、各国の住宅市場の異質性(Heterogeneity)でした。東京や香港では公営住宅があり、シンガポールではラクジュアリーな戸建て住宅がある一方で、ほとんどの方は公営住宅に住んでいます。深圳(中国)のような未来都市がある一方で、日本には築古のマンションが多くあります。中国の主要都市やシンガポール、香港などを比較するのに、住宅の品質をどう揃えて比較するのかが非常に難しく、できる限り品質を揃えて比較することを試みました。
東京都心部の分譲マンション価格は高いのか、安いのか
「今、東京の新築マンションが高すぎる」という議論がありますが、比較対象を何にするのかは難しい問題です。
戸当たりの価格で見ると、圧倒的に高いのが香港、そしてシドニー(オーストラリア)のデタッチド・ハウス(土地付き一戸建て住宅)です。深圳のように香港からの近くの新興都市やシンガポールも非常に高いですが、これらの都市と比較すると、東京はそこまで高いのかというと、それほど高い水準にはないといえます。
一戸あたりの広さも都市によって異なっていて、メルボルン(オーストラリア)では191㎡が平均的な姿になっています。シンガポールも112㎡となっていますが、それ以外の多くの都市では、標準的な広さは72㎡ぐらいです。
1㎡当たりの住宅単価で見ると、圧倒的に高いのが香港で、その次が東京の都心5区、続いて深圳、シンガポールとなります。
所得の何倍ぐらいで住宅が買えるのかを示す「所得比率」を見ると、深圳が40倍、香港が30倍、ソウルが18倍です。東京は16倍で、これをもって高いと言われていますが、ここで少し考慮すべき問題があります。
中国、香港、シンガポールでは、高額な住宅を買う人は少なく、公営住宅に住んでいる人が圧倒的に多い。香港では、劣悪な住環境で暮らしている人も多く、一般的な住宅市場で買っている人は一握りです。
日本では、香港やシンガポールのように限られた都市空間の中で住宅が取引されていることはなく、都心5区の周辺には18区があり、さらに神奈川や埼玉や千葉が背後に控えています。こうした状況を経済学では「代替財が存在する」といいます。代替財がない市場では、Housing Affordabilityは大きな問題ですが、東京には代替財が存在します。周辺エリアで供給される標準的な住宅で満足できるのであれば、Housing Affordability問題は存在しないことになります。
各国の都市の形成によっても、この問題は大きく異なります。アメリカのように、低所得者は危険なスラムにしか住むことができない、スラムに1度入ると外へ出るのが難しいといった格差が生み出されているなら深刻な問題です。しかし、日本では、どこに住もうと治安はよいですし、どの地域に住むのも自由に選択できます。
そう考えると、所得比率の倍率は慎重に見ていく必要があります。比較対象になる住宅のグレードはさまざまで、所得は平均値を見ているので、30倍40倍といった異常な倍率が出ていると考えられるためです。最近の東京都心部で新しく供給されているマンションを見ると、非常に高品質で、エネルギー性能が高く、さまざまな共有施設が充実していて、以前に供給されたマンションとはますます比較するのが難しくなっています。
各都市で持ち家比率を比較すると、香港などは非常に低く、公営の賃貸住宅に住んでいる人が多いためです。逆に、シンガポールの持ち家比率が高いのは、政府から払い下げられている公営住宅を購入しているためで、これは各国の住宅政策の違いに起因しています。
建築コストの上昇をテクノロジーで解決する方法
私たちが注目しなければならない問題に、建設部門のコスト上昇があります。建築コストは、1980年代のバブル時代に高くなりましたが、現在そのとき以上に上昇しています。その原因が高齢化と人口減少による労働者不足であるならば、どのように解決するのか。MITのレポートは、「デザインや建築技術、材料におけるイノベーションが建築コストの削減に大きな役割を果たす」と予測しました。
問題解決の方法として、「Cost-effective Construction(費用対効果の高い建設)」が考えられています。リサイクル材料の使用、3次元設計システムのBIM(Building Information Modeling)の活用、3Dプリンターを使った部材の開発、下請け会社の雇用改善、モジュール式住宅、柔軟な労働慣行を取り入れていく必要があります。
建築現場での労働力不足に対応するため、労働時間の管理や労働環境の改善も重要な課題になっています。人材配置のローテーションや人材マーケットを技術によって最適化できれば、労働コストの抑制と労働環境の改善を同時に実現できます。
私の研究室では、BIMに関する研究を進めており、BIMによる自動設計技術や、BIM導入によって建物の竣工後の情報をBIMに蓄積して維持管理コストを低減させる技術を研究しています。このような技術によって建築コスト問題もビッグデータを活用して改善できるようになるでしょう。
人の配置の最適化では、オフィスビルの中で働く人たちの行動を、センサーを使って、どの時間帯にどれぐらいの人が稼働しているのかをモニタリングします。オフィスワーカーが、どの時間帯にどの場所に集積して、どのチームから新しい生産性を上げる試みが生まれているかを調べることで、オフィスのレイアウトを改善し、エネルギーコストの削減もできるようになります。
「オフィスに、来週出社する人たち」を予測することも、ビッグデータを使えば可能です。その予測値にもとづいて、余剰の時間や場所をどのようにコントロールするかで、新しい価値をオフィスビルに作り出せるでしょう。
こうした技術を病院で使うと、来週の患者数を予測できます。コロナ禍では、医師や看護師の不足が大きな社会問題になりました。来週の患者数を予測して、医師や看護師の配置を最適化する研究も進んでいます。すでに予測値と実績値がピタッと一致するような成果が出ており、ビッグデータの活用事例として期待されています。
この技術を、建物の外側に出すと、人々がどのような経路で動いているかを示す「人流データ」になります。携帯電話の位置データを時間帯ごとに追いながら人々の移動を記録し、GPSデータで解析することで、CO2を最小化できる最適な移動手段を選択してシミュレーションできます。
こうした新しい技術やビッグデータの活用が、不動産市場の未来を変えていくドライバーになると考えています。
洪水リスクや急勾配のある可住地から安全な場所へ
不動産市場の未来を予見していくうえで重要になるのが「持続可能性」という問題でしょう。
日本は、他の国に比べて河川が急勾配であるという問題があります。それによって土砂災害や浸水のリスクが非常に高く、洪水が起こるリスクをいかにコントロールしていくかが重要です。
高齢化の進展は、可住地にも大きな影響を及ぼします。日本は国土面積の6%に過ぎない都市の中に、80%の人たちが住んでいます。首都圏でも、横浜や東京には急勾配の土地があり、多くの住宅が立ち並んでいます。
高齢化が進むと、斜度が高い場所には、人が住まなくなり、平坦な場所に人が集まるといわれています。これは世界的に起きている現象で、約200都市を調べた研究で共通の傾向が発見されています。
先ほど紹介したアルバート・サイツ氏は、「供給の非弾力性」を研究し、良好な住宅地である可住地を定義しました。人は、水辺や道路、鉄道の上には住めませんが、15度以上の斜度がある場所にも人が住めないと定義して可住地を計算しました。国際比較のために可住地を同じように定義すると、日本は人が住める可住地が非常に少ないことが分かります。
不動産の取引件数を登記件数のビッグデータから調べると、可住地の中では万遍なく取引が行われていました。さらに、2010年に取引があり、2020年には所有権の移転がなくなったエリアを見ると、首都圏の中にも多く点在し、九州、四国・中国地方、北海道などの可住地があるところでも多く見られました。1年間まったく取引がないエリアは不動産市場が機能不全に陥って、人が住み、家はあるけど、流動性が失われているエリアです。
都道府県別に、可住地の数や、危険なエリアに人が住んでいる数などを集計すると、可住地の中であっても、リスクがある場所に多くの人が住んでいることが分かります。浸水区域の中や、土砂災害エリアの中に多く人が住んでいます。
そうしたエリアから、人々がどのエリアに移り住んでいくことで安全になるのか。資産としてのサステナビリティが維持できるのか。不動産市場が消滅しているような流動性が欠けているエリアが今後、どのように広がっていくのか。私たちは、こうした状況を合わせて見ていく必要があります。
不動産市場は、これから未来に向かってどのように変化していくのでしょうか。人口減少によって日本の都市はなくなりつつあります。人が集積するエリアもなくなりつつあります。不動産取引市場もなくなりつつあります。その一方で、高齢化の影響を受けながら相続件数は増えており、気候変動リスクに晒されながら危険なエリアに住み続けている人たちがいます。日本においてAffordability問題があるとするならば、安全なところに人々が住むことができていないという問題であると思います。

スピーカー
清水 千弘
一橋大学教授・麗澤大学国際総合研究機構副機構長
1967年岐阜県大垣市生まれ。東京工業大学大学院理工学研究科博士後期課程中退、東京大学大学院新領域創成科学研究科博士(環境学)。麗澤大学教授、日本大学教授、東京大学特任教授を経て現職。また、財団法人日本不動産研究所研究員、株式会社リクルート住宅総合研究所主任研究員、キャノングローバル戦略研究所主席研究員、金融庁金融研究センター特別研究官などの研究機関にも従事。専門は指数理論、ビッグデータ解析、不動産経済学。主な著書に『不動産市場分析』(単著)、『市場分析のための統計学入門』(単著)、『不動産市場の計量経済分析』(共著)、『不動産テック』(編著)、『Property Price Index』(共著)など。 マサチューセッツ工科大学不動産研究センター研究員、総務省統計委員会臨時委員を務める。米国不動産カウンセラー協会メンバー。
【コラム制作協力】有限会社エフプランニング 取締役 千葉利宏