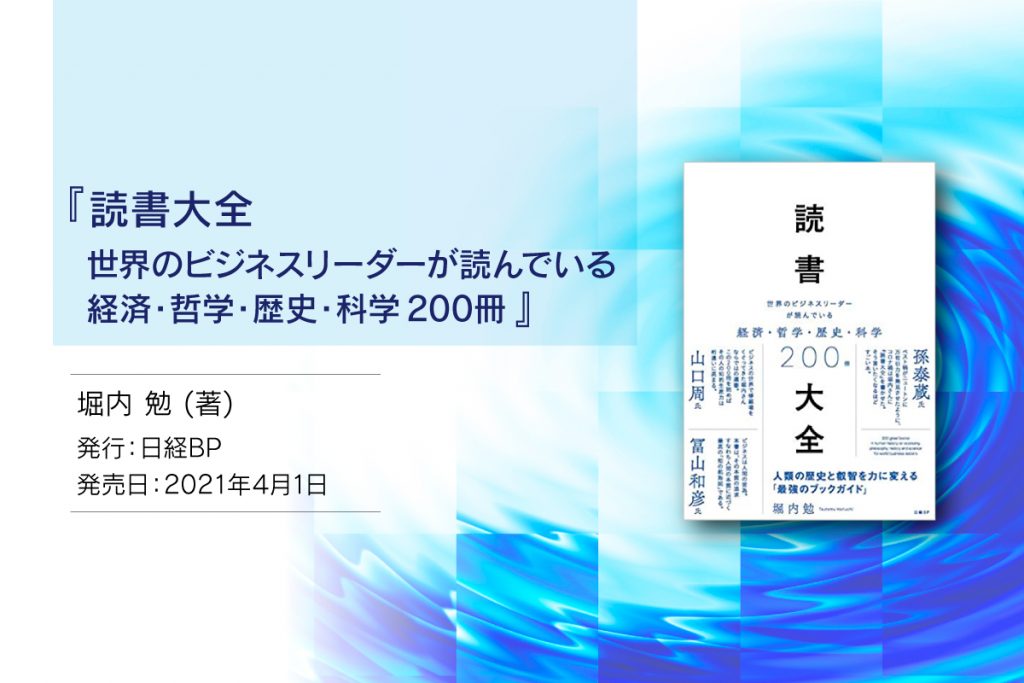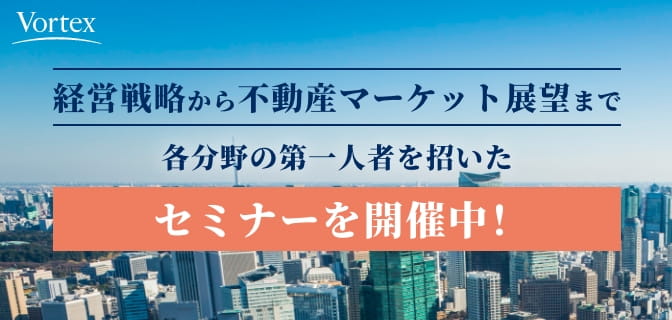ビジネスパーソンに贈る最強のブックガイド、『読書大全』
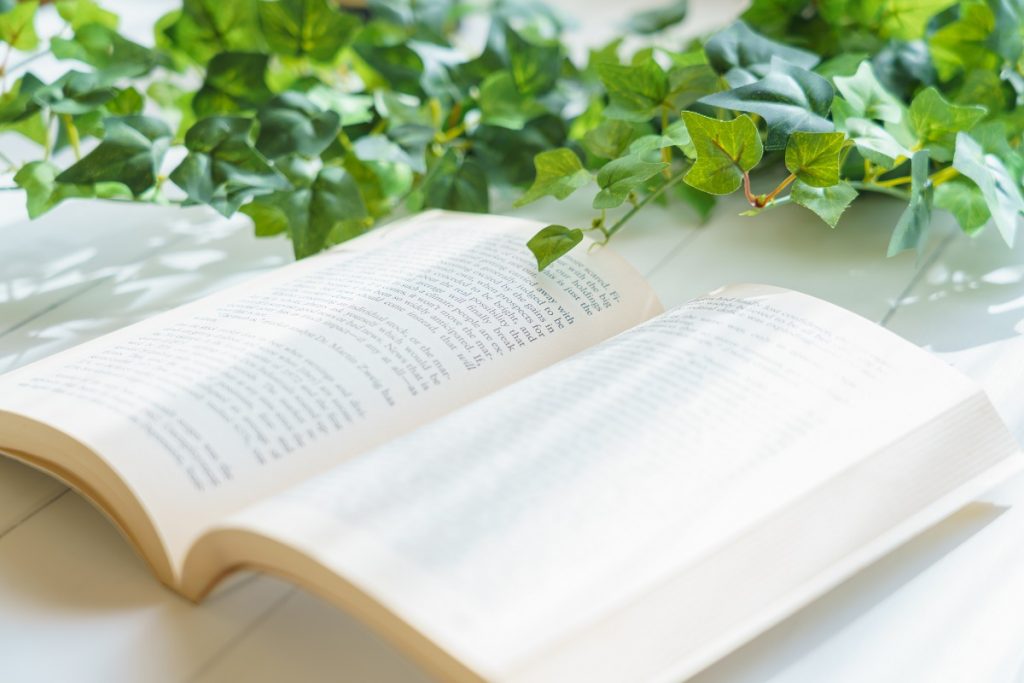
目次
記事公開日:2021/06/08 最終更新日:2023/04/17

堀内 勉 (著)
発行:日経BP
発売日:2021年4月1日
ビジネスの世界で修羅場を経験した、100年企業戦略研究所 所長の堀内勉が『読書大全 世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・歴史・科学200冊』を上梓するに至った理由、「本との向き合い方」や「読書の仕方」を紹介します。

著者
堀内 勉
一般社団法人100年企業戦略研究所 所長/多摩大学大学院経営情報学研究科教授、多摩大学サステナビリティ経営研究所所長
多摩大学大学院経営情報学研究科教授、多摩大学サステナビリティ経営研究所所長。東京大学法学部卒業、ハーバード大学法律大学院修士課程修了、Institute for Strategic Leadership(ISL)修了、東京大学 Executive Management Program(EMP)修了。日本興業銀行、ゴールドマンサックス証券、森ビル・インベストメントマネジメント社長、森ビル取締役専務執行役員CFO、アクアイグニス取締役会長などを歴任。
現在、アジアソサエティ・ジャパンセンター理事・アート委員会共同委員長、川村文化芸術振興財団理事、田村学園理事・評議員、麻布学園評議員、社会変革推進財団評議員、READYFOR財団評議員、立命館大学稲盛経営哲学研究センター「人の資本主義」研究プロジェクト・ステアリングコミッティー委員、上智大学「知のエグゼクティブサロン」プログラムコーディネーター、日本CFO協会主任研究委員 他。
主たる研究テーマはソーシャルファイナンス、企業のサステナビリティ、資本主義。趣味は料理、ワイン、アート鑑賞、工芸品収集と読書。読書のジャンルは経済から哲学・思想、歴史、科学、芸術、料理まで多岐にわたり、プロの書評家でもある。著書に、『コーポレートファイナンス実践講座』(中央経済社)、『ファイナンスの哲学』(ダイヤモンド社)、『資本主義はどこに向かうのか』(日本評論社)、『読書大全 世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・歴史・科学200冊』(日経BP)
▶コラム記事はこちら
『読書大全 世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・歴史・科学200冊』とは
2021年4月1日に『読書大全 世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・歴史・科学200冊』を上梓しました。人類の歴史に残る名著300冊をピックアップして、その内の200冊について書評を書いたものです。この300冊を、「第1章 資本主義/経済/経営」「第2章 宗教/哲学/思想」「第3章 国家/政治/社会」「第4章 歴史/文明/人類」「第5章 自然/科学」「第6章 人生/教育/芸術」「第7章 日本論」の7つに分けています。
難解な哲学や思想の本についても、できるだけ平易な言葉で分かりやすく書くように努めましたが、それでもやはり堅い内容の本には違いないので、一部の本好きの方々にしか受け入れられないだろうと思っていました。
それが意外にも好評を博して、発売から1カ月半の5月中旬の段階で第5刷まできて、多くの書店で平積みにしてもらえると同時に、日経ビジネスオンラインを始めとした色々な媒体で特集を組んでもらっています。また、様々なオンラインセミナーにも声がけしていただき、視聴者の方々とインタラクティブに意見交換する中で、「読書」のあり方について、改めて気づいたことも多々ありました。
本との向き合い方、読書の仕方
私の本との向き合い方、つまり読書の仕方ですが、これはスタンスがかなりはっきりしていて、「自分の生き方と照らし合わせて読む」というものです。ですから、読む本としては、必然的に哲学や思想関係のもので、自分の生き方やあり方に関わるものが多いです。また、ビジネスマンとしてライフワークにしている資本主義と人間との関係、資本主義社会における自分の立ち位置、そしてその中で自分はどう生きるかという問いに対する答えを探すために、これまで様々な本を読んできました。
ある意味で、最初からこうした根源的な「問い」があり、その答えを探すための「探求」としての読書なのかも知れません。そのため、私は本を買うとまず「前書き」を読み、次に「後書き」を読み、さらに「目次」を見ます。ここまではどんな本でも同じです。そして、目次の中から興味が持てそうな章をピックアップして、そこから読み始めます。そこが面白ければ、周りの章を読み、すごく面白ければ、最初の章に戻って全体を読みます。要は、自分の問題意識に沿ったことがどのように書かれているかを確認しながら読み進めるということです。
こうした過程で面白くない本やすでに自分が知っていることが書いてある本は、途中で読むのを止めてしまいます。私は大体一日一冊本を買っていて、40歳代の頃まではそれらをほとんど読んでいたのですが、今は年間200冊くらいしか読んでいないと思います。どうしてそれほどたくさんの本を読めるのですかという質問をよく受けるのですが、実はこのように一冊の本を頭から終わりまで全部読まないので、速く読めるのだと思います。全体を読むというのは、恐らく1割から2割くらいしかないのではないでしょうか。
読書は「自分の生き方と照らし合わせて」「知的好奇心の赴くままに」
このように自分の生き方と照らし合わせて読むという以外では、自分の知的好奇心の赴くままにランダムに読むというのがもうひとつで、それはほとんどの場合、自然科学系の本になります。特に、宇宙の起源や成り立ち、脳科学や精神・心に関するものについては、根源的な知的好奇心をかき立てられるので、新しい学説を紹介した本が出ると必ず読むようにしています。
従って、私が読む本のほとんどは、必然的にノンフィクションということになります。ポール・ゴーギャンの有名な絵画に『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか(D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?)』というものがありますが、これが我々人類にとっての最も根源的な問いなのだとすれば、私の読んでいる本は、全てこの問いに沿ったものだと言えるかも知れません。
ですから、本好きを自認してはいますが、小説は余り読みません。もちろん、子供の頃はたくさんの小説を読みましたが、私にとって小説は作者との心理的な距離が近過ぎて、どこかパーソナルで息苦しくて、居心地が悪いような気がします。特に、私小説のような一人称のものは、そのように感じます。
そうした意味で、やはりノンフィクションの方が客観性があって、世の中全般とのつながりを広く持てるような開放感があると感じています。ニュートンが、フランスの哲学者ベルナールの言葉を引用して、「私がかなたを見渡せたのだとしたら、それは巨人の肩の上に乗っていたからだ」と言っていますが、私にとって価値のある本というのは、そういう自分の視野を広げてくれるようなものだと思っています。
そうした中でも、私が好きな数少ない小説家の一人が、日系イギリス人作家のカズオ・イシグロです。映画化された『私を離さないで』『日の名残り』などに代表されるように、「人間とは何か?」「自分とは誰か?」を問い続けるイシグロの作品は、フィクションではあっても、根源的な問いに沿ったもので、私の心を捉えて離しません。
長くなりましたが、以上が私の読書方法です。実は「読書」そのものについてこれまで真剣に考えたことがなく、これまでずっと、私のような読み方が普通なのだと思っていました。つまり、本というのは、自分の問題意識に沿って「読む」ものであって、一方的に「読まされる」ものなのではないと思っていたのですが、今回、色々な方々と意見交換させていただく中で、本の権威主義的なところが好きになれないという方が何人かいました。つまり、本の存在自体が上から目線で偉そうだということらしいのですが、もしかしたら、そうした認識というのは、現代の「反知性主義」的な動きや歴史上見られた「焚書」(言論統制のための為政者による組織的な本の焼却)にも通じるものなのかも知れません。
私は、読んで共感できない本は直ぐに読むのを止めてしまえば良いと思っているので、ある本を読んでそれに反発するとか反感を覚えるということがありませんが、人によって本への向き合い方が随分と違っているのだなと思いました。
おわりに:『読書大全』の読み方
時には強い思い入れをもって本を読むということも必要なのかも知れませんが、せっかく手に入れた本については、大人と大人との付き合いのように、相手の立場を尊重しながら冷静に読み進めて、良いところは良いところとして受け入れて、自分の人生の一助としていただくのが良いのではないかと思います。私の『読書大全』についてもそのように読んでいただき、この中から少しでも自分に合った一冊を探し出されることを願っています。
読書体験は、皆さんが重大な経営判断や経営危機に直面し、人生の岐路に立たされたとき、そして自分とはなにか、自分が本当はなにがしたかったのかを改めて考えてみなければならないときに、必ずや、一筋の光明になると信じています。
『読書大全』をひらく
「『読書大全』をひらく」の連載では、『読書大全 世界のビジネスリーダーが読んでいる経済・哲学・歴史・科学200冊』』の中から、企業の持続可能性に関わるものをピックアップして解説しています。