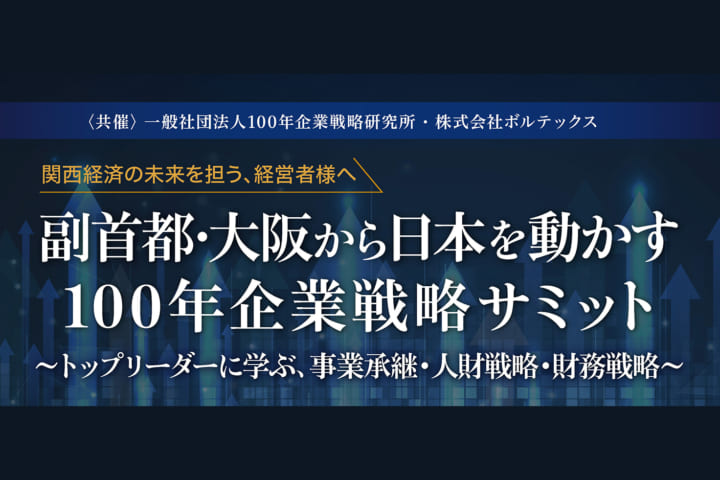AIビジネスにおける企業戦略と未来 ~企業はAIとどう向き合うべきか⑪

目次
【関連コラム】
データドリブンな企業への変容~経営者はAIとどう向き合うべきか①-1
データドリブンな企業への変容~経営者はAIとどう向き合うべきか①-2
AIと予測(AIで何ができるのか?)~経営者はAIとどう向き合うべきか②
AIの発展と方法論~経営者はAIとどう向き合うべきか③
機械学習の発展と、不動産価格の予測~経営者はAIとどう向き合うべきか④
AIを生み出すデータ資源~経営者はAIとどう向き合うべきか⑤
データ資源と決断~経営者はAIとどう向き合うべきか⑥
AIが行う予測と判断、人間の意思決定~企業はAIとどう向き合うべきか⑦>
AIが行う予測と、最善の判断~企業はAIとどう向き合うべきか⑧>
ワークフローと決断を分解する~企業はAIとどう向き合うべきか⑨>
AIツール導入と、仕事の再編~企業はAIとどう向き合うべきか⑩>
これまで「経営者は、進化するAIの導入を、どのように進めていけばよいか」という視点から、企業におけるAI導入について整理してきました。ここからは「企業がAIを含む新しい技術を取り入れて、どのように戦略を作っていけばよいか」という点に注目していきます。
海図をつくる
最近では、多くの企業が、DX事業部やテクノロジー推進室のような組織を立ち上げ、工学系の大学や大学院を卒業した人を、そこの役職に任命しています。私自身も企業でそのような任命を受け、働いた経験があります。これまで登場してきたA社の社長も、DX事業部を立ち上げて「清水君」を部長に任命しました。
「テクノロジーの進化は、業界だけでなく社会をも変えてきた。AIなどの新しいテクノロジーは第4次産業革命といわれるが、10年後まったく新しい社会構造、業界構造に変化していることは間違いない。市場において、競争の形もシェアも変わっていくだろう」
経営者は、どのように企業の舵を取るかについて、絶えず考えなければなりません。そのためには、長期ビジョンが必要になります。航海に例えれば、海図をつくって、針路を決める必要があります。非常にリスクの高い大海原で、リスクを最小限に抑えて目的を達成するには、正確な海図は不可欠です。海図の精度は、航海の行方を大きく左右します。
「社長、私はDX事業部長です。技術のことしか経験がありません。正確な海図をつくるような仕事は、私にはできません」
部長の清水君は、そう答えるでしょう。A社は、DX事業部でAIを推進してきましたが、その判断は正しかったのでしょうか。
私が企業で働いていた際も、技術者でありながら社長室に異動となり、社長の秘書をしていた時期があります。その判断は、企業にとって正しかったのか、私で秘書の仕事が務まったのかは分かりませんが、貴重な経験をしました。
AIとビジネスが融合する世界の代表的な研究者であるカナダのトロント大学のアジャイ・アグラワル教授の著書『Prediction Machines』では、Strategy(戦略)のパートで「企業の未来」について考察しています。
AIには予測する力があり、企業はそれを意思決定に繋げます。企業が決断して行動し、その結果をフィードバックしながら、AIの使い方やツールを改善していきます。そのツールを企業の中に取り込み、人間のタスクを機械が担っていきます。
そのタスクを、企業のなかで明確に定義して、人間と機械が共存することで、生産性が高まっていきます。それを実現するには、戦略が重要になります。経営者は、もう一度戦略としてAIビジネスを捉え直し、そのリスクとも向き合っていくことが重要になります。
経営層にとってのAI
「ダボス会議」で有名な世界経済フォーラム(World Economic Forum)の創設者であるクラウス・シュワブ氏による『The Fourth Industrial Revolution』という書籍があります。この書籍には、世界のトップ経営者が集まる会議で、どのような未来が予測されているのかが書かれています。
「この本を読みなさい!」と私に言ったのは、Googleのリサーチチームを10年間率いてきたアロン・ハレヴィでした。2015年に彼と出会い、一緒に仕事を始めたとき、「関わっている世界に、どのような未来が待っているのかを予測したうえで、AIについてもう一度捉え直してほしい」と思ったのでしょう。
私が専門とする不動産や人材、金融におけるAIの領域では、正しい未来の予測ができなければ、戦略を立てることはできません。今ある最先端の予測技術を導入するのに、どのようなツールを作るか、どのようなデータを集めるか。そのデータは社内にあるか、なければ業務フローを変えればデータを得られるか。既存のデータを変換すれば使えるようになるか。外部から調達すればよいか。そうした戦略を考えなければなりません。
AIの進化を見れば、過去に発明された数々のテクノロジーと同様に、時代を大きく変えていくことが容易に予測できます。しかし、未来にどういう社会が待っているかを予測することは極めて難しいことです。電気、車、プラスチック、マイクロチップ、インターネットなどが誕生したときも、破壊的な変化がいつ、どこで、どのように起こるのかを誰も予測できませんでしたし、今もそうでしょう。
皆さんの会社の役員会で、AIを重要議題にするのはいつでしょうか。議題にあがったとき、「AIが未来を正しく予測して、意思決定できない自分の存在を脅かしてしまう」と思う(旧来の)役員がいれば、反対に遭うのはほぼ確実です。そのときにCEO(経営最高責任者)は自らの権限を発揮して、どう向き合うか。苦しい選択が待っているでしょう。
AIはいかにビジネス戦略を変革するか?
私が企業でAI研究所を立ち上げて事業を推進しようとしたときも、私やチームの若いメンバーは、とてつもない逆風にさらされました。その逆風をどう乗り越えるかは、経営者の手腕にかかっていると思います。CEOはビジネス戦略を策定するときに、そうしたジレンマに陥ることを事前に覚悟する必要があります。
AIは予測することで不確実性を減らすのが役割ですから、不確実性を減らすことで解決できる問題を企業が抱えていなければAIを導入する意味はありません。予測マシンの存在が不可欠なら、積極的に投資すればよいし、必要がなければ、じっくり待って予測マシンが安くなったときに経営判断すればよいのです。
企業は、産業を壊すような破壊的なテクノロジーの登場や、新しい競合企業によって脅かされるリスクを常に考えなければなりません。例えば、ある経営者は、eコマースの配達遅れを解消し、できるだけ早く商品をお客様に届けることが重要なポイントだと考えました。これを実現するには、自分たちで在庫を抱えて商品の欠品をなくす必要がありますが、それによって在庫費用が増加してしまうジレンマに陥ります。しかし、AIによって正確に需要を予測できれば、在庫の問題は克服できます。『Prediction Machines』でも、物流拠点の再編によって、こうした問題をクリアした事例が紹介されていますし、私が手掛けた仕事でも同じような経験があります。
新しいテクノロジーを導入する時期はいつか?
どのタイミングでAIを導入すればよいか。その経営判断は極めて難しいといえます。農業分野でトウモロコシのある新種を導入した事例で考えてみましょう。
この新種は、乾きに強く、気候など地域環境に適応する力に優れているものでした。新種を投入すれば、生産性は上昇するものの、種苗の生産コストはまだまだ高い。農業経営者はいつ導入したらよいのかという問題に直面し、アラバマ州ではアイオワ州に比べて新種採用が20年遅れました。では、アラバマ州の農業経営者は怠慢だったのでしょうか?このケースを、ハーバード大学のツヴィ・グリリカス教授が研究しました。
グリリカス教授は、私の恩師であるブリティッシュコロンビア大学のアーウィン・ディワート教授の上司にあたる方でした。ディワート教授から、しばしばグリリカス教授の話を聞かされていましたが、彼はデータを正しく見て判断できる優れた教授だったそうです。一般的に、新しい品種が出てくれば、生産性の観点からそれを使うべきと考えるのが正しい判断です。しかし、グリリカス教授は1930年代のトウモロコシ生産の投資リターン(ROI)から見て、アラバマ州での新種採用は正当化できなかったことを証明しました。このことは、『Prediction Machines』でも紹介されています。アジャイ・アグラワル教授によると、当時、アイオワ州では広大な大地で大規模農業を展開できていたので、新しいテクノロジーの品種を投入することで生産性が上がり、より多くの利益を得ることができました。しかし、アラバマ州では小規模農業が主流で、コストの高い新種を採用しても、十分なリターンを得ることができず、新種を採用しないほうがROIは高かったといいます。
このような事例からも分かるように、AIを導入すれば、常に利益が上がるというものではありません。現在のAIのコストは高額です。GoogleやAppleなどのような巨大企業であれば、そこに舵を切るのは当たり前の時代ですが、自分の会社の事業規模でAIへの投資が見合うのかどうか、自分の会社が置かれている業界がAIに投資できる環境かどうかも判断して、AIのコストを注視しつつ、いつ導入するのかについて、経営者は考えなければなりません。
消費者には、新しい商品やサービスを購入するときに不安や懸念を感じる「知覚リスク」があります。例えば「家を買いませんか」と人間が言う場合と機械が言う場合ではどちらを信用するか、病気の診断における医師とAIの判断のどちらを患者は信じるか、といったAIに対する知覚リスクは、いつ取り除かれるのでしょうか。
人間と機械の予測精度が同じで、多くの人が人間のほうが好ましいと思っている段階では、いくら予測マシンを投入してもマーケットを獲得することはできません。そのとき、経営者は新しいテクノロジーの導入を遅らせることによる利益放棄とリスクのトレードオフに直面するのです。

著者
清水 千弘
一橋大学教授・麗澤大学国際総合研究機構副機構長
1967年岐阜県大垣市生まれ。東京工業大学大学院理工学研究科博士後期課程中退、東京大学大学院新領域創成科学研究科博士(環境学)。麗澤大学教授、日本大学教授、東京大学特任教授を経て現職。また、財団法人日本不動産研究所研究員、株式会社リクルート住宅総合研究所主任研究員、キャノングローバル戦略研究所主席研究員、金融庁金融研究センター特別研究官などの研究機関にも従事。専門は指数理論、ビッグデータ解析、不動産経済学。主な著書に『不動産市場分析』(単著)、『市場分析のための統計学入門』(単著)、『不動産市場の計量経済分析』(共著)、『不動産テック』(編著)、『Property Price Index』(共著)など。 マサチューセッツ工科大学不動産研究センター研究員、総務省統計委員会臨時委員を務める。米国不動産カウンセラー協会メンバー。