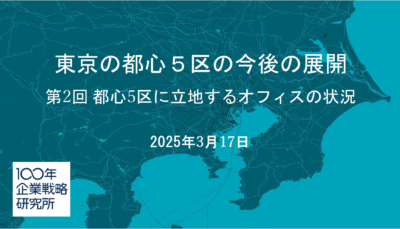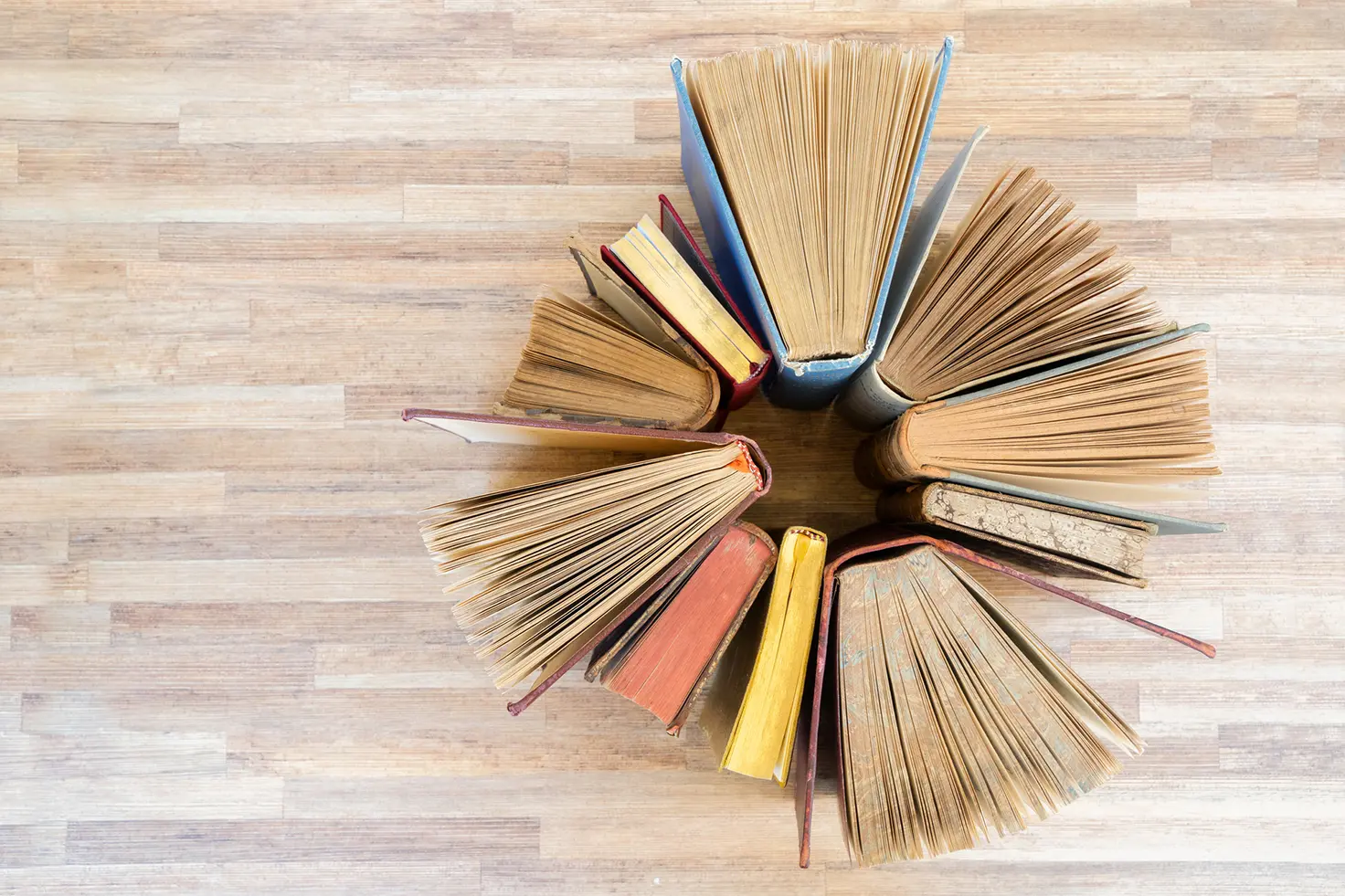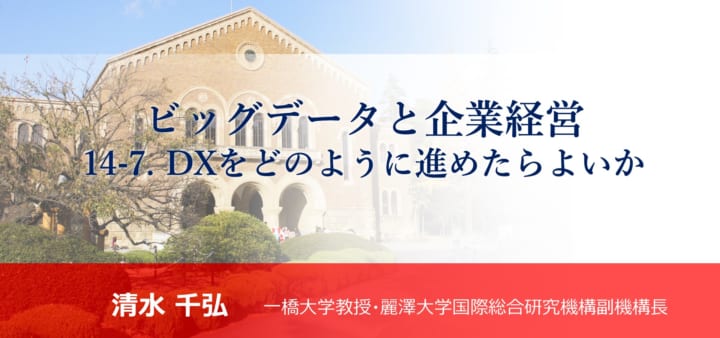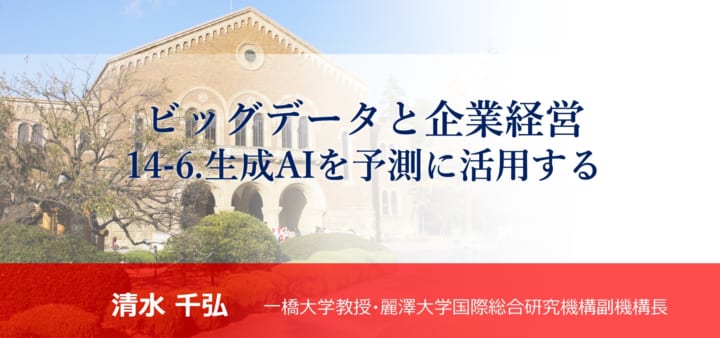生産性が向上!?注目を集めるシェアオフィスの活用方法とは?

目次
※百計オンラインの過去記事(2018/06/25公開)より転載 最終更新日(2025/08/22)
近年、ビジネス環境の急速な変化に伴い、働き方に関するさまざまな選択肢が広がっています。とりわけ、都市部のオフィス事情は多様化が進み、新規事業やスタートアップ企業だけでなく、大手企業でも柔軟なオフィス空間を求める動きが加速しています。新型コロナウイルス感染拡大を機に、テレワークやハイブリッドワークを取り入れる企業が増えたことで、「どこでも仕事ができる」「無駄を省いて効率を高めたい」という考え方が広く受け入れられるようになりました。その流れの中で注目が集まっているのが“シェアオフィス”です。
シェアオフィスは、一般的な賃貸オフィスと異なり、さまざまな所属の人が同じ空間で働くコワーキングスペースなどの共用部を備えています。利用者にフレキシブルな契約形態や充実した設備をもたらす点が特徴です。仕事を進めるためのデスクやインターネット環境はもちろん、受付サービスや会議室の利用など、従来のオフィスよりも自由度が高く、気軽に導入しやすいのが魅力といえるでしょう。
特に渋谷や新宿をはじめとする東京の主要エリアでは、スタートアップ企業の注目度が高いことや、若い世代が集まる商業地としてのブランド力によって、コワーキングスペースの数が増えています。リーダー層を含む多様なビジネスパーソンにとって、シェアオフィスは“働く場所”だけでなく、新しい人脈形成や情報交換ができるコミュニティとしての側面も担います。こうしたオフィス環境をうまく活用することで、企業全体の生産性向上やタイムマネジメントの改善にもつながる可能性があります。
本コラムでは、シェアオフィスが注目される背景や、市場の現状と今後の展開、実際にシェアオフィスを導入する際のポイントなどを解説します。経営者やビジネスパーソンにとって、新しいオフィス戦略を考えるうえで押さえておきたい情報を盛り込んでいますので、ここで得られる知識を踏まえ、自社におけるオフィス活用方法を再検討する機会としてご活用ください。
シェアオフィスが注目される背景
コロナ禍での働き方の変化とニーズ
コロナ禍によるテレワークの普及は、既存の働き方の常識を大きく覆しました。従来は「オフィスへ毎日通勤するのが当たり前」という認識が根強く、企業も固定費としてオフィス賃料を確保することを前提に経営を行ってきました。しかし感染拡大防止策として在宅勤務が推奨されるようになると、「出社しなくても業務が回る」「システムを整えれば離れた場所でもコミュニケーションが取れる」といった新しい発想が浸透し、これまで比較的限定的だったリモートワークが一気に拡大しました。
コロナ禍収束後はオフィス回帰の動きとともに、オフィスはコミュニケーションの場としての役割が求められ、フリーアドレス化や社内カフェの設置など、柔軟な働き方ができる環境を充実させる企業が増えてきました。
その結果、「オフィスは必要だが、必ずしも全員が毎日同じ場所に集まる必要はないのではないか」という疑問が生まれ、より柔軟なオフィス形態を望む声が高まりました。そこで脚光を浴びたのが、シェアオフィスやコワーキングスペースです。必要な日に必要な人数分だけ利用できる形態であれば、コストを抑えつつ適度なコミュニケーションを確保できます。
さらに、通勤が不便な地域から通う負担を軽減したいという要望も後押しし、オフィス形態の選択肢のひとつとしてシェアオフィスのニーズが高まっているのです。
柔軟なワークスペースを求めるニーズの増加
コロナ禍以前からも「ワークスペースを共有する」という考え方への興味は少しずつ高まっていました。企業成長の初期段階で固定的なオフィス契約を結ぶのはリスクが大きいと判断するスタートアップや、支社機能を最小限に留めたい企業の新規部署などが、コワーキングスペースを利用するケースが目立ちはじめました。
こうした柔軟なワークスペースは、プロジェクト単位での短期契約や、移転のしやすさなど、利用者にとって大きなメリットがあります。また、利用時間や利用人数を調整しやすいため、ビジネスパーソンにとって「物理的・時間的な制約から解放される」感覚が得られ、業務効率が上がるケースが多いのも特徴です。
特に渋谷のようにITベンチャーやスタートアップ企業が集まる地域では、シェアオフィスが事業者同士を結びつけてイノベーションを生み出すマッチングの場としての機能を果たすようになり、注目を集めています。

拡大するシェアオフィス市場の現状と今後の展開
新たに参入する企業と施設数の増加
シェアオフィスの潜在的ニーズが高まったことで、従来からの専門事業者だけでなく大手不動産会社や新興ベンチャー企業など、幅広いプレイヤーが新規参入をはじめています。たとえば、商業施設の一角やビルの空きフロアをシェアオフィスに作り替える動きがみられ、既存のホテルを一部コワーキングスペースとして改装する事例も増えたています。こうした多様な業態の参入は、利用者にとっては選択肢が増えることになります。
さらに施設数の増加により、都心部だけでなく郊外や地方都市でのシェアオフィス展開も進んでいます。インターネット環境が整備されていれば、企業の事業拠点は都心に集中させる必要はなくなり、「自宅近くのシェアオフィスに出社する」という働き方も視野に入ります。今後は幅広い地域でシェアオフィスが浸透していくことが予想されます。
市場競争がもたらすサービス向上の可能性
シェアオフィス市場が拡大すると競争が活発化し、利用者獲得のためのサービス向上が期待できます。たとえば、オフィス機能だけではなく、カフェラウンジやオンライン会議の専用ブース、専用アプリでの予約管理やコミュニティ機能など、付加価値の高いサービスを提供する施設が増加するでしょう。また、企業ニーズに合わせて、初期費用の免除や短期間の試験導入プランなど、契約形態の柔軟化も進むとみられます。
このように、シェアオフィス業界の競争は、利用者にとって利便性の向上やリーズナブルな料金体系、インテリアや共有設備のクオリティ向上をもたらす可能性があります。結果的に、企業の選択肢が豊富になり、シェアオフィス導入のハードルが下がることが予想されます。特に渋谷のように人材の流動性が高い地域では、最新の設備やネットワーキングイベントなどを通じて、スピード感のあるビジネス構築ができる環境が整いつつあります。
多様な働き方を生み出すシェアオフィスの活用方法
リモートワークとの相性とチームマネジメント
リモートワークやハイブリッドワークの導入が一般化している現在、シェアオフィスはチームマネジメント上の課題を解決する手段としても注目されています。自宅で作業することが多くなると、上司や同僚と接する機会はオンラインミーティングばかりとなり、人間関係やコミュニケーションの質に影響が出るケースもあるでしょう。そこで、必要に応じて週に数回だけシェアオフィスに集まるなど、対面で意見交換することで信頼関係を保ちやすくなるのです。
また、チームの中にはクリエイティブなアイデアを生むために直接会話したほうがよい人材や、集中できる環境が必要な人材など、個々に得意とする働き方や業務に適した環境が異なる場合もあります。リモートワークを基本にしながら、「必要なタイミングで柔軟にシェアオフィスを使う」という形態であれば、メンバーの生産性やモチベーションを維持しやすいと考えられます。
関連コラム
ビジネスパーソンに求められる時間と場所の有効活用
シェアオフィスを活用する際、ビジネスパーソンにとって大切なのは「時間の使い方」「場所の選び方」という視点です。たとえば外出が多い営業担当者なら、クライアントのオフィスやイベント会場から近いシェアオフィスを拠点にすると効率的に時間を使うことができ、移動コストも下げられます。一方で、開発やデザインなどの集中作業が多い職種の場合、静かな環境が整ったシェアオフィスを選択することでパフォーマンスが上がるでしょう。
さらに、シェアオフィスを利用することによって、人脈形成や新たなビジネス連携のチャンスを得られる点も見逃せません。多様な業種が集まる空間では、普段の業務だけでは得られない最新情報や、ほかの業界とのコラボレーション機会が生まれることがあります。そうしたシナジーが、リーダー層の能力開発にも好影響をもたらす可能性があるのです。

シェアオフィス導入による効果と導入時のポイント
コスト管理・生産性向上・コミュニケーション力向上
シェアオフィスを導入する場合、固定費の負担を抑えられる点がよくあげられます。専有オフィスを借りるとなると、敷金や礼金、独自の設備投資など初期費用が大きく、座席数に応じた広いスペースを確保しなくてはなりません。一方、シェアオフィスでは、デスクや会議室などの共用部を複数の利用者で使用するため、利用者単位のスペースに対する料金が安く設定されているケースが多いです。契約の柔軟性が高いこともあり、事業規模に応じてスムーズな調整が可能です。
また、シェアオフィスはレイアウトや内装も工夫されていて、利用者同士が自然にコミュニケーションを取りやすいデザインが特徴です。スタッフやほかの利用者とのやり取りが活発なコワーキングスペースを利用すれば、新規事業のアイデアが生まれることや、意外なコラボレーションのきっかけを得られることもあります。
生産性の観点では、「オフィス環境に関する雑務を最小限に抑えられる」という点があげられます。多くのシェアオフィスは、受付・清掃などの間接業務を施設側が担うため、利用者は本来の業務に集中しやすくなります。インターネットやセキュリティシステムが整っているところであれば、管理コストや保守業務を極力削減できるでしょう。
リーダー人材育成やエンゲージメントへの効果
シェアオフィスを利用することで期待できる効果のひとつとして、リーダー層のさらなる成長があげられます。新しい環境に身を置くことで視野が広がり、自社内だけでは得られない発想や情報に触れる機会が増えるからです。また、自主的に人脈を築き、コミュニティを活用する姿勢は、リーダーにとって欠かせない知識やスキルを磨くチャンスとなります。
さらに、社員同士が同じ場所に集まる機会が減る一方で、シェアオフィスを活用して就業環境をアップデートすると、個々が自主的に交流の場をつくろうとする動きが見られるようになります。結果として、組織全体のエンゲージメントやチームワークが高まり、新しい業務の進め方が社内に根付くきっかけにもなるでしょう。
関連コラム
物件選定や契約形態を見極めるポイント
シェアオフィス導入を検討する際には、いくつかの重要な視点があります。まず、「立地の利便性」です。都市部であれば、最寄駅からの所要時間、主要ターミナル駅までのアクセスなどの確認も欠かせません。また、渋谷や新宿などのビジネスが盛んなエリアは、オフィス使用だけでなく人脈形成や採用活動上のブランディングという観点でも有利となるでしょう。
次に「設備や付帯サービス」です。インターネット環境やセキュリティ体制のほか、会議室や打ち合わせスペース、専用スペースの有無、受付サービスの有無をチェックしておきましょう。コミュニティ開催やイベントスペースを備えていると、外部とのつながりを広げたい企業にとって大きなアドバンテージになります。
施設によってはシェアオフィスの住所を法人登記に使用することや、郵便の受け取りができるサービスもありますので、必要に応じて確認してみましょう。
最後に「契約形態の柔軟性」を確認することも大切です。拠点を増やすかどうか迷っている場合、短期契約プランが用意されているシェアオフィスは導入リスクの軽減につながります。社内での利用人数や頻度に合わせたプランがあるかどうかを確認し、自社に合った最適なオフィス環境を選びましょう。
新時代のシェアオフィスの可能性
経営者・ビジネスパーソンが知っておきたいメリット
シェアオフィスは、企業規模を問わず、これからの時代に必要な柔軟性や機動力を与えてくれる選択肢だといえます。初期費用を抑えられるだけでなく、オフィスレイアウトをはじめとする煩雑な管理作業への負担が軽減されるため、企業として本来取り組むべきプロジェクトやイノベーションの創出に集中しやすくなります。さらに、さまざまな業種や職種の人々が集い、最新の情報が飛び交うコワーキングスペースでの交流は、ビジネスを加速させるヒントに満ちています。
リーダー人材を成長させる場としても有効であり、新しい人脈形成や多角的な学びの場が用意されていることは大きなアドバンテージです。特に渋谷にはITベンチャーを中心とした若い企業が多く集積しており、活発なビジネスコミュニティが形成されています。こうした環境を活用することで、企業内の多様な才能を刺激し、新事業や新サービスを生み出す原動力にできるでしょう。
今後の企業成長に向けたオフィス戦略のひとつとして
シェアオフィスは、単なるビジネス拠点ではなく、柔軟な働き方を取り入れるためのプラットフォームの役割を担います。リモートワークやハイブリッドワークを活用しながら、自社の拠点戦略の一環としてシェアオフィスを活用することで、働き手のモチベーション維持と生産性の向上を同時に実現できる可能性があります。オフィスワークの在り方が見直される今だからこそ、実際に利用するメンバーの声をよく聞きながら、どのような場所が適切か検討を重ねることが肝要です。
今後を見据えると、企業規模の拡大や人材の拡充に合わせて新たな拠点が必要になるケースも少なくありません。シェアオフィスという選択肢は、多様なニーズに対応しやすく、高い柔軟性を持っています。自社独自の文化が育まれるように上手に使い分ければ、企業としてのアイデンティティを維持しながら業務効率の高い体制をつくれるでしょう。
シェアオフィス市場は今後も成長が予想され、機能やサービスの拡張、コミュニティ支援の充実などがさらに進む可能性があります。経営者やビジネスパーソンが持つ課題を解決し、チャンスを広げるための手段として、シェアオフィスは“新時代のオフィス戦略”の候補として押さえておきたいところです。企業としての将来を見据えるうえで、こうした柔軟な働き方を前向きに取り入れてみる価値は十分にあるといえるでしょう。
いま一度、自社の働き方やオフィス環境を見直してみてはいかがでしょうか。シェアオフィスを効果的に活用することで、新たな成長のステージへと進むきっかけを得られるかもしれません。