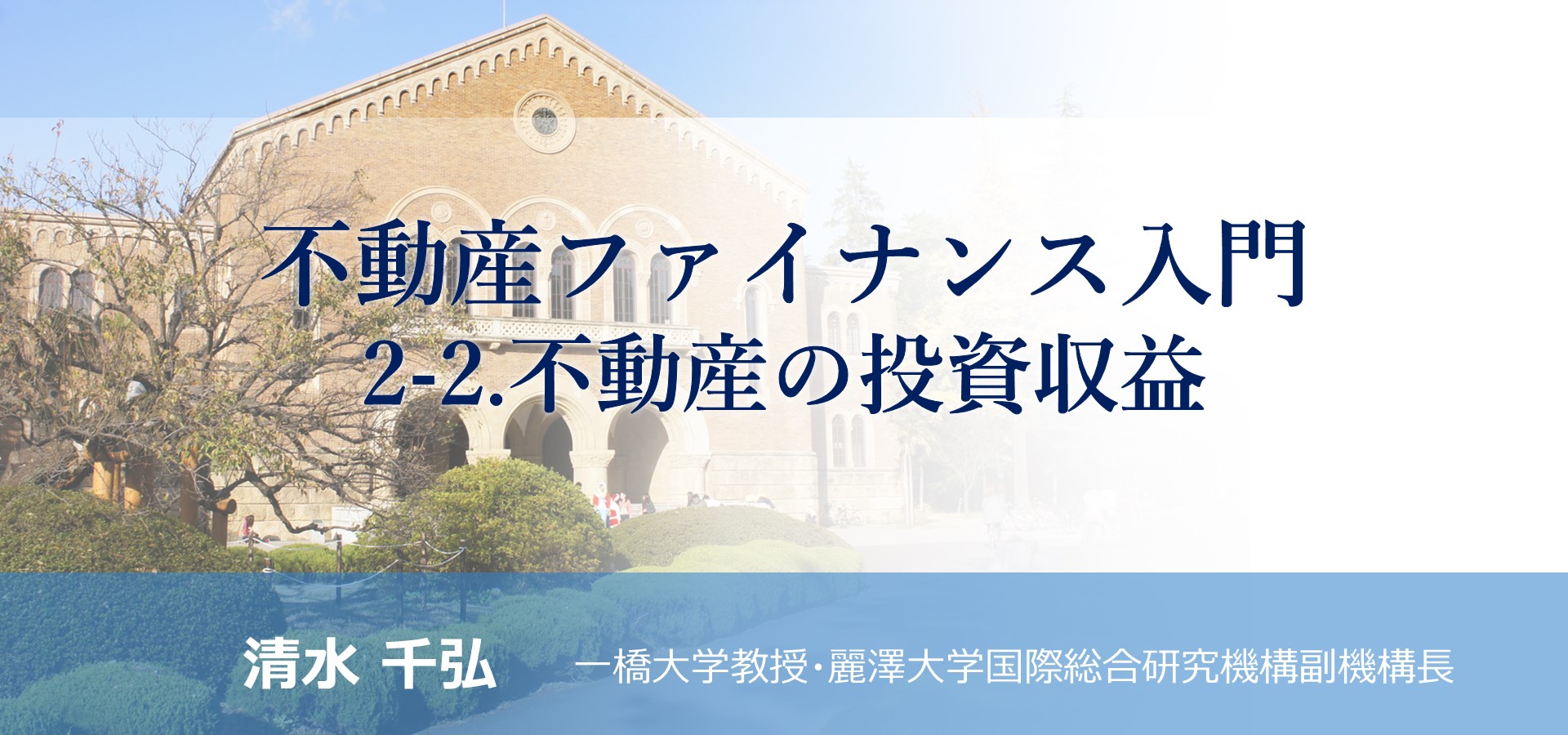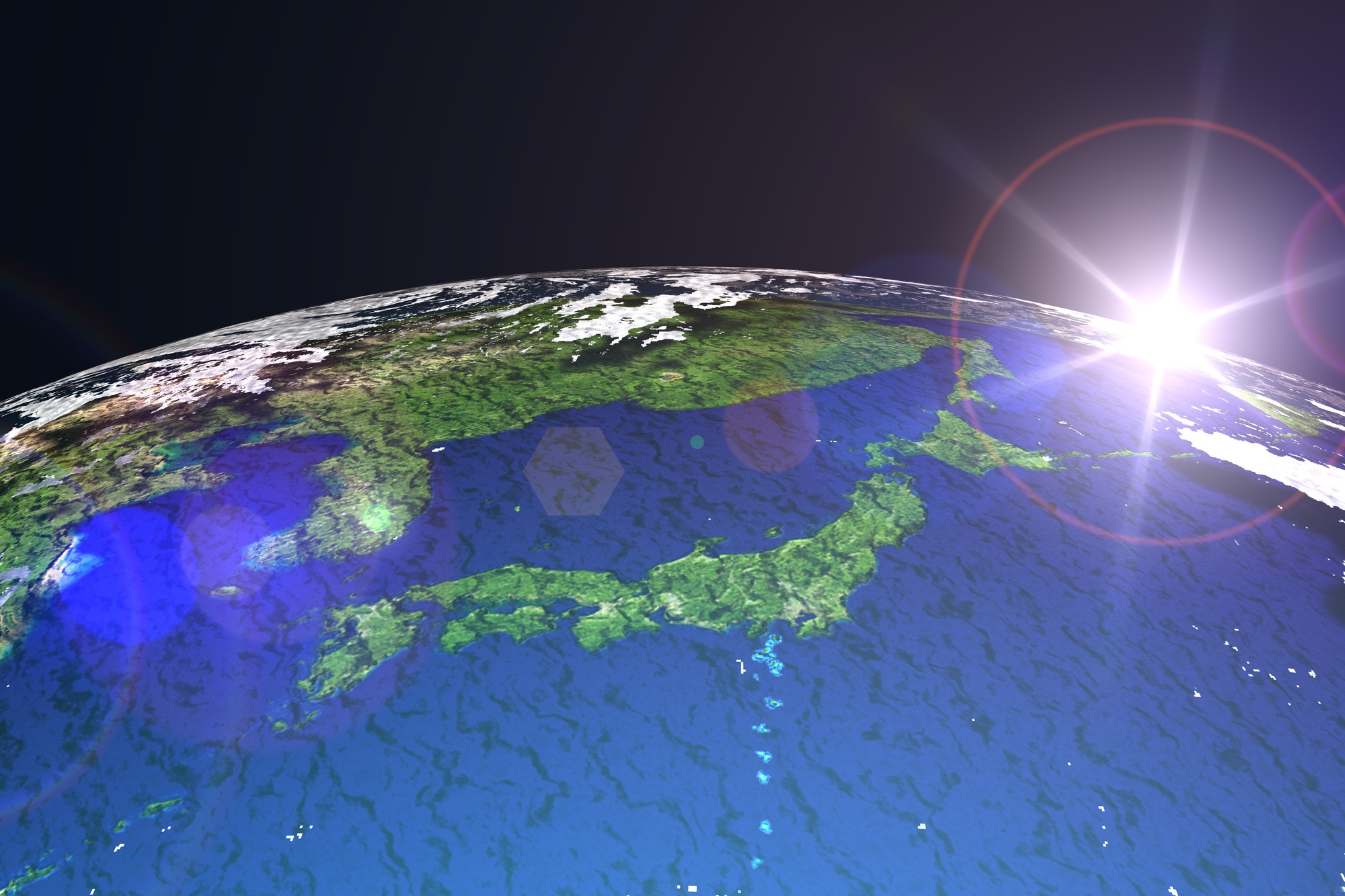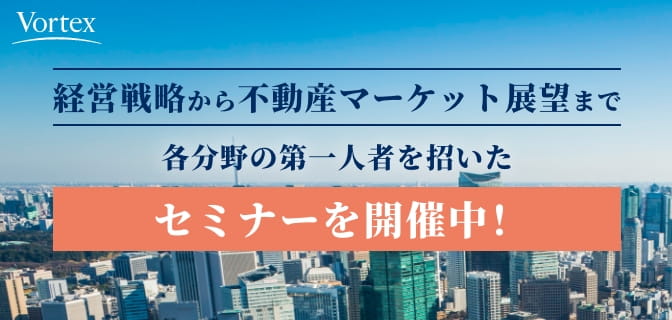プロパティマネジメントとは?業務内容や必要資格、役割、将来性を解説

目次
記事公開日:2020/03/11 最終更新日:2023/12/12
不動産という「箱」に人の力で価値を与える仕事があります。それが「プロパティマネジメント(Property Management)」です。PM(ピーエム)と略されることもあり、不動産に馴染みがない人にとっては聞きなれない言葉かもしれません。今回はプロパティマネジメントとは何か、基本的な業務内容や必要資格、さらに近年プロパティマネジメントが重視されるようになってきた背景と将来性について詳しく解説します。
プロパティマネジメントとは何か?
プロパティマネジメントとは、いわゆる不動産の管理・運営業務のことを指します。「ホテルとワンルームマンション」を例にとると分かりやすいかもしれません。いずれも部屋の中に風呂やトイレ、ベッドルームなどがあり、旅館業法などの細かい点を除けば、不動産の「箱」としては、ホテルもワンルームマンションも不動産の成り立ちはよく似ています。
しかし、部屋という同じような不動産の「箱」であっても、その管理や運営の方法によって収益は異なります。例えば都内で同じ部屋を運営した場合、ホテルは1泊1万円として月30万円の売上を生み出しますが、ワンルームマンションにすると家賃として月10万円しか売上を上げることができない部屋ということになります。
この差はなぜ生まれるのでしょうか。それは人が部屋をホテルとして運営し、ホテルとして管理するというプロパティマネジメントのサービスが入るためです。人の力によって、月30万円稼げる「箱」になるのです。
管理している不動産の収益をどのようにして最大化するのか、戦略的に運用計画を立てて「箱」の魅力を引き出すことが、プロパティマネジメントとしての責務といえるでしょう。
プロパティマネジメントの基本概念
プロパティマネジメントとは、不動産投資における重要な要素であり、オーナーの代わりに不動産の運営と維持を行う管理の専門分野を指します。
基本的な役割としては以下のようなものがあります。
テナントの管理
テナントの募集、選定、契約、契約更新、クレーム対応などが含まれます。
物件の管理と維持
建物の定期的な点検やメンテナンス、修理、清掃などが含まれます。
財務管理
家賃の収集と追跡、費用の支払い(税金、保険、メンテナンス費用など)、財務報告などが含まれます。
マーケティングと広告
物件の空室を満たすためのマーケティング活動や広告を行います。
法律と規制の遵守
地方や国の法律、規制に従って物件を管理します。
これらの活動は、不動産の価値を維持または向上させ、オーナーに対するリターンを最大化することを目指しています。プロパティマネジメントは、不動産の成功を大きく左右するため、不動産投資においては非常に重要な役割を果たします。
プロパティマネジメントの役割と重要性
これまでのプロパティマネジメントは賃料徴収や督促などの会計業務、賃上げ交渉やクレーム処理などのテナント対応、清掃や警備などビルメンテナンス会社への指示などが主な業務でした。しかし近年は不動産オーナーへの空室対策提案や優良テナントに長期間入居してもらうためのテナント維持活動なども手がけるようになり、その業務内容は高度化しています。一昔前なら、ビル管理といえば定年後の高齢者がのんびり仕事しているようなイメージもありましたが、今やその様相はまったく変わり、オーナーやテナントに対して積極的に提案を行い、不動産の価値を高める活動を行うアグレッシブな会社も多いです。

普段テナントと接する機会の多い管理会社は、お客様であるテナントの声を最もよく把握している存在です。そんな管理会社の提案する空室対策が有益なものとなるのは自然なことでしょう。オーナーとしては実力ある管理会社にプロパティマネジメントをさせることで、空室が発生しても有効な対策を取ることができます。
高い賃料を払い長く入居してくれているテナントを大切にすることも肝要です。ここで優良テナントに行き届いたサービスを提供するのも、プロパティマネジメントの役割です。
また、近年では環境への配慮、コミュニティへの貢献など、社会的な要請に応えながら物件を運用することを求められるようになってきました。プロパティマネジメントは、長期的な視点で物件価値を維持するだけでなく、ステークホルダーからの信頼を得る重責をも担っているのです。
ESGに関するコラム
プロパティマネジメントの基本的な業務内容
一口にプロパティマネジメントといっても、その業務は多岐にわたります。大きく3つの基本的な業務について、確認していきましょう。
収益最大化のための賃貸管理(リーシングマネジメント)
賃貸用不動産において、不動産オーナーの代わりに集客活動や管理業務を実行するのが、リーシングマネジメントの役割です。
具体的には、空室物件へ新たなテナントを獲得するために、集客活動として広告、仲介会社へ情報提供、不動産流通標準情報システム(レインズ)への登録等を行います。
物件への問い合わせ対応や、顧客(仲介会社)を現地案内することも日々の業務となります。申込が入れば、申込書や対応時のやり取り、テナントの属性などを勘案し、管理会社としての意見・判断を整理してオーナーへ報告します。時には条件交渉を行い、契約がまとまるように動く必要もあります。
オーナーの承認がおりれば、賃貸借契約を結び、入居が済めばひと区切りとなります。更新の手続きやクレーム対応もリーシングマネジメント業務の一部といえます。
設備管理とメンテナンス、テナントマネジメント
管理受託した物件について共用部分の補修・修繕、現場の清掃、警備や巡回、管理人業務、各種設備の点検修理・管理等をはじめ、ハード面の管理業務を行います。
また、テナントへの毎月の請求業務や支払い業務、建物の管理費・修繕積立金の会計、定期総会や理事会を支援するといったソフト面の管理業務もあります。
資産管理(コンストラクションマネジメント)
一棟での管理を受託している場合、修繕費用の平準化や建物の長寿命化を目的として、中長期修繕計画の策定を行います。また、定期的な建物診断や消防点検、大規模修繕工事等をスムーズに実施するためには、管理組合や入居者との信頼関係を築く必要があります。
プロパティマネジメント業務に必要な資格
プロパティマネジメント業務上で必須の資格はありませんが、次にあげる資格を取得すれば、就職の際に有利となったり、昇格のためにプラスで働いたりします。もちろん、仕事を行う際の知識としても役に立ちます。
宅地建物取引士(宅建士)
宅地建物取引業法に定められた不動産取引における専門家であることを証明する国家資格。毎年20万人前後が受験する国家試験に合格し資格を取得します。不動産業界だけなく建築業界、金融業界等でも活躍が期待されます。宅建士には独占業務があります。また、宅地建物取引業者には宅建士の設置義務があるため、営業、事務系といった職種を問わず取得を推奨されるケースがあるようです。
独占業務
宅建士には3つの独占業務があります。
1つ目は「重要事項の説明」で、売買や賃貸の契約成立前に買主・借主に対して物件に関する重要事項の説明を行う業務です。不動産は高額で取引されることがありますが、不動産に関する知識や経験について売主・貸主と比べると買主・借主の方が少なくなってしまうため、宅建士が重要事項の説明を行い、契約後のトラブル等を極力抑える必要があります。
2つ目が「重要事項説明書への記名」で、重要事項説明書の内容が正しく記載されているのかを確認したうえで宅建士が記名を行います。
3つ目が「契約書(37条書面)への記名」で、こちらも重要事項説明書同様に、内容が正しく記載されているのかを確認したうえで宅建士が記名を行います。
重要事項説明書と契約書の違いは、「購入する」「借りる」といった最終判断のための情報のひとつが重要事項説明書で、その内容に納得し契約を取り交わしたという証明が契約書となります。
※2022年の法改正により、重要事項説明書や契約書へ宅建士の押印は不要となりました
設置義務
宅地建物取引業法(第三十一条の三)において、事務所等ごとに5人に1人以上の割合で「成年者である専任の宅地建物取引士」を置かなければならないと定められています。例えば、ある事務所の従業員が21人の場合は、その内5人以上が専任の宅建士でなければいけません。
管理業務主任者
マンションの管理の適正化の推進に関する法律により定められた国家資格で、マンション管理のマネジメントをメイン業務としています。マンション管理業を営むには、管理業務主任者の設置義務があります。さらに、管理組合等に対する特定の業務は、資格を持つ者だけが行える独占業務となっています。
独占業務
管理業務主任者には4つの独占業務があります。
1つ目は「管理受託契約に関する重要事項説明」です。管理受託契約成立前にマンション管理業務者は管理組合に対し、管理業務主任者をして、管理事務の内容や契約期間等の重要事項を説明させなければいけません。
2つ目は「管理受託契約書に関する重要事項説明書への記名」です。重要事項説明書の内容が正しく記載されているのかを確認したうえで管理業務主任者が記名を行います。
3つ目は「管理受託契約書への記名」です。こちらも重要事項説明書同様に、内容が正しく記載されているのかを確認したうえで管理業務主任者が記名を行います。
4つ目は「管理事務に関する報告」です。マンション管理業者は定期的に、管理組合に対し、管理業務主任者をして、管理事務の状況等を報告させる必要があります。
設置義務
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(第五十六条)において、事務所ごとに委託を受ける管理組合30組合につき1名の管理業務主任者を設置することが定められています。
マンション管理士
宅地建物取引士や管理業務主任者と同じ不動産にかかわる国家資格で、3つの中では合格率が低いこともあり、難易度が高いとされています。マンション管理士には設置義務や独占業務はありませんが、建築基準法や消防法、マンション管理の適正化の推進に関する法律などの適用を受ける事項等、マンション管理にかかわる法令を理解し、その遵守を確保することが求められます。
管理業務主任者がマンション管理会社側に立って管理に携わるのに対して、マンション管理士はスペシャリストとして管理組合や住人からの相談に応じ、マンションの管理運営に関する総合的なサポートを行います。また、マンションの長期的な価値向上や生活品質の向上を目指して、必要に応じて専門的なアドバイスも提供します。
不動産の価値をあげるプロパティマネジメントの成功事例
シェアハウス導入による空室率改善の事例
プロパティマネジメントの重要性の認識は、ここ数年、不動産オーナーの中でも高まってきています。シェアハウスが成功しはじめたことも不動産オーナーの意識を変えた要因として大きいと思われます。管理・運営面で見ると、シェアハウスはワンルームマンションとホテルの中間に位置します。ワンルームよりは煩雑な業務が多いですが、ホテルほどは求められません。今まで空室だった賃貸マンションに、シェアという管理・運営サービスを加えたことで、空室率を改善し収益を上げる部屋に生まれ変わったのです。このシェアハウスの成功により、最近では管理・運営次第で不動産の価値があがることを不動産オーナーも認識しはじめています。
新たな運営方法による資産価値の向上事例
このほか、オフィスをコワーキングスペースに、月極駐車場を時間貸し駐車場にすることで、不動産の価値をあげている例などがあります。いずれも不動産に新しい管理・運営を加えたことで、不動産の価値を高めています。また地方自治体が保有している体育館やプールに大手スポーツクラブが運営として参入したことで収益が改善している例もあります。これも広義でプロパティマネジメントによる成功事例に含めていいでしょう。
このようにシェアハウスなどの住宅系に限らず、オフィスや倉庫、商業施設といったあらゆる不動産において、プロパティマネジメントはその価値を高める役割を果たしているのです。

プロパティマネジメントが求められる背景
このようにプロパティマネジメントが重視されるようになったのには、日本が人口減少社会に入り、賃貸事業における空室率の高まりも要因としてあげられます。これまでのような単なる箱貸しでは空室は増加するばかりで、不動産の価値が下がるようになってしまいました。この価値下落を防いでくれるのが、テナントにサービスを与えるプロパティマネジメントなのです。住宅やオフィスも一つの施設と捉えれば、プロパティマネジメントという施設運営力を加えることで、住宅やオフィスという施設の価値を維持できるようになります。
不動産投資の収益最大化にはプロパティマネジメントが必要
不動産投資を行ううえで、最も意識しなければならないのは空室リスクでしょう。空室状態が長引けば、賃料を下げざるを得なくなり賃料下落リスクが発生します。ここで賃料を下げてもテナントが入らなければ、さらに空室対策用のリノベーションなどを行うことになり、修繕費リスクも発生します。空室は収入を下げるだけでなく、新たな追加投資の必要まで迫られるものなのです。団塊の世代が退職し、就労人口も減っている現在、空室リスクの問題は住宅に限らず事業系のオフィスであっても意識しなければならない問題となっています。
また建物は放っておけば古くなり、その価値は自然と下がってしまいます。その下落を抑えるのもプロパティマネジメントの仕事です。通常プロパティマネジメント会社には、ビルの清掃や設備点検などを行うビルメンテナンス会社が連携する形をとります。プロパティマネジメント会社が入ることで、例えばビル清掃会社に細かく指示を出すなどの目配りが可能です。また人の目が介入することによりビルの美観が保たれ、オフィス利用者に快適性を与えることもできます。行き届いた管理・運営をすることが、ビルに品格を与え築年数が経っても価値を維持することができるようになるのです。
プロパティマネジメントの将来性
下記3つの要因から、プロパティマネジメントの将来性は非常に高いと考えられています。
不動産価値の最大化
不動産は限りある資源であり、その価値を最大化するための専門的な知識やスキルが求められます。プロパティマネジメントの専門家が、物件の維持管理やリノベーション、適切なテナントの選定などを行うことで、不動産価値の最大化が達成されます。
都市の高齢化
都市化と高齢化が進む中で、不動産の需要は高まりつつあります。これにともない、不動産の適切な管理や運営がより重要になってきており、プロパティマネジメントの需要も増加しています。
テクノロジーの進化
IoTやAIなどのテクノロジーの進化により、不動産管理の効率化やサービスの向上が現実のものとなってきています。これらの技術を活用しながら、プロパティマネジメントはさらに進化し、その価値は増大すると考えられます。
不動産業界において、立地やビルスペックは物理的な要素である一方で、プロパティマネジメントはサービス面での要素と捉えられます。これら物理的な限界を超えるには、サービス面の強化が重要です。そのためには、不動産に新たな価値を生み出すための深い専門知識と先見の明が求められます。
プロパティマネジメントのトレンド
不動産業界も他の産業と同様に変化が進んでおり、特にデジタル技術とサステナビリティへの取り組みは重要なトレンドとなっています。
デジタル技術の活用
①ビッグデータ
テナントの行動パターン、市場動向、物件の状態、ビルのエネルギー消費量、稼働率、メンテナンス履歴などのデータを収集・分析することで、適切な改善策をタイムリーに実行でき、運営の効率化と質の向上、よりよい意思決定を支援しています。
②人工知能(AI)と機械学習
AIは、ビッグデータの解析や、テナントとのコミュニケーション(AIチャットボットなど)を円滑に行うために活用されます。また、機械学習は、物件の価値や需要の予測、メンテナンスの最適化、予測メンテナンスの実現などに用いられます。
③IoT (Internet of Things)
IoTデバイスを通じて収集されるデータは、ビルの運用やメンテナンスにおける洞察を提供し、エネルギー効率の最適化や予防的メンテナンスの実現など、より効率的なプロパティマネジメントを可能にしています。
サステナビリティへの取り組み
①エネルギー効率の改善
LED照明の導入や高効率設備への更新など、エネルギー効率を改善させる手段がいくつかあります。注目すべき具体的な事例として、「LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)」認証を取得している建物が存在します。LEED認証は、建物のエネルギー効率の改善と環境負荷の最小化を目指すものであり、これはプロパティマネジメントの戦略的な一部として重要な位置を占めています。
②再生可能エネルギーの利用
太陽光パネルの設置や風力発電の導入により、自然エネルギーを活用することで、環境への負荷を低減します。これにより、持続可能な社会に貢献するとともに、物件の運営コストの削減も期待できます。
③緑化プロジェクト
屋上庭園や緑豊かな共用エリアの設置、地元の自然を尊重したランドスケープデザインなどがあります。これにより環境負荷の軽減とともに、テナントの健康や満足度の向上にも寄与しています。
これらの取り組みは、プロパティマネジメントの効率と効果性を向上させるだけでなく、物件の価値を高め、テナントの満足度を向上させることも可能です。
不動産テックに関するコラム
まとめ
今後、不動産の価値を持続的に高めるためのプロパティマネジメントの役割は、ますます重要性を増していくでしょう。
つまり、プロパティマネジメントは将来性が期待できる分野であり、重要な役割を果たし続けることが予想されます。

著者
株式会社ボルテックス 100年企業戦略研究所
1社でも多くの100年企業を創出するために。
ボルテックスのシンクタンク『100年企業戦略研究所』は、長寿企業の事業継続性に関する調査・分析をはじめ、「東京」の強みやその将来性について独自の研究を続けています。